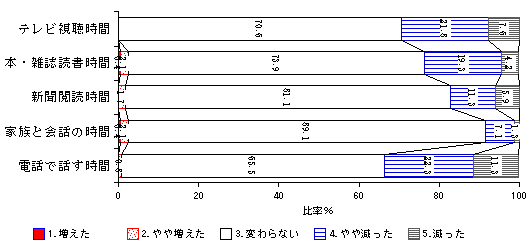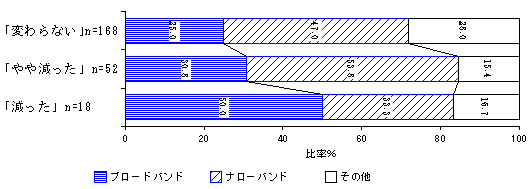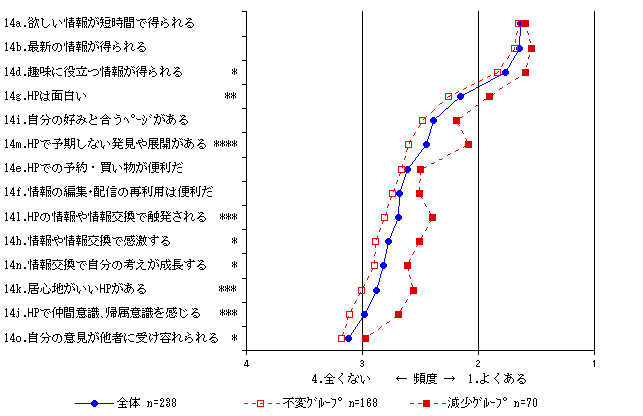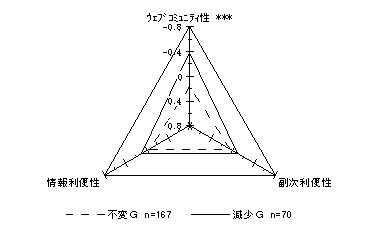日野調査における有効回答数502票のうちで、インターネット利用者は283人である。この人達によるインターネット利用後のメディア利用時間変化の質問に対する回答を、図3.3.1.1に示す。最も変わったのは電話で話す時間で、僅かに増えた人もいるが、「やや減った」も含めて34%の人は減少したと回答している。次いでテレビ29%、本・雑誌が24%、新聞が17%、家族との会話は8%の人が減少したと回答している。
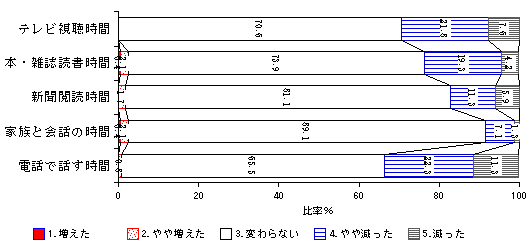
図3.3.1.1 インターネットに伴うメディア利用時間変化(日野n=238)
電話で話す時間の減少は、電話からメール利用へ移行することによって減少しているもので、この点も関心を惹く問題ではあるが、元々の利用時間がテレビほど長くないので、ここでは触れず、テレビの時間減少について話を進める。テレビの場合には、視聴時間が増加した人は居らず、「変わらない」、「やや減った」、「減った」の3グループがある。そこでこのグループ毎の平日のテレビ視聴時間を表3.3.1.1に示す。同表によると、インターネット利用前のテレビ視聴時間は分からないが、利用後では「変わらない」が最も長く152分、「やや減った」が次いで長く144分、「減った」はかなり減って、87分となっている。テレビ視聴時間には年齢が影響するので、念のために平均年齢を見ておくと、それぞれ40才、42才、35才であり、「減少」グループが比較的若年層であるが、通常の年齢分布での差よりもずっと大きい差が生じている(NHK2002)。
表3.3.1.1 平均のテレビ視聴時間(平日)と年齢
| グループ |
平均テレビ視聴時間(分) |
標準偏差 |
平均年齢(才) |
標準偏差 |
| 「変わらない」n=168 |
152.2 |
115.2 |
40.3 |
13.2 |
| 「やや減った」n=52 |
144.2 |
106.6 |
42.5 |
13.5 |
| 「減った」n=18 |
87.2 |
71.1 |
35.1 |
10.9 |
またこの3グループにおいて最も多く利用しているインターネット接続法を見ると、「変わらない」、「やや減った」では電話やISDNなどのナローバンドが多いのに対して、「減った」ではブロードバンドが50%で最も多い。しかしこの場合にはナローバンドも33%あり、テレビ視聴時間の減少はブロードバンド化が影響している面はあるものの、それに固有な現象というわけではないことは分かる。
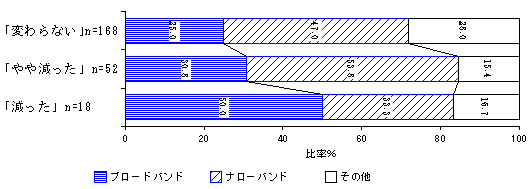
図3.3.1.2 テレビ視聴時間変化とインターネット接続法(日野)
これまでは年齢やインターネット環境の面から、テレビ視聴時間の減少を見てきたが、インターネットのウェブの利用を左右する最も大きい要因は、本人がウェブの利用からどのような満足、ないしは効用を得ているのかにあると考えられる。その効用によって、利用時間は長くなったり、または短かったりするであろう。そこでウェブ利用の効用面から、テレビ利用時間の減少の傾向を探ることとする。
HPを見てそれからどの様な種類の効用を得るかは、HPの利用目的によって異なるであろう。見るページによっても異なり、したがって人によって様々に異なることが考えられる。今まで述べてきた「減った」?「変わらない」の各グループの人たちの間でも、それぞれホームページの利用の仕方は大分異なることが予想される。その差を反映して、HPから得る効用の種類も異なることが期待できる。そこで本調査では、効用の得かたがどの様に異なるかを調べることにした。
効用の種類としては、利便性を中心とした機能的満足に関する効用と、様々な心理的満足を含む生活文化的満足に係わる効用が考えられる。これらの項目(設問)についてはマズローの心理学(ゴーブル1972)を参考にして、15個の設問を設定した。満足の種類としては、知識欲、自己表現、成長性、癒し、生活浸透、コンサマトリー、自尊心、愛・集団帰属、利便性を考えた。また八ッ橋(2002)を参考にした。
具体的な設問と集計結果を図3.3.1.3に示す。ここでは幾つかは実際の設問を短く記述して示している。例えば同図中の「14a.欲しい情報が短時間で得られる」については、回答者がこの様な効用を感じる度合を、「1.よくある」から「4.全くない」までの4段階で回答を求めている。これらの回答を集約したのが同図である。なお(1)で述べた「変わらない」を不変グループ(G)、「やや減った」と「減った」を減少グループ(G)として扱っている。この図から次の点を知ることが出来る。
-
不変Gは概して全体の平均の左側にあるのに対して、減少Gは右側にあること。つまり減少Gは評価対象の全部の効用について、HPから多くの効用を得ている。
-
全体での効用の高い項目(上部)では減少Gと不変Gの評価には有意差はない。つまり誰でも
評価する共通性の高い項目では両者には差は小さい。これらは「14a.欲しい情報が短時間で得られる」、「14b.最新の情報が得られる」などで、これらは機能的利便性に関する効用である。
-
評価項目の下の方が概して両者の差は大きく、差が有意となる効用も増す。有意差の度合の高い効用は減少Gに特に強く現れる。これらは「14n.HPで予期しない発見や展開がある」、「14k.居心地のいいHPがある」などで、これらが減少Gの特徴点を表わすことになると考えられる。
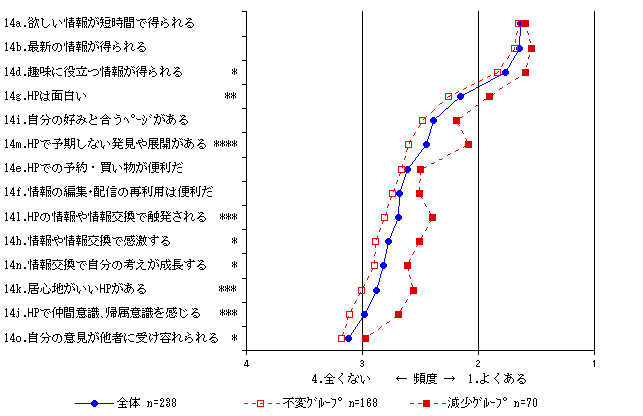
図3.3.1.3 ホームページの効用評価の平均値の分布
平均値の検定:*:p≦0.05、**:p≦0.01、***:p≦0.001、****:p≦0.0001
調査では上述したように、14個の効用についてデータを得た。しかしこの中には類似したものもあり、また14個では数が多すぎて、全体の構造が見えにくい点がある。そこでこれらに因子分析を適用して、議論を簡略化することを試みた。また図3.3.1.3によると、どの効用でも減少Gは不変Gよりもしばしばあるわけで、このことはこれらのデータに因子分析を適用した場合に抽出される因子スコアは、減少Gと不変Gではより大きい統計的な差を作り出す可能性が大きいことを示している。
そこで上記の14個の効用データに対して、因子分析を行った。その結果を表3.3.1.2に示す。
全体では3つの因子が抽出されており、分散の7割がカバーされている。各因子の名称は、ウェブコミュニティ性、情報利便性、副次利便性で、右の効用の項目群から作成されており、それぞれ適切な因子の解釈が出来ていると考えられる。
次ぎにこれらの因子が減少Gと不変Gでどの様に異なる傾向を持っているかを見るために、因子スコアの平均値を調べた。その結果を図3.3.1.4に示している。3つの因子軸は外側へ行くほどに、その因子の傾向が強まることを示しており、因子名の右についている*の印は、平均値の分離の有意性を示している。また各因子軸の0は全体の平均の位置を示している。
表3.3.1.2 ウェブの効用の因子分析結果
| 因子(平方和、寄与率) |
対応する変数(係数の大きい順↓ → ↓) |
第1因子 (4.93, 35.2%)
ウェブコミュニティ性 |
14j.仲間/帰属意識を感じる 14m.予期しない発見展開がある
14k.居心地がいいHPがある 14o.主張が他者に受け入れ
14l.情報交換で触発される 14h.感激するページがある
14n.自分の考えが成長する 14i.自分好みのページがある
◎仲間意識と居心地感のあるHPで情報交換・人脈が出来て快適なコミュニティが形成される。 |
第2因子 (3.17, 22.7%)
情報利便性 |
14b.最新の情報が得られる 14d.趣味に役立つ情報がある
14a.情報が短時間で得られる 14g.HPは面白い
◎欲しい情報、最新の情報、趣味に役立つ情報が簡単に得られる。 |
第3因子 (1.71, 12.2%)
副次利便性 |
14e.HPでの予約・買い物が便利だ
14f.編集・配信などで再利用できる便利さがある。
◎予約や買い物に利用したり、HPの情報を再利用したりする |
(注)平方和と寄与率はバリマックス回転後の値である。寄与率の合計は70.1%である。
この図から分かることを以下にまとめる。
-
第1因子ウェブコミュニティ性には、不変Gと減少Gの間で有意差があり、減少Gでは明らかにその傾向が不変Gよりも強い。
-
第2因子情報利便性、第3因子副次利便性は、両方ともに0の近くにあり、両グループ間には差はない。
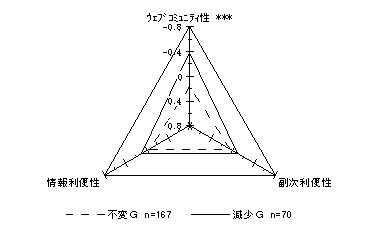
図3.3.1.4 テレビ視聴時間変化グループ別のウェブ効用因子スコア
***:分散分析 p≦0.001
この様にしてみてくると、様々なウェブ効用のうちでウェブコミュニティ性を活用している人は、概してテレビの視聴時間が減少し、そうでない人はテレビの視聴時間は変わらない、と言うことが出来る。情報利便性と副次利便性は、”利便性”の言葉に象徴されるように、効率概念である。それに対してウェブコミュニティ性は、”仲間意識”や”居心地の良さ”に象徴されるように生活文化的な概念である。その意味では、利便性の観点からウェブを利用している限りにおいてはテレビの視聴時間が減少すること、すなわちテレビからインターネットへ利用時間が移行することはないが、コミュニティとしてのウェブ利用の度合が高まると、テレビからインターネットへの利用時間の移行が起こると言うことが出来る。
そこで次にはこれらの因子の傾向をより具体的に見るために、因子を代表するグループを作り、その分析を通じて、移行の姿を明らかにしていく。