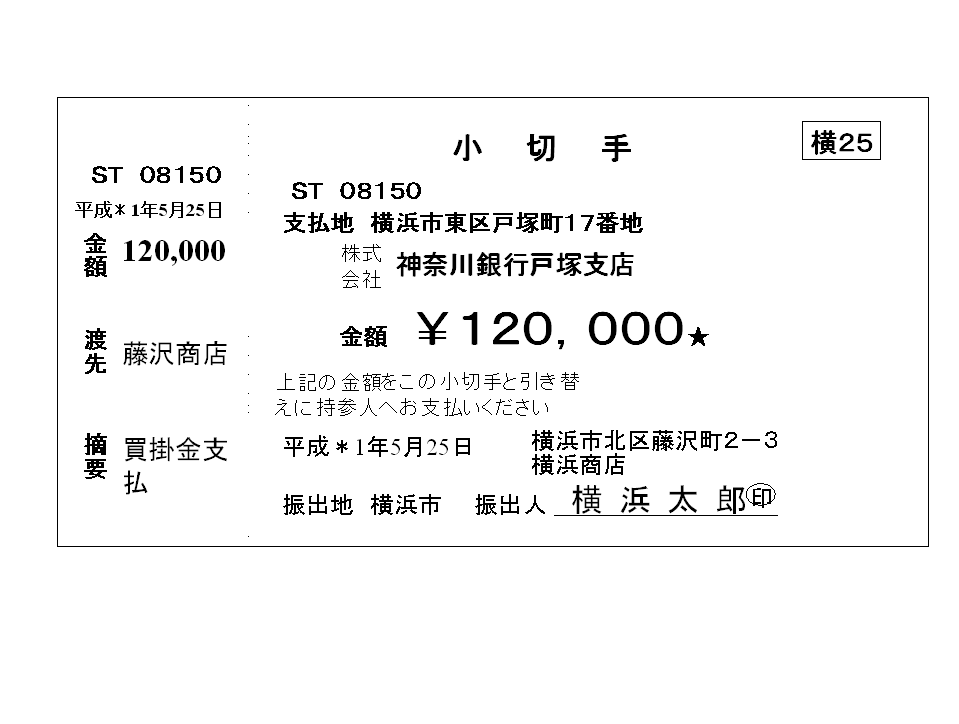
<取引例>横浜商店に商品を250,000円売り上げ、代金は横浜商店振り出しの小切手で受け取った。
(借) 現 金 250,000 (貸) 売 上 250,000
| 講 義 ノ ー ト |
〔第1回〕
「簿記演習A」の復習を行ないます。
〔第2回〕
◎現金取引
●現金
・現金として処理されるのは、通貨の他に通貨代用証券がある。
・通貨代用証券には次のものが含まれる。
他人振り出しの小切手
郵便為替証書
送金小切手
期限の到来した公社債利札など
・現金の収入は「借方」に、支出は「貸方」に記入される。
現 金
借方 貸方
――――――――――――――
前期繰越 ×××|支 出 ×××
収 入 ×××|次期繰越 ×××
|
・現金出納帳
| 平成 16年 |
摘 要 | 収 入 | 支 出 | 残 高 | |
| 9 | 1 | 前月繰越 | 583,250 | 583,250 | |
| 2 | 出張旅費 | 28,000 | 555,250 | ||
| 3 | 売掛金回収 | 52,600 | 502,650 | ||
以下略
・小切手の様式
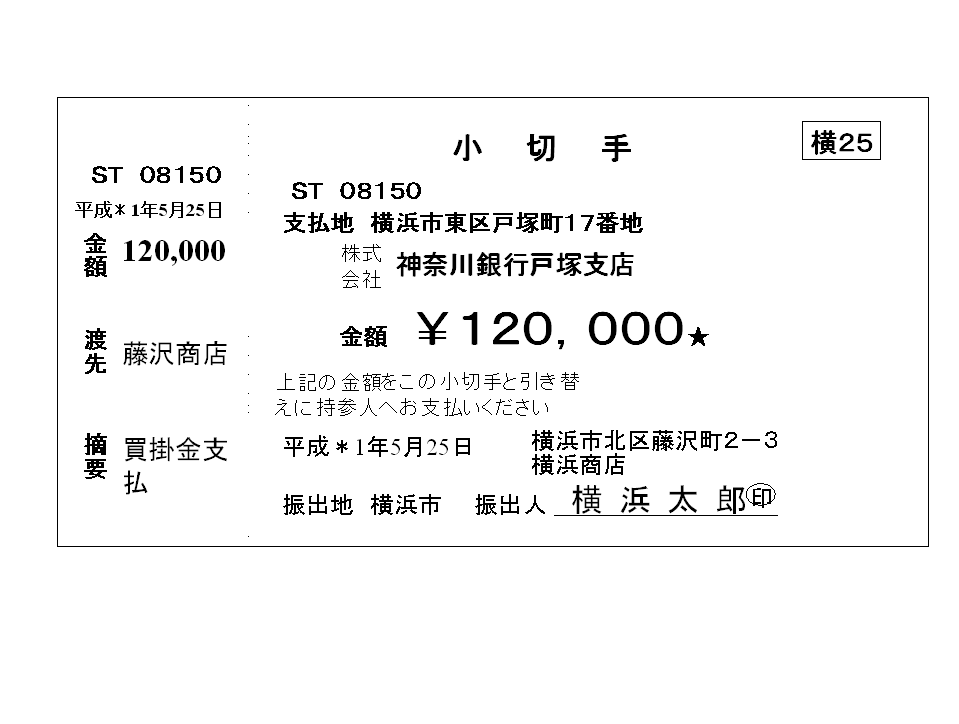
<取引例>横浜商店に商品を250,000円売り上げ、代金は横浜商店振り出しの小切手で受け取った。
(借) 現 金 250,000 (貸) 売 上 250,000
●当座預金
・当座預金(cash in bank)は、銀行に預け入れた、利息の付かない預金のことである。決済を現金を用いて行わず、小切手を用いるので安全性が高い。
・当座預金への預け入れは借方側、小切手の振り出しは貸方側に記録する。
当座預金
借方 貸方
――――――――――――――
前期繰越 ×××|振り出し ×××
預け入れ ×××|次期繰越 ×××
|
・当座預金出納帳
| 平成 16年 |
摘 要 | 預 入 | 引 出 | 借/貸 | 残 高 | |
| 9 | 1 | 前月繰越 | 1,423,600 | 1,423,600 | ||
| 3 |
売掛金の回収 | 330,500 | 1,754,100 | |||
| 4 |
商品の仕入 | 520,000 | 1,234,100 | |||
以下略
<取引例>
9/3 神奈川商店の売掛金330,500円を現金で受取り、ただちに当座預金に預け入れた。
(借) 当座預金 330,500 (貸) 売 掛 金 330,500
9/4 横浜商店より商品520,000円を仕入れ、代金は小切手を振り出して支払った。
(借) 仕 入 520,000 (貸) 当座預金 520,000
◎当座借り越し
当座契約の時に、しかるべき根抵当(有価証券など)を差し入れて預金残高を超えて小切手を振り出せるように契約することができる。これを当 座借越契約(または当座貸越契約)という。
当座預金の残高をオーバーする金額については「当座借越」勘定で処理する。これは一種の銀行からの借り入れであるので、預金残高がマイナスの期間に対する利息を支払わねばならない。そのためできるだけ早く当座預金に預け入れる必要がある。
<取引例>
①商品580,000円を仕入れ小切手を振り出して支払った。当座預金の残高は400,000円であるが、当社は取引銀行との間に500,000円の当座借越契 約を行っている。
(借方)仕 入 580,000 (貸方)当座預金 400,000
当座借越 180,000
②得意先の売掛金350,000円を現金で受け取り、ただちに当座預金に預け入れた。
(借方)当座借越 180,000 (貸方)売 掛 金 350,000
当座預金 170,000
●小口現金
・切手代や新聞代などの小口の代金の支払いをするために、小払係または用度係に前もって一定の金額を渡しておいてそこから支払をすることが行わ れる。これを処理するために現金とは別個に「小口現金」勘定を設ける。
・一定の金額を月初めに常に補充する方法を定額資金前渡制(インプレスト・システム)という。
小口現金
借方 貸方
――――――――――――――
最初の補充額 ×××|
|
|
・小口現金出納帳
| 受 入 | 平成 16年 |
摘 要 | 支 払 | 内 訳 | ||||
| 交通費 | 通信費 | 消耗品費 | 雑 費 | |||||
| 50,000 | 9 | 1 | 前月繰越 | |||||
| 3 | 切手 | 3,400 | 3,400 | |||||
| 5 | ボールペン | 2,300 | 2,300 | |||||
以下略
<取引例>
①当社は今月から定額資金前渡制を採用し、9月分の小口現金50,000円を小切手を振り出して用度係に渡した。
(借) 小口現金 50,000 (貸) 当座預金 50,000
②当月の小口現金の支払明細は次の通りであった。ただちに現金で補充した。
通信費 14,250円 消耗品費 18,880円 雑 費
5,790円
(借) 通信費 14,250 (貸) 当座預金 38,920
消耗品費 18,880
雑 費 5,790
※②の仕訳を行なえば、小口現金の金額は依然として最初に補充した金額のまま維持される。
〔第3回〕
●手形取引
・手形は将来の一定の日に支払うことを約束した証券であり、支払手段として小切手とともに用いられる。
・手形が小切手と異なるのは、手形を振り出すときに当座預金の残高がなくとも良いという点である。将来の一定の日(手形の満期日)にあればよいのである。
・手形には、法律上、約束手形と為替手形がある。場面に応じていずれかが利用される。
・簿記処理上は、受取手形と支払手形で処理される。
・「受取手形」勘定は手形の債権であるから資産であり、「支払手形」勘定は手形の債務であるから負債である。
◎約束手形の場合
振出人は手形債務者,受取人は手形債権者
取引例:A社はB社から商品150,000円を仕入れ、代金は約束手形を振り出して支払った。
A社の仕訳 (借) 仕 入 150,000 (貸) 支払手形 150,000
B社の仕訳 (借) 受取手形 150,000 (貸) 売 上 150,000
◎為替手形の場合
名宛人が手形債務者,受取人は手形債権者
取引例:C社はD社から商品200,000円を仕入れ、代金は得意先であるE社の引き受けを得て、同額の為替手形を振り出して支払った。
C社の仕訳 (借) 仕 入 200,000 (貸) 売掛金 200,000
D社の仕訳 (借) 受取手形 200,000 (貸) 売 上 200,000
E社の仕訳 (借) 買掛金 200,000 (貸) 支払手形 200,000
◎手形の裏書譲渡
保有する手形を支払に充てるために、手形の裏書をして引き渡すこと。
取引例:G社からの買掛金85,000円を支払うために、F社は保有するS社振出しの手形50,000円を裏書譲渡し、残額は現金で支払った。
F社の仕訳 (借) 買掛金 85,000 (貸) 受取手形 50,000 現 金 35,000
◎手形の満期決済
自社が振り出した約束手形や引き受けた為替手形の満期日が到来すると、取引銀行の当座預金の口座から自動的に引き落とされること。
取引例:A社は取引銀行から以前振り出していた約束手形150,000円の満期が到来したので当座預金から引き落とした旨の通知を受け取った。
F社の仕訳 (借) 支払手形 150,000 (貸) 当座預金 150,000
〔第4回〕
●手形取引(2)
◎手形の割引(売却)
資金の融通を受けるために所有する手形を裏書すること。そのさいに、割引料を支払うが、それを「手形売却損」勘定で処理する。
取引例:当社が保有する約束手形250,000円を取引銀行で割り引き、資金の融通を受けた。割引料4,500円を差し引かれた手取額は当座預金に預け入れた。
[解答]
(借方)当座預金 245,500 (貸方)受取手形 250,000
手形売却損 4,500
◎自己受け為替手形
自社を受取人として為替手形を振り出すことがある。これを自己受け為替手形という。
取引例:当社は得意先の売掛金165,000円を回収するために、その得意先を名宛人とする為替手形を振り出した。なお、得意先からは引受け済みである。
[解答]
(借方)売 掛 金 165,000 (貸方)売 掛 金 165,000
◎受取手形記入帳と支払手形記入帳
| 日付 | 摘要 | 手形 種類 |
手形 # |
振出人 (裏書人) |
振出日 | 満期日 | 支払 場所 |
金 額 | 顛 末 | |
| 年月日 | 年月日 | 日付 | 摘要 | |||||||
◎現金過不足
・帳簿上の現金残高と実際の有り高が異なるときに原因が判明するために一時的に処理する勘定が「現金過不足」勘定である。
・原因が分かった段階で適切に処理する。
・決算時までに原因が分からないときには「雑損」または「雑益」として処理する。
[取引例]
①帳簿上の現金残高が564,800円であるが、実際の有り高が524,000円であった。
②買掛金22,400円を現金で支払った取引の記帳漏れが発見された。
③決算時までに差額の原因が判明しなかった。
[解答]
①(借方)現金過不足 40,800 (貸方)現 金 40,800
②(借方)買 掛 金 22,400 (貸方)現金過不足 22,400
③(借方)雑 損 18,400 (貸方)現金過不足 18,400
〔第5回〕
◎有価証券
・株式や社債を有価証券と言う。
・一時的な資金運用のために市場性のある有価証券を取得したときには「売買目的有価証券」勘定で処 理する。
・有価証券を取得する際にかかる売買手数料などの諸費用は売買目的有価証券の金額に含める。
・有価証券を売却する際に、購入価額と売却金額の差額は「有価証券売却損」または「有価証券売却益」勘定で処理する。
・社債を売買する際に利息を受け払いするが、これを「有価証券利息」勘定で処理する。
[取引例]
①資金の一時的運用のために市場性のある神奈川工業(株)の株式1万株(額面50円)を1株当たり200円で購入し、小切手で支払った。
②上記株式2千株を1株当たり220円で売却し、代金は当座預金とした。
③配当金12,500円を現金で受け取った。
④横浜物産(株)の社債1,000,000円を100円につき95円で買い入れ、有価証券利息8,000円と ともに現金で支払った。
[解答]
①(借方)売買目的有価証券 2,000,000 (貸方)当座預金 2,000,000
②(借方)当座預金 440,000 (貸方)売買目的有価証券 400,000
有価証券売却益
40,000
③(借方)現 金 12,500 (貸方)受取配当金 12,500
④(借方)売買目的有価証券 950,000 (貸方)現 金 958,000
有価証券利息 8,500
◎固定資産
・長期間にわたって使用される資産は「固定資産」とよばれる。
・固定資産には、建物、備品、機械、車両運搬具、土地などがある。
・固定資産を取得するときに付随的に発生する諸費用(買入手数料や登記料など)は固定資産の価額に含める。
固定資産の購入価額(取得原価)=固定資産本体の価額+付随費用
・固定資産を売却したときには、その差額を「固定資産売却損」または「固定資産売却益」とする。
[取引例]
①建物5,000,000円を購入し、代金は小切手で支払った。なお、この売買に伴って、仲介業者への手数料150,000円と登記料80,000円は現金で支払った。
②所有している土地15,000,000円を22,200,000で売却し、売却代金は当座預金に振り込まれた。
[解答]
①(借方)建 物 5,230,000 (貸方)当座預金 5,000,000
現 金 230,000
②(借方)当座預金 22,200,000 (貸方)土 地 15,000,000
固定資産売却益 7,200,000
◎未払金、未収金
・商品売買以外の取引で生ずる代金の未払又は未収は「未払金」または「未収金」として処理する。
※買掛金、売掛金と区別する。
[取引例]①備品540,000円を購入し、代金は月末に支払うことにした。
②土地(取得価額 2,000,000円)を2,500,000円で売却し、代金の内1,000,000
円は現金で受け取り、残金は後日受け取ることになっている。
[解答]
①(借方)備 品 540,000 (貸方)未 払 金 540,000
②(借方)未 収 金 1,500,000 (貸方)土 地 2,000,000
現 金 1,000,000 固定資産売却益 500,000
〔第6回〕
その他の取引
◎仮払金と仮受金
・金額や取引内容が不明の時に一時的に処理しておく必要がある。これが「仮○金」勘定である。
・例えば、出張旅費がいくらかかるか分からないが、とりあえず概算額を支払っておいて、後に精算するような場合がある。この場合に支払われる概算額を「仮払金」(資産)勘定で処理しておく。
・出張先の社員から代金の払い込みがあったが、その内容が不明の時には一時的に「仮受金」(負債)勘定で処理しておく。
[例題]次の取引を仕訳しなさい。
①当社の販売員文教太郎の大阪出張にあたり、出張旅費の概算額120,000円を現金で支払った。
②文教太郎が帰社し、旅費の精算を行い、不足額15,000円を現金で支払った。
[解答]
①(借方)仮 払 金 120,000 (貸方)現 金 120,000
②(借方)旅費交通費 135,000 (貸方)仮 払 金 120,000
現 金 15,000
◎手形貸付金と手形借入金
・約束手形などを振り出して金銭の借り入れを行う場合には、「手形借入金」(負債)勘定で処理し、約束手形などを受け取って金銭を貸し付けた場合には「手形貸付金」(資産)勘定で処理する。
・なお、金銭の貸借のさいに借入期間または貸付期間に対する利息の授受が行われる。
・これらの手形は、商品の売買で行われる商業手形とは異なり、金融手形と呼ばれる。
[例題]次の取引を仕訳しなさい。
当社は横浜商事より2,000,000円を借り入れ、同額の約束手形を振り出し、利息を控除した手取額を当座預金とした。借入期間は6か月、借入利率は年3.5%である。
[解答](借方)当座預金 1,965,000 (貸方)手形借入金 2,000,000
支払利息 35,000
◎前払金と前受金
・商品の売買契約を行うときに、その代金の一部を手付金として受け払いすることがある。手付金を受け取ったときには「前受金」(負債)勘定で処理し、手付金を支払ったときには「前払金」(資産)勘定で処理する。
・実際に商品の引き渡しがあったときにこの勘定を相殺する。
[例題]次の取引を仕訳しなさい。
①当社は横浜商店から商品180,000円を仕入れる契約をし、手付金18,000円を現金で支払った。
②上記の商品を受け取り、手付金を除く代金は掛けとした。
[解答]
①(借方)前 払 金 18,000 (貸方)現 金 18,000
②(借方)仕 入 180,000 (貸方)前 払 金 18,000
買 掛 金 162,000
◎預り金
・従業員の所得税や健康保険料など、会社が従業員に代わって支払をするために、従業員から一時的に預かっておくことがある。これを「預り金」または「○○預り金」(負債)として処理しておき、税務署や保険会社に納付したときに相殺する。
[例題]次の取引を仕訳しなさい。
①当月の給料¥2,420,000を支払うに当たり、源泉所得税と保険料¥338,000を控除した金額を当座預 金から支払った。
②税務署へ従業員から源泉徴収していた所得税¥226,000を現金で支払った。
[解答]
①(借方)給 料 2,420,000 (貸方)預 り 金 338,000
当座預金 2,082,000
②(借方)預り金 226,000 (貸方)現 金 226,000
◎引出金
・個人企業で、店主が企業の財産を家計のためなど個人的な目的で使用することがある。これを店主による資本の引き出しという。
・この引き出しを処理する方法には次の2つの方法がある。
第1法 「引出金」勘定を用いる方法
第2法 「資本金」勘定に借記する方法
[例題]次の取引を仕訳しなさい。
店主が家計用の光熱費28,000円を現金で支払った。
[解答]
第1法 (借方)引出金 28,000 (貸方)現 金 28,000
第2法 (借方)資本金 28,000 (貸方)現 金 28,000