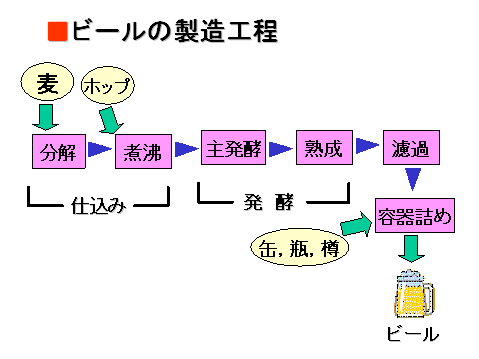ガソリン価格の原価構成を図で示すと次のようになります。
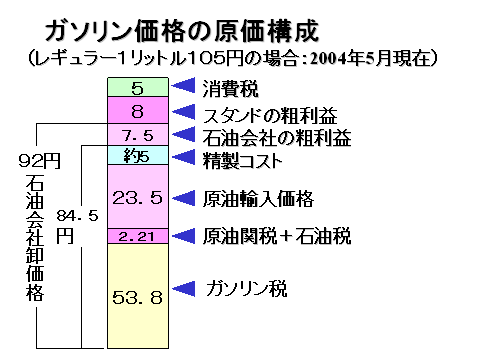
日本のガソリン価格は税金が大きな比重を占めていることが分かります。原油の精製コストってわずかしかないんですね。w( °0 °)w
小売価格から原油コストと税金を引いたマージンを石油会社とガソリンスタンドが分け合う。(「日本経済新聞」2004年5月29日付けを参考にしました)
?FAQ(よくある質問)?
Q1.原価計算対象となるサービスとはどのようなものですか。
Ans.サービス(service)は目に見えないので(無形なので)とらえにくいかもしれません。サービス業(クリーニング業、理髪業、コンサルタント、金融業など)は顧客にとって確かに価値あるアウトプットを作り出しています。例えば、クリーニング店では汚れた衣服をきれいにすることによって、理髪店では調髪したり、ひげを剃ったり、頭を洗うことによって有用なサービスを提供しています。サービス別にコストを配分することは、有形の製品よりも難しいことは確かです。しかし、サービス別に収益性(どのくらい儲かっているのか)を分析したり、サービスの価格を決定するのに原価計算は不可欠です。例えば、電気通信事業では、市内通話、市外通話、ファックス、VAN(付加価値通信網)などのサービス別に原価計算をしています。
Q2.工場で製品製造のために発生するものがすべて製品に配分されるのでしょうか。
Ans.いいえ、すべてが配分されるのではありません。製品に配分されるとは、製品のコストになるということです。異常な原因で発生したものや各企業の設定した正常値を超えたものについては、それが工場内で発生したものであっても、製品のコストにはなりません。例えば、火災などによる材料の損失額や異常な量の欠陥品に対して投じられた金額は製品のコストではありません。
Q3.原価の3要素として、材料費、労務費、経費があるということを学びましたが、この分類は固定的なものでしょうか。
Ans.いいえ、そうではありません。ほとんどの教科書はこの3要素に基づいて説明されていますし、1962年に出来た「原価計算基準」でもこの分類によっています。これはあくまでも一般的な分類です。これと異なる分類をしている業種もあります。
例えば、あるソフトウェア開発会社では、材料費、労務費、経費、外注費と4分類をしています。この業種では、ソフト開発の一部の作業を外部に委託(外注)しているところが多いからです。また、材料費はわずかしか発生せず、労務費(人件費)が大きなウエイトを占めています。
Q4.原価計算を行う場合と行わない場合とでは情報にどんな違いが出てきますか。
Ans.製品やサービスごとの原価が分かりません。それで、企業全体の業績しか分からないので、その中に隠されている無駄や不能率、製品(製品ライン)別やサービス別の業績状況(採算性、収益性)などマネジメントに欠かすことのできない情報を入手することができない。
Q5.原価計算を行わないでも財務諸表を作れるのでしょうか。
Ans.作れます。商的工業簿記がこれに当たります。ただし、原価計算を行って得られた数値よりもかなりラフなものとなります。例えば、製品や仕掛品の期末棚卸高は実地棚卸をせざるを得ず、その数値も見積や推測の域を出ません。つまり、かなり主観的にならざるを得ません。この数値ではマネジメントにもまったく使えません。
Q6.授業で、原価構成、売価構成を学びましたが、具体的な例を挙げて説明してください。
Ans.では、駅の中や駅前にあるコーヒー・ショップをとりあげてみましょう。1杯180円から250円くらいの価格で売っています。その販売価格の10%は粗利益(販売利益)になります。原価構成ですが、原料費は10〜20%、残りの70〜80%は人件費と家賃と地代などの店舗運営費です。スターバックスは「都内主要地域などの一等地に出店する」という戦略をとっているため、出店コストが高くなる傾向があります。それにつれて、販売価格も高くなります。高いコーヒーは原料も違うので、おいしいと思い違いをしている人も多いようです。各社ともブレンド比率にはちがいがあるものの、使用しているコーヒー豆の種類に大差はないのです。(「日本経済新聞」2002年11月28日付けを参考にしました)
もう1つガソリン代の例をあげてみましょう。ガソリンはもちろん原油からつくるというのは誰でも知っていますね。最近、原油価格が高騰しているので、車に乗っている人は大変ですね。
ガソリン価格の原価構成を図で示すと次のようになります。
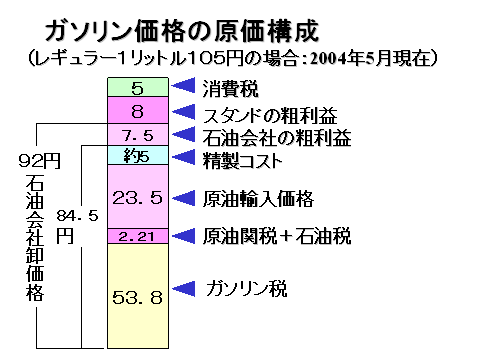
日本のガソリン価格は税金が大きな比重を占めていることが分かります。原油の精製コストってわずかしかないんですね。w(
°0 °)w
小売価格から原油コストと税金を引いたマージンを石油会社とガソリンスタンドが分け合う。(「日本経済新聞」2004年5月29日付けを参考にしました)
Q7.材料費の計算で、棚卸減耗費について学びました。棚卸減耗益というのはあるのでしょうか。
Ans.測定間違いや計算間違いがなければ、通常は減耗益は生じません。ただ、まれに生ずることがあります。例えば、原油などの原料は真夏の暑い気温によって膨張して増えることがあります。このような場合には、帳簿棚卸高を超える実地棚卸高が観察されます。
Q8.材料の棚卸減耗費の処理について教えてください。
Ans.材料棚卸減耗費は材料副費として材料の購入価額に含める場合と製造経費とする場合があります。材料の購入価額とした場合には、その材料を消費した指図書または製品の直接材料費となります。製造経費とした場合には、製造間接費に含められて指図書または製品に配賦されます。
Q9.材料費の分類で、素材(費)と原料(費)とは異なるという記述がありましたが、もう少し詳しく教えてください。
Ans.素材は、よく「素材を活かす」という言葉があるように、本来そのモノの持っている特徴を活かして製品にされます。一方、原料は製造過程において化学的な変化などをしてそのモノの最初のものとは全く別の形状になって製品化されます。
英語では、「○○は××から作られる」という表現で、この両者を区別しています。××のところが原料を表す場合にはmade
fromが、素材を表す場合にはmade ofが用いられます。「家は木材という素材で造られる」と言うが、「家は木材という原料で造られる」とは言いません。また、「石けんは原油という原料から作られる」と言うが、「石けんは原油の素材を活かして作られる」とは言いませんね。お分かりいただけたでしょうか。
Q10.原価計算を行うには、工場へ行って、どのように製品が作られるかを観察し、理解しなければならないと教科書に書いてありました。本当でしょうか。
Ans.本当です。会社で実際に原価計算を行っている人には現実的な問題です。でも、大学などで学習する過程では必ずしも不可欠というわけではありません。教科書で学ぶのは、あくまでも現実の世界を理解するために、業種や規模を問わず適用・応用できるようだいぶ抽象・単純化されていると言うことです。
すでに学んだように、原価計算は、ある目的のために材料の投入から製品の完成までのモノやサービスの流れをできるだけ忠実に貨幣価値的に追跡する作業なので、製造工程についてきちんと知っておくことが大切です。もちろん、製造工程は製品によって異なります。同じ製品であっても企業によって異なる場合もあります。なかには企業秘密というものもあるでしょう。
次に、皆さんに馴染みがある(?)ビールの製造工程を示しておきます。