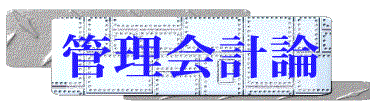
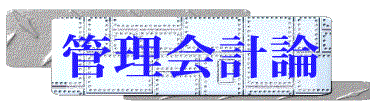
会計学は大別すると財務会計と管理会計がある。財務会計は外部に企業の経理状況を公表することに関心があるが、管理会計は企業の内部で会計データをどのように管理のために活用するかに関心がある。企業の利益を向上させるために、また原価を引き下げるために活用できる会計情報をどのようにして作成し、それをどのように用いるかを考える。そのための会計データの取り方、整理の仕方、集計の仕方はもちろん、会計スタッフはこれらの情報がどのような経営環境において用いられるのかを知らねばならないから、簿記、原価計算の知識だけではなく、基礎的な経営管理の知識も必要である。前半は管理会計の基礎的概念と技法などについて講義し、後半は管理会計技法に焦点を当てる。
■講義予定
1.管理会計と財務会計(1)
2.管理会計と財務会計(2)
3.管理会計の体系
4.利益管理会計(1)利益管理のプロセス
5.利益管理会計(2)損益分岐点分析
6.利益管理会計(3)プロダクトミックス
7.利益管理会計(4)利益目標の設定
8.原価管理会計(1)原価管理のプロセス
9.原価管理会計(2)管理可能費など
10.原価管理会計(3)原価分解方法
11.業績管理会計(1)責任会計
12. 業績管理会計(2)原価センターの業績評価
13. 業績管理会計(3)投資センターの業績評価
14.企業予算(1)予算の意義
15.企業予算(2)予算編成の方法
16.予算編成の事例(1)売上高予算など
17.予算編成の事例(2)製造予算など
18.標準原価管理(1)標準原価について
19.標準原価管理(2)原価標準の設定
20.標準原価管理(3)差異分析①
21.標準原価管理(4)差異分析②
22.標準原価管理(5)原価企画
23.意思決定会計(1)意思決定のための原価概念
24.意思決定会計(2)ケース分析
25.設備投資意思決定会計(1)キャッシュフロー
26.設備投資意思決定会計(2)経済性計算
■講義の内容・要点
1.管理会計と財務会計(1)
・
会計は、会計情報の利用者(ユーザー)によって財務会計と管理会計に分かれる。
・管理会計は、企業の経営管理者に提供される会計情報を取り扱う。
・財務会計と管理会計ではどこが異なるのかを2回に分けて解説する。
2.管理会計と財務会計(2)
・財務会計との相対的な違いを通して、管理会計の特徴を見ていく。
3.管理会計の体系
・管理会計の体系化は、管理会計のフレームワークを決定する問題である。どのように管理会計を体系立てて説明するのがふさわしいかを考える。
・本講義では、業績管理会計と意思決定会計に分類するアプローチをとる。なぜこれがふさわしいかを説明する。
4.利益管理会計(1)利益管理のプロセス
・大綱的利益計画と予算管理との関係を理解する。
・大綱的利益計画を中心に解説する。大綱的利益計画を立てる際に用いられる管理会計手法を簡単に取り上げる。
5.利益管理会計(2)損益分岐点分析
・大綱的利益計画のための管理会計手法として、損益分岐点分析を具体的に展開していく。
・損益分岐点売上高の計算式
損益分岐点=固定費/(売上高-変動費/売上高)
・目標利益を達成するための各種方策を取り上げる。
・安全余裕率と損益分岐点比率
・損益分岐点分析はきわめて概略的で使いやすいが、その限界も認識することが大切である。
6.利益管理会計(3)プロダクト・ミックス
・直接原価計算とは
・限界利益と限界利益率は直接原価計算を理解するキーである。
・直接原価計算の手法を用いたプロダクト・ミックス(ここではセールズ・ミックス)問題を取り上げる。ここでは、計画売上高を変えないでもどのように利益を増やすことができるかを知ることができる。
7.利益管理会計(4)利益目標の設定
・各種の経営指標を取り上げる。その中には、ROE(株主資本利益率)やEVA(経済的付加価値)を含む。
・ROIの欠点
8.原価管理会計(1)原価管理のプロセス
・原価管理とは
・原価管理のプロセス
・標準原価と予算
・固定予算と変動予算
9.原価管理会計(2)管理可能費など
・管理可能費と管理不能費
・アクティビティ・コストとキャパシティ・コスト
10.原価管理会計(3)原価分解方法
・原価分解とは原価を固定費と変動費に分解することである。原価関数のパラメータの算定でもある。
・損益分岐点分析、直接原価計算、変動予算を採用するための基礎的データとなる。
・分解方法
①会計的分解法
②数学的・統計的分解法
③工学的分解法
・ABC(活動基準原価計算)とABM(活動基準管理)
ABMはどのように原価引き下げに貢献するのかがここでの論点である。
11.業績管理会計(1)責任会計
・責任センター……会計上の業績評価のための組織小単位。
①原価センター
②収益センター
③利益センター
④投資センター
・責任会計(responsibility accounting)
12.業績管理会計(2)原価センターと利益センターの業績評価
・管理者の業績と組織の業績の区別。
・管理可能利益と貢献利益
・京セラのアメーバー経営(ミニ・プロフィット・センターの一例)
13.業績管理会計(3)投資センターの業績評価
・ROIとRI(残余利益)
・カンパニー制(投資センターに関連して)
・バランスド・スコアカード
14.企業予算(1)予算の意義
・企業予算の意義
・調整機能の重要性
・予算と短期利益計画との関係
15.企業予算(2)予算編成の方法
・わが国における予算編成の手順
・予算の体系
・ゼロベース予算
・参加型予算編成
16.予算編成の事例(1)売上高予算など
・売上高予算……販売予測と販売分析
・製造高予算と在庫予算
17.予算編成の事例(2)製造原価予算など
・直接材料費予算
・材料購買予算
・直接労務費予算
・製造間接費予算
・販売費予算
・一般管理費予算
・総合予算
18.標準原価管理(1)標準原価について
・標準原価管理と原価企画
・標準原価管理のプロセス
・標準原価管理と科学的管理法
19.標準原価管理(2)原価標準の設定
・標準原価カード
・原価標準の設定方法
20.標準原価管理(3)差異分析①
・直接材料費差異の分析……価格差異と数量差異
・直接労務費差異の分析……時間差異と賃率差異
21.標準原価管理(4)差異分析②
・製造間接費の差異分析……能率差異、予算差異、操業度差異
22.標準原価管理(5)原価企画
・差異の原因・調査
・3シグマ法
・原価企画
23.意思決定会計(1)意思決定のための原価概念
・意思決定会計の特徴
・業務意思決定の特徴
・会計情報を用いた意思決定のメカニズム
・意思決定のための原価概念
①差額・増分原価
②埋没原価
③機会原価
24.意思決定会計(2)ケース分析
・部品の自製・購入問題
・特別注文問題
・売却か追加加工問題
・製品の撤退問題
・リニア・プログラミング(LP)問題
25.設備投資意思決定会計(1)キャッシュフロー
・設備投資意思決定の特徴
・キャッシュフロー
・貨幣の時間価値
26.設備投資意思決定会計(2)経済性計算
・設備投資の経済性計算の手法
①回収期間法
②正味現在価値法(NPV法)
③内部利益率法(IRR)など
■講義の進め方
OHPを用いて講義を進めていく。
■評価方法
2回のペーパーテスト(60分~70程度。持ち込み可)に、出席点とレポート点(2回程度)を加味して評価する。出席が2/3未満の場合には、試験を受けることができないので注意すること。
■テキスト
志村正著『管理会計テキスト(理論と計算)』神奈川大学生協にて製本,
2000年。
■参考書
・櫻井通晴著『管理会計[第二版]』同文舘,2000年。
・加登豊著『管理会計入門』日本経済新聞社(日経文庫),1999年。
■受講生へのメッセージ
本講義の受講を希望するものは、2年次の「原価計算」を修得していて、さらに企業の経営管理にも興味があるものが望ましい。