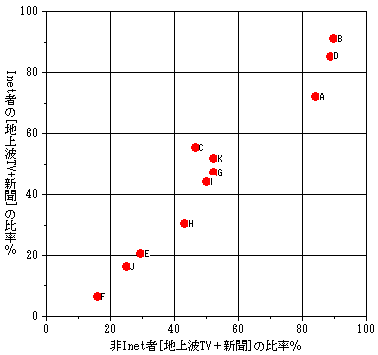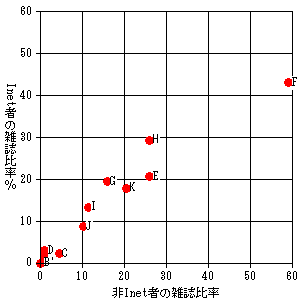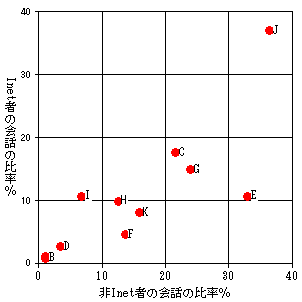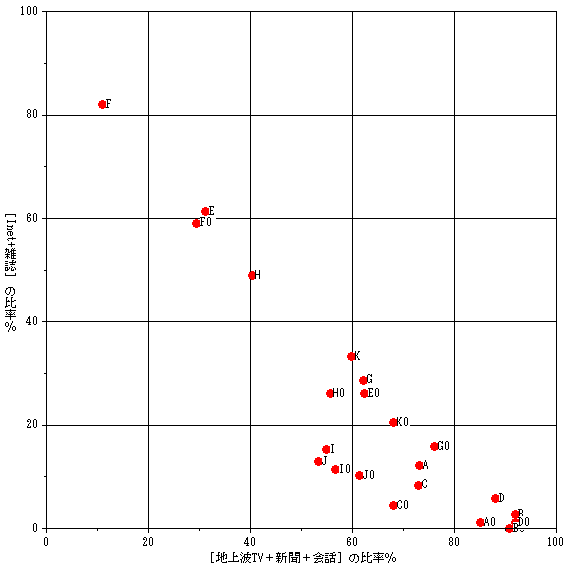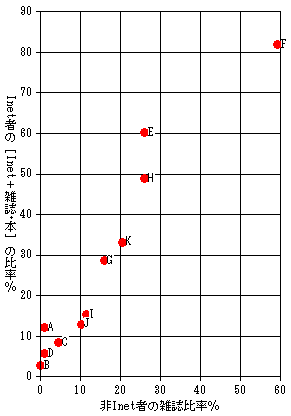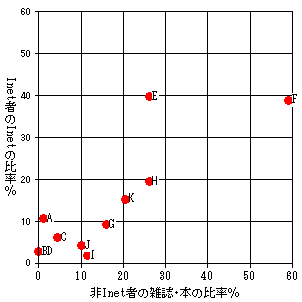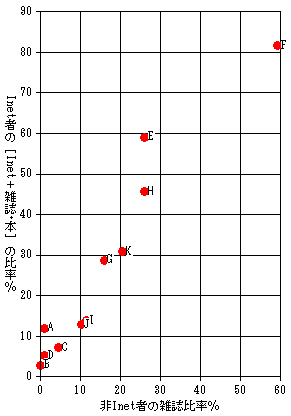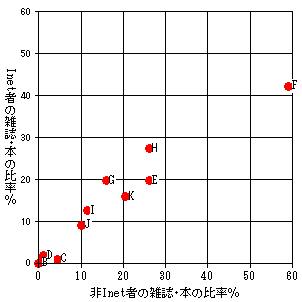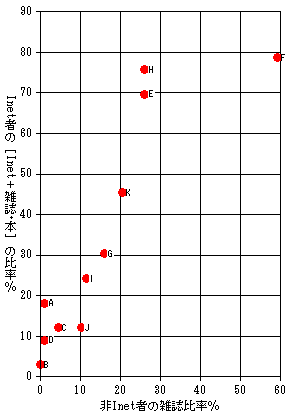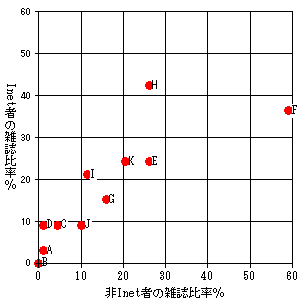地上波テレビ放送と新聞は、生活で最も身近に利用されることを反映して、ここでも様々な情報ニーズに対応して選ばれる比率が高い。この2つは類似している面も相違している面もあるが、整理上はマスメディアとして、双方の合計値で見ることにする。地上波テレビ放送と新聞の選択比率の和を、非インターネット利用者を横軸、インターネット利用者を縦軸にして図3に描く。この図から次のことが分かる。
-
各情報ニーズ毎の2つのメディア(マスメディア)の選択のされ方は、ほぼ勾配1の直線の近くに分布している。
-
A、B、Dは和の比率が非常に高く、勾配1の直線上、ないしはその近くに分布している。
-
C,E〜Kは、この2つのメディアへの依存が相対的に小さく、さらに勾配1の直線より下側に分布している。約5〜10%程度低い。
これらの情報ニーズでは、インターネット利用者のマスメディア依存が低い下している可能性を見ることが出来る。
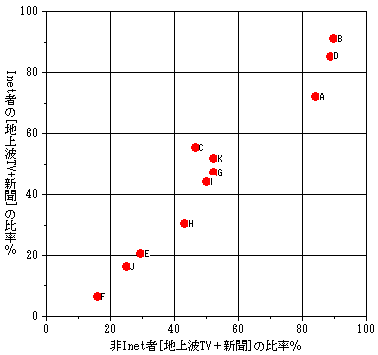
A.海外の出来事 B.日本の出来事 C.地域の出来事
D.政治・社会問題 E.仕事の情報 F.趣味の情報
G.話題を豊富に H.知らない世界 I.興奮や感動
J.癒しと気晴し K.生活情報
サンプル数
インターネット利用者 N=262
非インターネット利用者 N=88
図3.インターネットの非利用者と利用者の[地上波TV+新聞]比率
ここでは表3に示したメディア選択の実態を、問題整理に有用な1枚のグラフに表すことを試みる。
これまでは様々な情報ニーズに対して比較的共通的に選ばれる可能性の高い4つの従来メディアについて、その傾向を見てきた。インターネット環境に伴う変化という点では、マスメディア[地上波テレビ+新聞]、家族・友人との会話の2つは、依存性を減らす傾向にあり、雑誌・本にはあまり変化はないという傾向である。
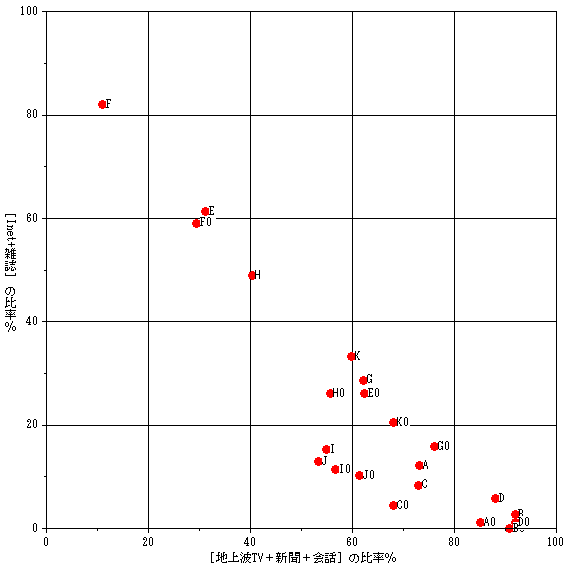
(注1)
A.海外の出来事 B.日本の出来事 C.地域の出来事
D.政治・社会問題
E.仕事の情報 F.趣味の情報 G.話題を豊富に
H.知らない世界
I.興奮や感動 J.癒しと気晴し K.生活情報
(注2)
A0,B0,・・・・:非インターネット利用者 N=88
A,B,・・・・・・:インターネット利用者 N=262
図6 「地上波TV+新聞+会話」比率と「インターネット+雑誌」比率
次にインターネットであるが、11個の情報ニーズに対応したインターネットの選択比率と他のメディアの選択比率の相関を見ると、雑誌・本との相関が強く、相関係数は約0.75である。そこで[地上波TV+新聞+会話]を横軸に、[Inet+雑誌・本]を縦軸にして、インターネットの利用者と非利用者の情報ニーズの散布図を描いた。それが図6である。
同図ではインターネット利用者の情報ニーズの位置はA、B、Cなど、非利用者の位置はA0、B0、C0
などで示している。この図では、図中の位置と非利用−利用における相対的な位置関係が、メディア選択の総括的な傾向を示している。
例えば「E.仕事の情報」に注目すると、非インターネット利用者のメディア選択の位置はE0(62.5,26.1)であるが、インターネット環境ではE(31.3,60.3)に移行する。つまり横軸が31%減少し、縦軸が34%増加している。マスメディアと会話依存が減少し、インターネットと雑誌・本への依存が増加していることを示している。それでは34%−31%=3%の増加分がどこから来たのかというと、それは表3における主要5メディア以外の6個のメディアと「その他」および「無回答」の合計の差から生じている。
この点についてさらに補足を加える。12個の選択肢のメディアと「無回答」を含めた13個の回答比率の合計は100%になる。もし地上波テレビ、新聞、雑誌・本、インターネット、家族・友人との会話という主要5メディアの選択比率の合計が100%なら、各情報ニーズは左上がり・右下がりでX軸またはY軸との交点が100%を通る対角線(便宜上で直線Sと呼ぶ)上に乗る。合計が100%にならない場合には、その分だけ図中ではSから離れた位置に置かれる。この点から次の傾向を理解することが出来る。
-
インターネットの利用と非利用の相対的な位置関係の勾配が−1の直線Sに近く、かつ平行な場合、双方のメディア環境下でのメディア選択の差は、主要5メディア内で起きている。
-
情報ニーズの位置が対角線から離れれば離れるほど、主要5メディア以外のメディアの寄与が大きくなる。
この様な図の特徴を前提として図6の主な傾向を見ると、次の点を読みとることが出来る。
-
A〜D、A0〜D0の情報ニーズは、いわば環境監視ニーズと呼ぶことが出来るものであるが、これらは概して右下に分布しており、マスメディア+会話への依存が高い。またインターネット利用と非利用での相対的な位置変化は小さい。概してインターネットの影響を受けにくい情報ニーズである。
-
E〜K、E0〜K0の情報ニーズは、いわば個人関心ニーズと呼ぶことが出来るものである。これらは環境監視ニーズの左側に下から上まで広く分布している。注目すべき点は、インターネットの利用と非利用の相対的な位置の差が非常に大きく、ほぼ勾配が−1で左上に向かって変化していることである。すなわちこれらの情報ニーズでは、インターネット環境下では主要5メディア内でのメディア選択が変化し、主にはマスメディアの役割が低下し、インターネットの役割が高まることを示している。
特に例を上げれば、「E.仕事の情報」、「F.趣味の情報」、「H.知らない世界」などでは非常に大きい変化が起きて、インターネットの比率が高まっている可能性が高いことが分かる。
-
しかし個人関心ニーズでも、「I.興奮や感動」、「J.癒しと気晴らし」は他の情報ニーズとは大分異なる。インターネット+雑誌・本にはあまり依存することはなく、マスメディア+会話とビデオ・オーディオが選ばれている。このために直線Sから離れている。
前節では、個人関心ニーズの場合には、インターネット環境下では[地上波TV+新聞+会話]の選択比率が減り、[インターネット+雑誌・本]を増やす形でインターネットへの移行が起こることを述べてきた。それではインターネットと雑誌・本の関係はどの様になるのだろうか。それを図7aに示す。横軸は非インターネット利用者の雑誌・本の比率、縦軸はインターネット利用者の[インターネット+雑誌・本]の比率である。
この図によると[インターネット+雑誌・本]の比率は、非インターネット利用者の雑誌・本の比率とほぼ比例し、勾配が1.8〜2.0倍程度の直線の近くに分布している。ここではこの値を便宜的に1.9としておく。他方では以前の図3によると、インターネット利用者と非利用者の雑誌・本の選択比率はほぼ同じで、勾配が1.0の直線の近くに分布している。したがってこの2つの図より、インターネット分は非インターネット利用者の雑誌・本の選択比率の0.9倍の分だけ生じていることが分かる。
インターネットの比率が非インターネット利用者の雑誌・本の比率に比例して生じることは、非常に興味ある事実である。これはインターネットの利用が、雑誌・本と同じ情報ニーズに対応して発生することを示しているためである。インターネットは選択性の強いメディアであるが、雑誌・本も既存メディアの中では選択性の強いメディアである。その様な選択性という共通する特性がこの背景と考えられる。
また特にインターネットの比率が高い情報ニーズは、「E.仕事の情報」、「F.趣味の情報」である。これらは日常的に多く現れる情報ニーズであり、そこで多く利用されることがインターネットの便利感の背景をなしていると考えられる。
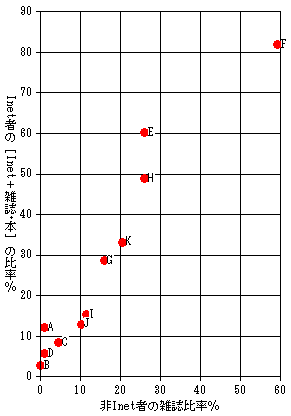
a.インターネット+雑誌・本
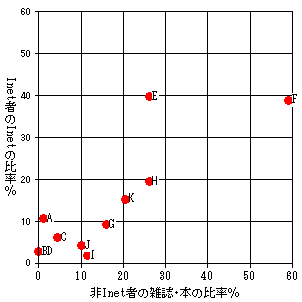
b.雑誌・本
図7 インターネットの比率の傾向:全サンプルN=264
ところでもう一つ興味ある論点がある。インターネットと雑誌・本の代替性である。インターネットと雑誌・本が同じ情報ニーズに対応するということは、双方の競合があり得ることである。それでは競合はどの様に生じているのであろうか。
調査では別の質問でインターネット利用者に対して、「インターネットを利用するようになってから、雑誌・本を読む時間が変化したか否か」を聞いている。回答がある254人のうちで、「増えた」のが13人 5.1%、「不変」が208人81.9%、「減った」が33人13.0%である。時間の増減を聞いているのと、「時間の変化でメディア選択の変化を規定することが出来る」とは完全には言い難いが、大筋としては時間が「増えた」人は選択も増え、時間が「減った」人は選択も減ったと考えるのが自然である。この質問への回答は、「不変」が8割強で断然多く、このグループが全体の傾向を決めている。そこでこの「不変グループ」208人についての[インターネット+雑誌・本]と雑誌・本の傾向のグラフを図8a、bに示す。
このグラフによると、図8aでは[インターネット+雑誌]の比率は、図7の場合とほとんど同じで勾配1.9の直線の近くに分布している。また図8bの非インターネット利用者のグラフでも図3とほぼ同じの勾配1.0の直線近くに分布している。回答者の大勢となっている「不変グループ」の結果と全サンプルの結果が同じと言うことであるから、大筋としては、インターネットと雑誌・本の競合は生じていないと見られる。
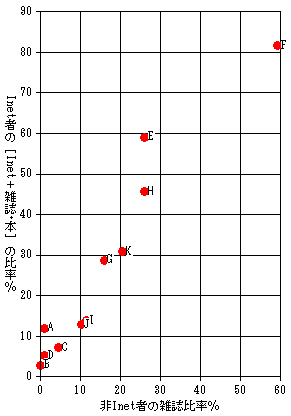
a.[インターネット+雑誌・本]
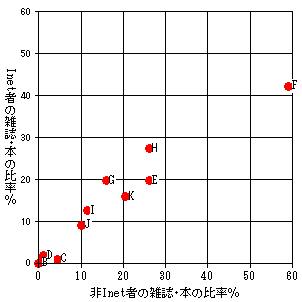
b. 雑誌・本
図8 インターネット非利用者と利用者の[インターネット+雑誌]比率:不変者(N=208)の場合
それでは33人の「減少グループ」の場合にはどうなるかを見る。図9aとbがその結果である。図9aを見ると、この場合には各情報ニーズは勾配が2.2程度の直線の近くに分布している。また図9bでは、勾配が1.2程度の直線に近くに分布している。この場合にインターネットの比率は非インターネット利用者の雑誌・本の比率の1.2倍程度であり、不変グループよりも依存性が高い。次に[インターネット+雑誌・本]の比率は同じく2.2倍程度であるということは、インターネット利用者の雑誌・本の比率は、非インターネット利用者のそれと同程度であることを意味している。
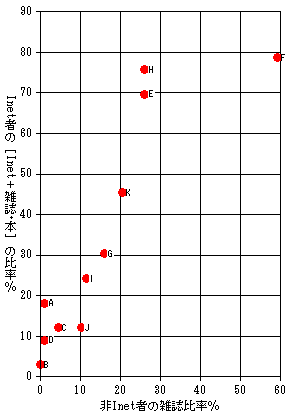
a.[インターネット+雑誌・本]
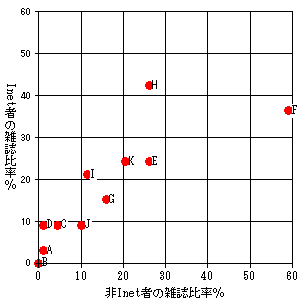
b. 雑誌・本
図9 インターネット非利用者と利用者の[インターネット+雑誌]比率:減少者(N=33)の場合
したがってこの場合には、元々は非インターネット利用者の雑誌・本より依存度が高かった人がインターネットに移行し、インターネット依存をより高め、また雑誌・本の依存も減らして、結果としては非インターネット利用者と同じ水準の雑誌・本の依存度になっているものと理解される。