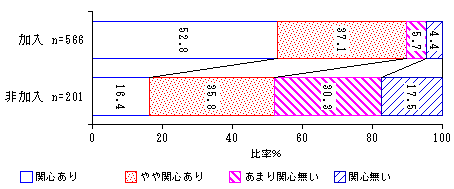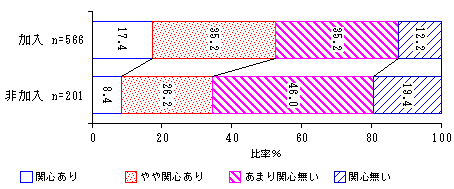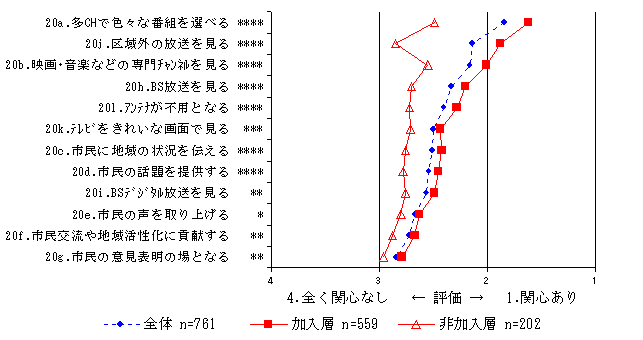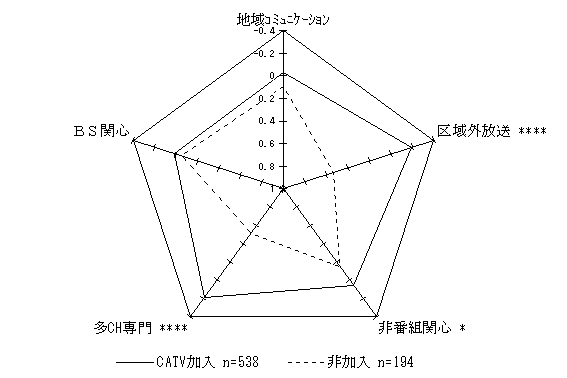目次へ戻る
5.3 CATVにおける地域コミュニケーションの加入効果
CATVは地域のコミュニケーションを活発化し、もって生活の豊かさを実現する手段として注目され、政策的な努力も相俟って、かなり広範に普及して来ている。その発展段階を時期的に見れば、1980年代央までは概して地上波数の少ない地方の市町村を中心に立地が進んで来たが、1980年代後半になると多チャンネルニーズとテレトピア計画等の支援下で、大都市部にも急速に立地が進展した。しかしながら多チャンネル・ニーズの充足を目指して大都市部に立地したCATV局では、経営環境の厳しさも相俟って、地域活性化に向けた地域番組制作の位置づけが様々で、それを反映して放送される番組の充実度合にも様々な水準がある。
地域番組への注力が様々な水準にある理由としては、CATV局の資金調達力が様々な水準であることもあるが、地域番組への注力が経営的にメリットをもたらすか否かが不明であることもその理由となっている。そのために営業努力や他の努力が優先され、地域番組努力が後回しになることも十分にあり得ることである。
そこで地域番組への努力がどの様な経営効果をもたらすかを研究することとした。具体的には、視聴者の加入満足における地域番組の寄与度合を計測し、それが加入者による口コミの推薦行動にどの様に影響していくかを見ようとした。そのために地域番組制作では日本でも有数の努力をしている鳥取県米子市の中海テレビ放送エリアを事例研究の調査対象地域として取り上げ、地域住民への調査を行っている。
「地域番組への経営効果」には、「視聴者満足→加入推薦」以外にも「住民出演→加入促進」、「地域活性化貢献→親密度形成→加入促進」などの様々な筋道が考えられるが、今回は視聴者満足の構造把握を試み、それと推薦行動の関係を見ることとした。なお他地域との比較も断片的だが試みている。研究内容も方法論においても初めての試みであり、方法論としての検証も課題の1つである。
5.3.1 CATVへの関心
(1)様々な項目への関心度
調査では、加入の動機に相当する色々な項目について、加入者には加入時点での関心の程度を、非加入者には調査への回答時点での関心の程度を聞いている。例えば「a.多くのチャンネルでいろいろな番組を選べる」、「c.地域の放送局として市民に地域の状況を伝える」などの点について、「1.関心がある」〜「4.全く関心がない」までの4段階で回答を得ている。その結果、例示した設問については、加入者と非加入者から次のような回答を得ている。
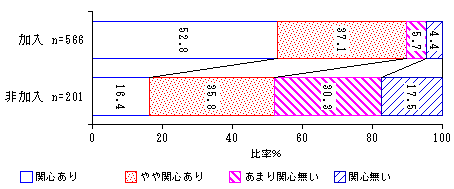
選択肢平均値 加入:1.62 非加入:2.49
a.多くのチャンネルで色々な番組を選べる χ2乗 ****
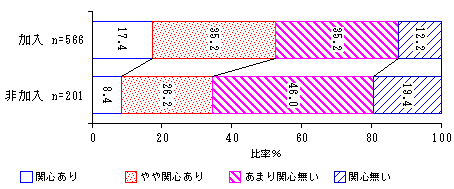
選択肢平均値 加入:2.42 非加入:2.76
c.地域の放送局として市民に地域の状況を伝える χ2乗
****
図5.3.1.1 CATVへの関心の事例
同図によると「a.多くのチャンネルでいろいろな番組を選べる」という点については、加入者は「2.やや関心がある」を含めると8割が関心があるが、非加入者は約半分となり、非加入者の関心の程度が低いことが分かる。また「c.地域の放送局として市民に地域の状況を伝える」では、加入者、非加入者ともに関心の度合は低下しているが、加入者の方が関心の度合は強いことが分かる。
次にこの関心の程度を選択肢の平均値で表すと、図5.3.1.1に示している通り、a.では(加入者、非加入者)は、(1.62、2.49)、b.では(2.42、2.76)で、平均値の点でも大きい差となって現れている。
そこで関心に関する全質問の回答結果を平均値で図示したものが、図5.3.1.2である。
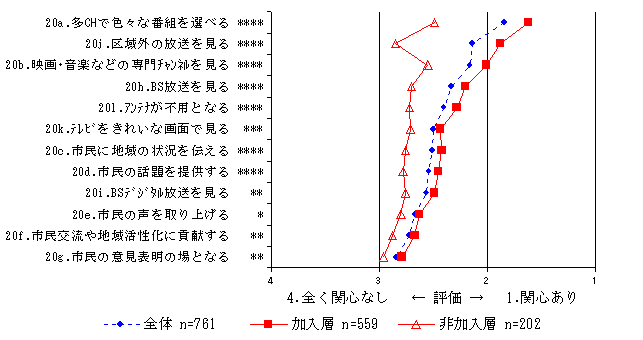
図5.3.1.2 CATVへの関心の傾向
平均値の検定:*:0.01<p=<0.05,**:0.001<p=<0.01,****:p<0.0001
同図は全体での関心度の高い項目順に上から下へ配列されているが、おおよその傾向は次のようになっている。
-
加入者の関心度は項目によってかなり異なるが、非加入者はどの項目でも大きくは変わらない。
-
加入者は、多チャンネル性や専門番組、区域外再送信、BS、アンテナ不用などに関心が高い。地域情報に関する項目、いわば地域コミュニケーションへの関心は高くない。
-
関心度が高い項目では加入者と非加入者の差は大きいが、関心度の低い項目では差は減少する。
(2)因子分析による関心の構造
調査段階での12項目についての関心の度合を前項で述べたが、着目すべき項目を減らし、関心度の骨格で議論を整理するために、これらの12項目の回答に対して因子分析を行った。その結果を表5.3.1.1に示す。同表では5個の因子を抽出し、これらの因子で元々の分散の87%をカバーしている。5つの因子はそれぞれ、地域の番組や情報交換に関係する地域コミュニケーション関心、BS番組の視聴に関するBS関心、多チャンネルで様々な専門番組を見ることに関する多チャンネル専門関心、アンテナが不用であることやきれいな映像にかんする非番組関心、米子の地上波アンテナでは見ることが出来ない区域外放送に関する区域外放送関心である。
表5.3.1.1 CATVへの関心の因子と対応する変数
| 因子(平方和、寄与率) |
対応する変数(係数の大きい順↓ → ↓) |
第1因子 (4.22, 35.1%)
地域コミュニケーション関心 |
20e.市民の声を取り上げる 20c.地域の状況を伝える
20f.市民交流や地域活性化貢献 20g.市民の意見表明の場となる
20d.市民の話題を提供する
◎市民の声を取り上げ、市民交流のや地域活性化に貢献し、市民に話題を提供する
などの地域コミュニケーションの関心 |
第2因子 (1.85, 15.4%)
BS関心 |
20i.BSデジタル放送を見る
20h.BS放送を見る
◎ケーブルテレビによるBS再送信への関心 |
第3因子 (1.74, 14.5%)
多CH専門関心 |
20a.多くのCHで色々な番組を選べる
20b.映画・音楽・ニュースなどの専門チャンネルを見る
◎多くの中から番組を選択し、また専門チャンネルを見ること |
第4因子 (1.64, 13.7%)
非番組関心 |
20l.アンテナが不用になる
20k.テレビをきれいな画面で見る
◎番組効果以外の点への関心 |
第5因子 (1.00, 8.3%)
区域外放送関心 |
20j.サンテレビ、瀬戸内海放送などの区域外の放送を見る
◎区域外放送を見ることの関心 |
(注)平方和と寄与率はバリマックス回転後の値である。寄与率の合計は87.1%である。
この因子分析結果の5因子の因子スコアの加入者と非加入者の平均値を用いて、加入者と非加入者の平均像を描いてみたのが、図5.3.1.3である。因子スコアは標準化データであり、元々のデータの選択肢が、「1.関心がある」〜「4.全く関心がない」であるため、負で絶対値が大きい外側ほどに、各因子の傾向が強いこと示している。この点を考えると、加入グループと非加入グループの差は非常に明確であることが分かる。主な傾向は次のようになっている。
-
加入と非加入は、地域コミュニケーション関心、BS関心では、注目すべき差はない。
-
多CH専門、区域外放送では非常に顕著な差が出ている。
-
非番組関心も有意な差がある。
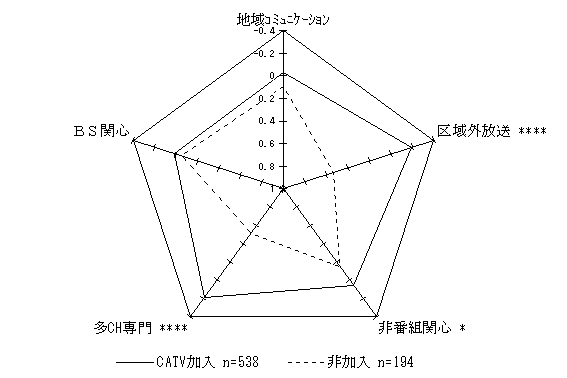
図5.3.1.3 加入−非加入別のCATV関心度の因子スコア平均値
平均値の検定:*:0.01<p=<0.05,****:p<0.0001
これらの結果から見れば、加入の有力な要因は多チャンネルの専門番組への関心と区域外放送への関心で、次いで非番組関心も寄与があるが、地域コミュニケーション関心やBS関心にはあまり寄与がない、ということになる。非加入者が加入を決めるまでには、CATVへの関心以外にも様々な要因があるとしても、CATVへの関心は最も有力な要因である。この有力な要因でこのような差があることは注目される。
しかしこれらのデータは、加入者では加入前の関心であり、非加入者では現在の関心であるために、加入者の現在の評価とは異なる。この点では、加入者が加入後にどの様に評価しているのかが重要な着目点である。
次へ進む
目次へ戻る