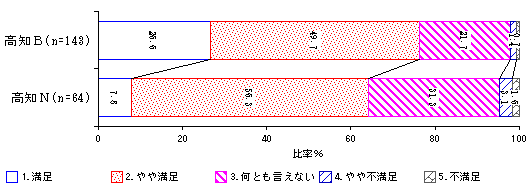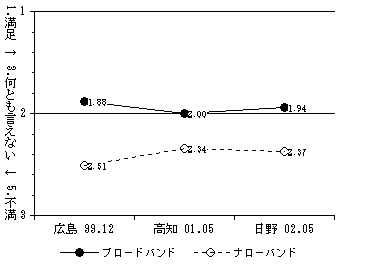これまで見てきたように、インターネットは利用者がかなりの時間を使うものとして、生活に定着しつつあるものと見ることが出来る。この様な傾向を見ると、インターネットは多くの人に様々な満足を与えつつ普及しているものと想定される。それではインターネットを利用する利用者の満足度はどの様なものであろうか。その調査結果の一例を図11に示す。利用者の満足度を、「1.満足」、「2.やや満足」、「3.何とも言えない」、「4.やや不満」、「5.不満」の5段階の順序尺度で聞いている。その回答を、ブロードバンド・グループとナローバンド・グループで分けて集計している。
同図によると、インターネット利用における満足度はかなり高い。ブロードバンド・グループでは、「1.満足」、「2.やや満足」を合わせた合計は76%にも達し、「3.何とも言えない」と回答する中間層は22%で、不満層はわずかに2%である。利用時間の長さを反映して、満足度も高いと理解することが出来る。これに対してナローバンド・グループでは「1.満足」層が20%近く低下するものの「2.やや満足」層が7%増加し、両者の合計は約64%と低下する。さらに「3.何も言えない」中間層が約10%増加して、不満層は約5%となる。この傾向を見ると、ナローバンド・グループでは受益度合が低下し、満足度が低下していることが分かる。
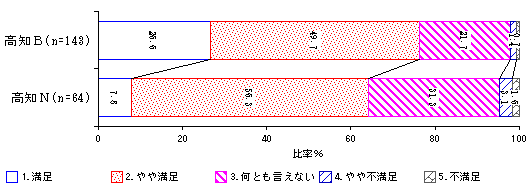
図11 インターネットの利用満足度(高知市調査)(χ2乗p=0.03)
これは一地域の傾向だが、他の調査地点を含む全体ではどうであったかという結果を図12に示す。この図はブロードバンド・グループとナローバンド・グループ毎に、順序尺度である選択肢の平均値を求めたものである。この図を見ると次の点が分かる。
-
ブロードバンド・グループの満足度は全般に高く、平均でも「2.やや満足」の近くにある。
-
これに対して、ナローバンド・グループの場合には一段と下がった評価である。
図10に示した高知市の場合よりも、広島市や日野市の場合には、ブロードバンド・グループの満足度は高く、かつナローバンドとの差は大きくなっている。したがってこれらの地点では、ブロードバンドは高知市の場合よりも好意的に受け入れられていることが分かる。複数調査地点におけるこの様な傾向を見ると、ブロードバンド化はかなり強く受け入れられる可能性が高いことが理解される。
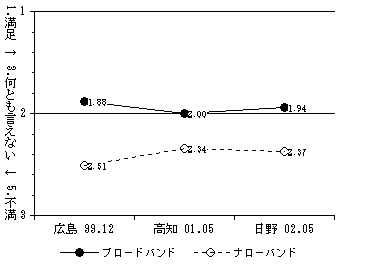
図12 インターネットの満足状況
本調査における標本抽出は、概してCATVの加入層と非加入層に層別化した二段階抽出を行っている。このために本報告では、次の2つの集計方法を採用している。
1.有効回収したデータをそのままに集計分析する方法
CATVへの加入−非加入が結果に影響するとは考えにくい層化におけるクロス集計などでは、この方法を採用した。この場合には、層別間での統計的検定を行っている。
2.有効回収データをウエイト加重(ウエイトバック)して集計分析する方法
単純集計で地域間の比較が行う場合など、適切に地域間比較が行われるようにするために、層別の回収数が母集団規模となるようなウエイト加重を行っている。その場合のウエイトを、別表に示している。ウエイト加重を行うと仮想的に標本規模が大きくなるために、統計的有意性の検定は利用困難となる。
別表 各地域の有効回収数、母集団規模とウエイト
| 地域区 分(抽出単位) |
標本区分(注1) |
有効回収数 |
母集団 |
ウエイト |
| 広島市(世帯) |
HICAT地区 |
CATV |
104
|
15,076
|
144.961
|
| 非CATV |
106
|
117,370
|
1107.264
|
| チャンネルU地区 |
CATVInet |
147
|
850
|
5.782
|
| CATV |
39
|
6000
|
153.846
|
| 非CATV |
45
|
40180
|
892.888
|
| 札幌市(人口) |
中央区 |
男 |
51
|
61087
|
1197.784
|
| 女 |
55
|
72323
|
1314.964
|
| 西区 |
男 |
49
|
42303
|
863.327
|
| 女 |
55
|
47085
|
856.091
|
| 豊平区 |
男 |
45
|
61103
|
1357.844
|
| 女 |
61
|
67009
|
1098.508
|
| 南区 |
男 |
52
|
34807
|
669.365
|
| 女 |
54
|
37983
|
703.389
|
| 諏訪地域(世帯) |
茅野市 |
CATVInet |
28
|
1,747
|
62.393
|
| CATV |
95
|
20,853
|
219.505
|
| 諏訪市 |
CATVInet |
55
|
1,980
|
36.000
|
| CATV |
114
|
18,352
|
160.982
|
| 岡谷市 |
CATVInet |
39
|
2,069
|
53.051
|
| CATV |
91
|
17,350
|
190.659
|
| 下諏訪町 |
CATVInet |
16
|
775
|
48.438
|
| CATV |
42
|
7,891
|
187.881
|
| 高知市(世帯) |
(注1) |
CATVInet |
177
|
499
|
3.0613
|
| CATV |
163
|
5,039
|
28.4689
|
| 非CATV |
123
|
23,299
|
187.4228
|
| 日野市(世帯) |
(注2) |
CATV |
132
|
3641
|
27.5833
|
| 再送信 |
89
|
3828
|
42.9550
|
| 非CATV |
281
|
7118
|
25.3309
|
(注1)CATV:多チャンネルCATV加入 CATVInet:ケーブルインターネット加入 非CATV:多チャンネル
CATV非加入
(注2)まず25町丁を抽出し、その後に等確率で標本抽出したため、地域は1つとしてウエイト付けをした。
(注3)まず13町丁を抽出し、その後に当確率で標本抽出したため、地域は1つとしてウエイト付けをした。