ウェブの効用タイプがインターネット利用行動を特徴付けていることを見てきたが,もう少しメディア利用から離れた,個人的性格ないしはパーソナリティなどの個人的傾向がどの様にメディア利用を規定しうるかは,興味ある問題である.この様な要因として先行的には情報欲求が検討されている(川浦1998).先行研究の場合にはテレビ,新聞,雑誌,CDなどの多様なメディアと情報欲求の関係が横断的に検討されている.今回の調査では先行研究にある情報欲求の項目の幾つかを変更し,ウェブ効用タイプとの関係を調べた.
情報欲求に関する設問は,例えば「A.世の中の出来事や流行は人よりも早く知りたい方である」に対して回答者が該当する度合を,「1.よくあてはまる」〜「4.まったくあてはまらない」の選択肢で聞いている.この設問に対する回答をウェブ効用タイプのグループ別に平均値で集計した結果を図8に示す.
同図は全体の平均が1に近い順に上から設問項目が配列してある.また非インターネット層も図中に記載されている.同図によるとウェブ効用タイプの3グループは,グラフ上では明確に分かれている.さらにウェブコミュニティGはすべての設問で出現が最も多く,低効用Gはすべての質問で出現が少なく,情報利便Gは中間にある.また設問によって分離は拡大したり縮小したり,様々である.
そこで因子分析を使って,議論を簡略化することを試みた.その結果を表8に示す.
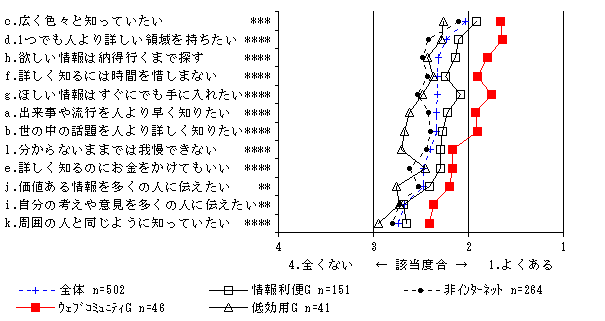
図8 情報欲求の平均値の分布
平均値の検定:**:p≦0.01,***:p≦0.001,****:Sig.≦0.0001
| 因子(平方和,寄与率) | 対応する変数(係数の大きい順↓ → ↓) |
| 第1因子 (2.94, 24.5%)
情報追求度 |
22f.詳しく知るに時間を惜しまない
22e.詳しく知るにお金を惜しまない 22h.欲しい情報は納得行くまで探す 22g.欲しい情報はすぐでも手に入れたい 22d.人に負けない詳しい領域を持ちたい ◎時間やお金を惜しまず,納得行くまで情報を追求しようとする度合を示す. |
| 第2因子 (2.63, 21.9%)
情報認知度 |
22b.世の中の話題を人より詳しく知りたい
22a.出来事や流行を人より早く知りたい 22c.いろいろなことを知っていたい 22k.周囲の知ることを知らないと落ち着かない 22l.物事を分からないままにするのは我慢出来ない ◎諸々の事柄を,とりあえずは知っておきたいと言う度合を示す. |
| 第3因子 (2.00, 16.7%)
情報共有度 |
22j.価値ある情報は多くの人に伝えたい
22i.自分の考えを多くの人に伝えたい ◎自分の情報を他人と共有したいとする度合を示す. |
(注)平方和と寄与率はバリマックス回転後の値である.寄与率の合計は63.1%である.
この様にして作成した因子がどの様な特性を持つのかを,因子得点と他の設問や変数との相関係数を求めることによって調べた.その主な結果を表9に示す.同表によると,情報追求度とウェブ利用は密接に関係し,情報追求度が強まるほどにウェブの利用度合が増すことが分かる(2).またCATVの専門番組などの選択的なテレビ利用度合も増加し,情報追求の熱心さという点では双方は共通している.
次に情報共有度であるが,この傾向が強いほどウェブコミュニティグループになりやすいことを示し,ウェブ利用と関係を持つ因子であることが分かる.
最後は情報認知度であるが,この因子はインターネットとは関係なく,地上波テレビ放送と密接に関係している.特に民放の総合編成局の視聴度合,テレビ視聴時間の長さと強い関係を持つ因子である.
| a.情報追求度 | b.情報認知度 | c.情報共有度 |
| 情報追求度が強いほど・・・・
・ウェブを見る回数が多い *** ・ウェブを見る時間が長い *** ・定期的に見るサイトが多い *** ・情報利便性が強い *** ・掲示板記入時間が長い ** ・掲示板閲読時間が長い * ・用件閲読の傾向が強い *** ・テレビ視聴時間が少ない *** ・CATV等非地上波放送のチャンネルレパートリーが多い *** ・年齢は若い ** ・高学歴である *** |
情報認知度が強いほど・・・
・インターネットでテレビ視聴時間が減らない * ・テレビ視聴時間が長い ** ・TBS,テレ朝などの民放局をよく見る *** ・地上波放送のチャンネルレパートリーが多い ** |
情報共有度が強いほど・・・
・ウェブコミュニティ性が強い * ・環境閲読の傾向が強い *** ・年齢が若い *** |
Peason *:p≦0.05,**:p≦0.01,***:p≦0.001,****:p≦0.0001
そこで情報追求度を横軸,情報共有度を縦軸として,ウェブ効用タイプの3グループの散布図を作成したのが図9である.3グループは情報欲求の因子によって有意に分離して位置づけられ,情報欲求がメディアの利用を規定していることを示している.すなわちウェブコミュニティGは情報追求度,情報共有度ともに強く,情報利便Gは情報追求度は強いが情報共有度は平均的であり,低効用Gは情報追求度は平均的だが情報共有度は弱い.この3グループ以外の非インターネット利用者はここには記入されていないが,情報共有度は平均的,情報追求度はさらに弱いところにある.この結果は情報欲求がインターネット利用行動を規定しうる量であるものとして,興味が持たれる点である.
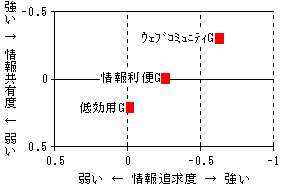
図9 情報態度の因子スコア平均値の散布図
平均値の分離は,縦方向も横方向もp≦0.05で有意