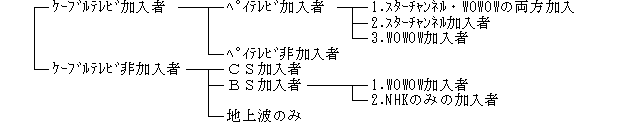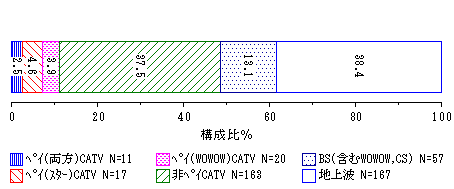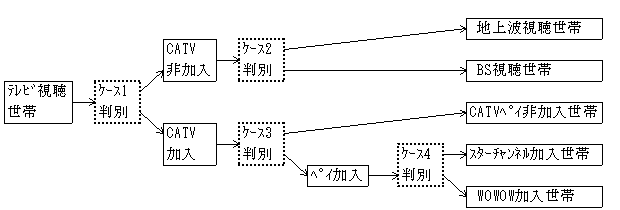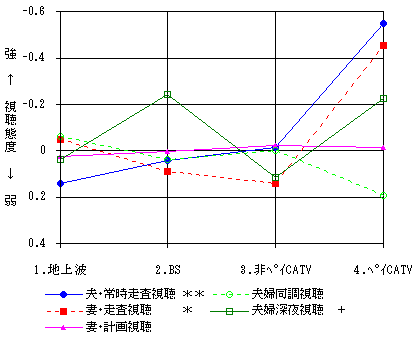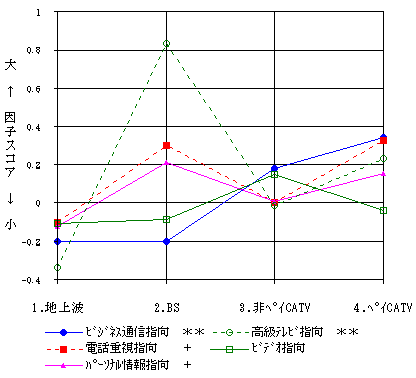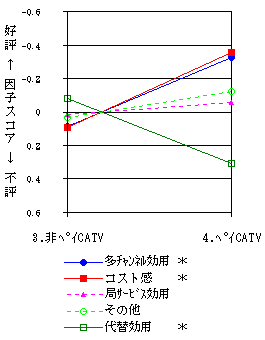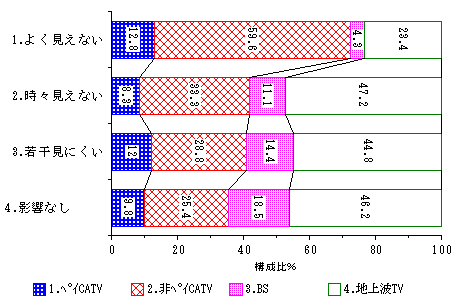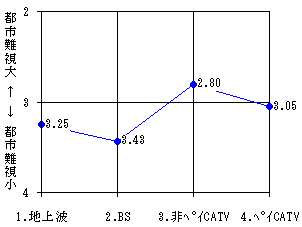対象地域で利用可能なテレビ・メディアの選択肢を図1に示す。ケーブルテレビ加入者については、ペイテレビへの加入の有無で大きくは2つに分かれる。さらにYCVのペイテレビは、スターチャンネルとWOWOWの2種類があるため、その採用の仕方で3種類に分かれる。ケーブルテレビの非加入者については、CSかBSか地上波のみかで3つに分かれる。さらにBS加入者は、WOWOWも加入かNHKのみかで2つに分かれる。
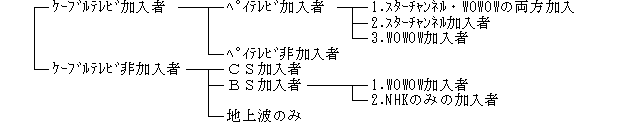
図1 対象地域におけるテレビメディアの選択肢
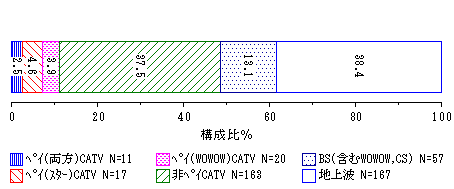
図2 調査の回収サンプル数におけるテレビ・メディアの選択
調査で得た435の有効回収数の世帯におけるテレビ・メディアの選択状況を図2に示す。CS加入者は2票(BSも加入)、BSのWOWOW加入者は5票あったがあったが、それぞれ比率が小さいので、ここではBSに含めている。
なお回収サンプルに抽出率の補正を加え、対象地域のテレビ・メディアの選択状況を推測すると次の様になっている。地上波テレビ69.5%、BS−NHK20.8%、BS−WOWOW2.1%、BSとCS0.8%、ペイ非加入のCATV5.2%、ペイ加入CATV1.5%である。約7割の世帯が地上波のみを視聴し、2割がNHK衛星放送も視聴している。残りの1割で沢山のメディア選択がなされているが、これらはすべてBS−NHKを視聴しているので、BS−NHKの視聴世帯は約3割となり、かなり大きい比率となっているのが分かる。
分析の手法としては、対象となる2つのグループへの帰属を促進している変数は何かを調べる目的で、判別分析を採用した。判別分析では2つのグループを分けるための線形判別関数を作り、その係数からグループ分けへの寄与とその度合いを知ることが出来る。このための分析の対象グループとして、図2のサンプルの状況を勘案しつつ、表1に示す4ケースを選んだ。その際に変数として利用する項目を添付している。利用可能な変数は双方のグループに共通に計測されていなければならない。また判別分析では量的な意味合いを持たせることの出来る変数である必要がある。各ケースは図3に見るようなメディア選択の位置づけとなっている。
表1 分析対象グループと変数となる調査項目
| 区分 |
分析対象グループ/変数の項目 |
| ケース 1 |
CATV非加入世帯 VS CATV加入世帯
CATVのの加入者・非加入者に共通する調査項目 |
| ケース 2 |
地上波テレビ世帯 VS BS世帯
CATV非加入者の調査項目 |
| ケース 3 |
ペイテレビ非加入世帯 VS ペイテレビ加入世帯
CATV加入者の調査項目 |
| ケース 4 |
スターチャンネル加入世帯 VS WOWOW加入世帯
CATV加入者のペイ加入者の調査項目 |
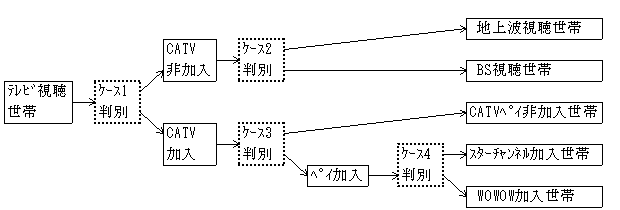
図3 判別のケースの位置づけ
調査では様々な項目についてデータを入手しているが、類似した多くの設問のある項目については、設問をグループ化して集約を図る方が効果も累積的に現れ、理解しやすい場合がある。ここでは因子分析を利用して集約をはかった設問を説明する。
(1)テレビの視聴態度とメディア選択
ケーブルテレビの加入の決定に、配偶者の意見が大きく影響することは、調査に先立って実施した加入者とのグループインタビューで明らかになっていた。したがって夫婦両方が居る世帯では、夫婦のテレビ視聴の態度が、ケーブルテレビの加入の決定に影響することが期待される。そこで調査ではテレビ視聴の態度を世帯主と配偶者の双方に別々に質問している。その質問を表2に示す。
表2 視聴態度の質問
| 質問 |
回答選択肢 |
Q5_1_1 見たい番組があるときだけテレビをつける
Q5_2_1 仕事や勉強のときに、何となくつけておく
Q5_3_1 見る番組を事前に調べて決めている
Q5_4_1 テレビを見る直前に見たい番組を調べる
Q5_5_1 テレビをつけて見たい番組を捜す
Q5_6_1 コマーシャルの間は別のチャンネルに切り換える
Q5_7_1 面白い番組が無くてチャンネルをいろいろと回す
Q5_8_1 深夜0時過ぎまでテレビを見る
Q5_9_1 他の人の見ている番組をおつきあいで見てしまう
Q5_10_1 つまらないと思ってもつい見てしまう
Q5_11_1 見たい番組が無い場合はテレビをこまめに消す |
1.よくする方である
2.どちらとも言えない
3.あまりしない方である |
この質問の回答は22個あるが、個別的に見ると多すぎて分かり難いので、視点を集約するためにそれらを因子分析にかけた。その結果、全体の分散の48%をカバーする5つの因子を得た。因子負荷行列より見た因子の意味合いを、表3に示す。第1因子は「夫・常時走査視聴」(分散の16.2%)で、夫のテレビ好きとでも言うべき視聴態度である。テレビ依存が高くチャンネル操作も頻繁(チャンネル横断的に視聴するの意味で、走査視聴と呼ぶ)な傾向を示している。第2因子は「妻・走査視聴」(同11.2%)で第1因子に似た妻の傾向である。第3因子は「妻・計画視聴」(同7.3%)で、醒めた節約型視聴とでも言うべき傾向である。第4因子と第5因子夫婦が同時に関与する視聴態度で、「夫婦追従視聴」(同7.1%)、「夫婦深夜視聴」(6.0%)である。夫婦が必ずしも独立でなく、双方が同時に係わる態度が現れた点が興味深い。
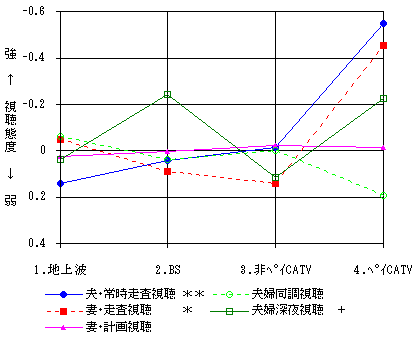
(注)1.平均値の検定:**:Sig. <0.01 *:Sig. <0.05 +:Sig. <0.10
図4 各因子スコアのメディア別平均値
次にここで抽出した5つの因子の因子スコアーがテレビ・メディアのグループ毎にどの様な傾向を示すかを見たのが、図4である。第1因子「夫・常時走査視聴」と第2因子「妻・走査視聴」はほぼ同じ様な傾向で、ペイ加入者の平均がかなり高くなっている。したがってこれらの因子は、ケーブルテレビ加入者のうちで、ペイ非加入者かペイ加入者かを区別する際に有効性を発揮する可能性がある。また第5因子「夫婦深夜視聴」は、BS加入者とペイ加入者でかなり高くなっている。したがってこの場合には、ケーブル非加入者においては地上波かBSかの区別に、ケーブルテレビ加入者においてはペイ非加入かペイ加入かの区別に効く可能性は高い。
(2)情報機器所有とメディア選択
西野(1993)によると、ケーブルテレビの加入者の方が非加入者に較べて情報機器の所有が多い。このためケーブルテレビの加入者は情報活動が積極的と見られている。今回の調査でも同じ様な点を分析したが、機器の種類によってかなり傾向が異なることが分かった。そこで表4に示す14種類の情報機器のデータを因子分析にかけて、機器所有をグループ化することにした。
表4 機器所有の質問項目
| 1.ホームビデオ |
8.ファクシミリ |
| 2.29インチ以上のテレビ |
9.コピー機 |
| 3.レーザーディスク |
10.留守番電話 |
| 4.ビデオカメラ |
11.コードレスホン |
| 5.パソコン |
12.携帯電話 |
| 6.ワープロ |
13.ポケベル |
| 7.衛星チューナー付きテレビ |
14.自分専用のテレビ |
表5 情報機器所有の各因子の定義 ( )は固有値
| 因子区分 |
構成機器 |
| 第1因子:ビジネス通信指向 (2.5) |
コピー機、ファクシミリ、携帯電話、ポケベル |
| 第2因子:電話重視指向 (1.5) |
留守番電話、コードレスホン |
| 第3因子:パーソナル情報指向 (1.3) |
自分専用テレビ、パソコン、ワープロ、レーザディスク |
| 第4因子:高級テレビ指向 (1.3) |
29"以上TV、衛星チューナー付きTV |
| 第5因子:ビデオ指向 (1.0) |
ビデオカメラ、ホームビデオ |
その結果、全体で54%の分散をカバーする5つの因子を抽出した(3)。各因子の内容を表5に示しているが、傾向はかなり明確である。第1因子は「ビジネス通信指向」(分散の17.6%)を示す機器所有である。最近これらの機器の家庭での普及が進み、必ずしもビジネス指向と言いにくい面もあるが、携帯電話まで含める概念としては、その様な呼称となろう。第1因子の因子スコアーは職業で見ると自営業、専門職、経営者で大きい。第2因子は「電話活用指向」(分散の10.6%)で、電話の機能を向上させ、家庭外とのコミュニケーションの手段として重視している。第3因子は「パーソナル情報指向」(9.4%)で、個人での情報作成・処理に慣れ、情報入手に自分のチャンネルを持つなど、パーソナルな情報活動を重視する傾向である。第4因子は「高級テレビ指向」(同9.4%)で、お金をかけテレビを楽しむ傾向、第5因子は「ビデオ指向」(同7.4%)でビデオ重視の傾向を示している。
次に各因子スコアーのメディア・グループ毎の平均の傾向を図5に示す。第1因子の「ビジネス通信指向」は、地上波やBSでは小さいが、ケーブル加入では有意に増加している。また有意性は弱いが第2因子の「電話活用指向」、第3因子の「パーソナル通信指向」はBSとペイ加入で大きくなる傾向を示している。また第4因子の「高級テレビ指向」は、BSでは非常に大きい突出ぶりを示し、高級テレビ指向がBS視聴を支えていそうな傾向を示している。
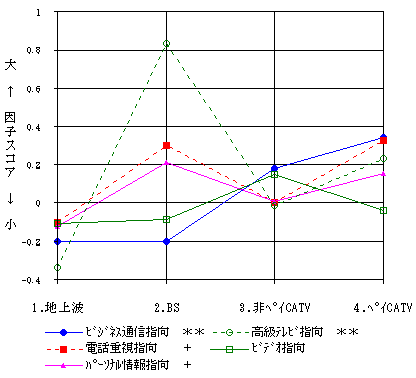
メディア選択への影響因子
1.CATV-非CATV
ビジネス通信指向
2.ペイ加入-ペイ非加入
ビジネス通信指向
3.地上波-BS
高級テレビ指向
電話重視指向
パーソナル通信指向
(注)1.平均値の検定:**:Sig. <0.01
*:Sig. <0.05 +:Sig. <0.10
図5 各因子スコアのメディア別平均値
(3)ケーブルテレビ評価とメディア選択
ケーブルテレビの効用には、多チャンネルにより専門番組を見られたり、都市難視や不良電波状況から開放され映像が向上したり、さらにはアンテナのメンテナンスが不要になるなど、様々なものが挙げられている。本調査では、それらの効用や加入・工事費用など26項目について、加入世帯主からの評価を得ている(八ッ橋(1995))。この26個の評価項目を因子分析を使ってグループ化した。その結果57%の分散をカバーする5つの因子が抽出された。各因子の概要を表6に示す。
表6 ケーブルテレビ評価の各因子の定義 ( )固有値
| 因子区分 |
内容 |
| 第1因子:多チャンネル効用 (6.7) |
色々な番組、映画・音楽、スポーツ中継、BS視聴等12項目 |
| 第2因子:費用感 (3.3) |
加入料・工事費、基本料、BS受信料など6項目 |
| 第3因子:局サービス効用 (1.8) |
顧客対応、地域貢献、メンテナンス、付加サービスの4項目 |
| 第4因子:その他 (1.6) |
レース、知人出演番組、地域情報、仕事情報の4項目 |
| 第5因子:代替効用 (1.4) |
アンテナ不要、家の外観、映像向上の3項目 |
ケーブルテレビの評価は、大筋としては4つの効用とコスト感で表されている。第1因子は「多チャンネル効用」(分散の25.6%)で、「色々な番組が選べていい」、「チャンネルが多くていい」、「映画・音楽の専門チャンネルがいい」など、12項目が含まれている。第2因子は「費用感」(12.7%)で、費用は大枠としては同じ様な傾向を示し、一つの因子に収束している。第3因子は「局サービス効用」(6.9%)で、ケーブルテレビ局の顧客サービスが該当する。第4因子は地域関連効用とでも言えなくはないが、「レース」があるためここでは「その他」(6.1%)とした。第5因子は「代替効用」(5.4%)で、「アンテナ不要」、「家の外観向上」などが該当する。
これらの因子スコアはケーブルテレビ加入者だけに限定したものであるが、メディア別の平均を図6に示す。第1因子「多チャンネル効用」、第2因子「コスト感」、第5因子「代替効用」はペイ非加入世帯とペイ加入世帯では有意な差を示している。ペイ加入者は「多チャンネル効用」、「コスト感」の点ではペイ非加入世帯より好評で、他方「代替効用」はペイ非加入世帯の方が好評である。
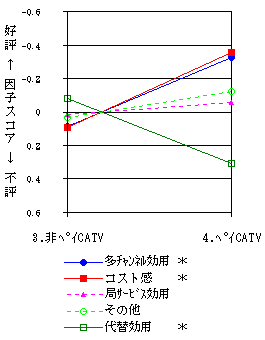
(注)1.平均値の検定: *:Sig. <0.05
図6 各因子スコアのメディア別平均
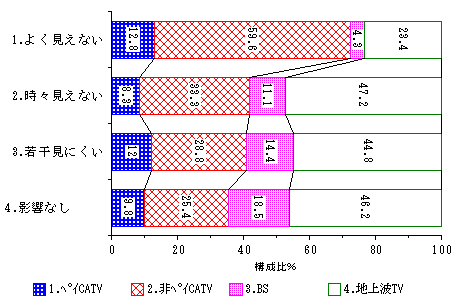
図7 都市難視とメディア選択 χ2:Sig. <0.01
メディアの選択に効く可能性のある変数として、従来は注目されたことのない変数を作成してきたが、ここでは都市難視がメディア選択に及ぼす効果を見てみる。従来から都市難視の地域ではケーブルテレビの加入率は高い、と言われている。そこで本調査では、都市難視の程度を「1.よく見えない」から「4.障害はない」まで4段階に分け、各世帯の難視状況を調査した。そのデータを利用して、都市難視の程度とメディア選択の傾向を調べたのが図7である。都市難視とともにメディアの選択が変わる様子が分かる。すなわち、都市難視の増大とともに、非ペイ加入者比率が増加し、BS加入者比率が減少し、また地上波の比率も低下する。したがって本来なら地上波かBSの層が非ペイのケーブルテレビ加入にシフトしていることを示している。
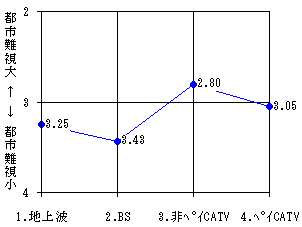
図8 都市難視度のメディア別平均値 Sig:0.0001
都市難視の度合いを平均値で見たのが図8である。非ペイのケーブルテレビ加入者の難視度が最も高く、都市難視故にケーブルテレビに加入する層の存在を示している。またBS加入者の難視度が低いことも、図7の傾向を補完している。