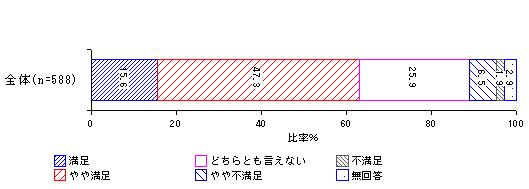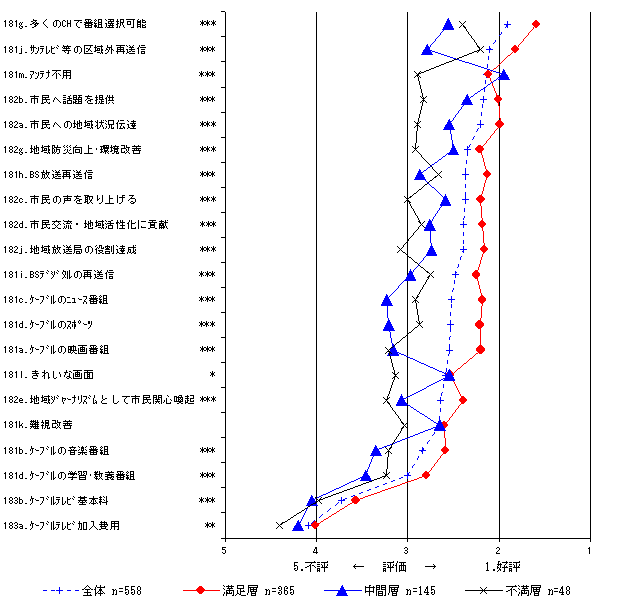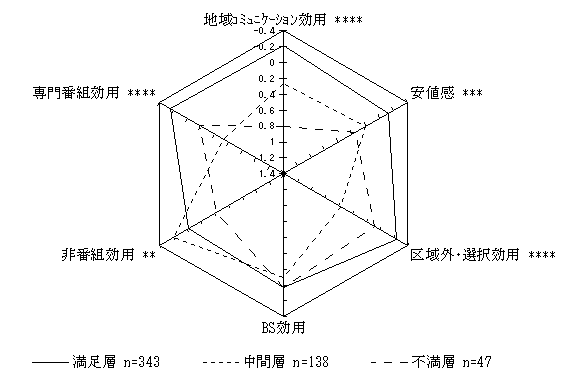調査では加入者がCATVを利用していて感じている満足度を、利用全体の総合満足度と様々な項目別の評価の2つの面から回答を得ている。ここではその両面から分析を進め、CATV利用の満足度の構造を把握する。
まず総合満足度であるが、CATV利用に対する満足度を「1.満足している」〜「5.不満である」までの5段階で聞いた結果を図5.3.2.1に示す。
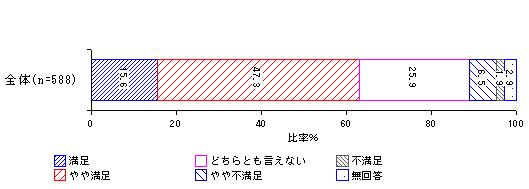
図5.3.2.1 CATVの利用の総合満足度
「1.満足」、「2.やや満足」の合計は6割強で、「4.やや不満」、「5.不満]の合計は1割弱であり、全般的には満足度はかなり高いということが出来る。無回答を除外して選択肢番号の平均として満足度の平均を求めると、2.30である。全体としては、「2.やや満足」よりもすこし「3.どちらとも言えない」側によった位置にある。
なお以下ではこの総合満足度の結果から加入者を、「1.満足」と「2.やや満足」を満足層、「3.どちらとも言えない」を中間層、「4.やや不満足」と「5.不満足」を不満層とし、3グループに分けて、様々な分析を行っている。
CATVの利用は多面的な効果を持ちうる。そこでCATVの利用がもたらしうる多くのメリットの項目を列挙し、それぞれの項目ごとに利用者がどの程度のメリットを得ているかを、5段階で調査した。例えば、「a.ケーブルのチャンネルによる映画番組がいい」に対して、「1.そう思う」〜「5.そうは思わない」の5段階のどれかで回答を得た。その結果から前記の3グループ別の平均値を求め、21の項目別に比較した結果を図5.3.2.2に示す。
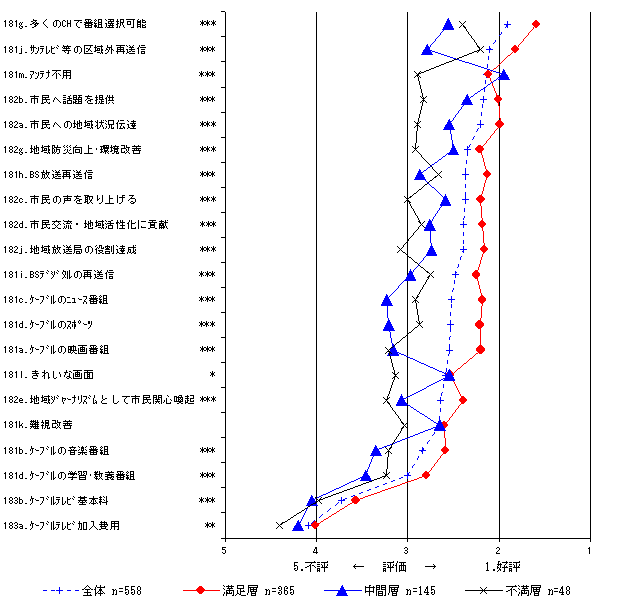
図5.3.2.2 CATVの利用の項目別評価の平均値
平均値の検定:*:0.01<p≦0.05,**:0.001<p≦0.01,***:0.001<p≦0.0001,・・・・
項目の配列の順序は、全体の値が小さい(評価が高い)順に、図の上から下に向かって書かれている。この図を見ると次のような点が明らかになる。
-
満足層は、「181j.アンテナ不用」以外のすべての項目で他の2つのグループより評価の平均は良好である。
-
中間層と不満層は全般には全体の左側(評価が低い側)にある。
-
中間層と不満層の評価はかなり入り組んでいる。中間層の方が良好な評価をしている項目は12あり、不満層の方が良好な評価をしている項目は9ある。
これらの全般的な傾向を見ると、利用者の満足度評価は、これらの様々な項目の総合満足度として形成されている可能性は高いものの、中間層と不満層の評価はかなり入り組んでおり、総合満足度の形成は複雑な面があると予想される。
この様な点を考慮しつつ、以下では議論をより単純化する目的で、21個の評価に対して因子分析を適用する。
図5.3.2.2に示した21項目の評価結果にさらに、「138a.ケーブルテレビの加入費用」、「138b.ケーブルテレビの毎月の基本料」というコスト感と関係する項目を「1.安い」〜「5.高い」の5段階評価された結果を加え、23項目の評価結果に対して因子分析を適用した。その結果を表5.3.2.1に示す。
表5.3.2.1 利用満足の因子と対応する変数
| 因子(平方和、寄与率) |
対応する変数(係数の大きい順↓ → ↓) |
第1因子 (4.59, 23.0%)
地域コミュニケーション効用 |
182b.市民の話題提供 182a.市民に地域状況伝達
182c.市民の声を提起 182j.地域放送局の役割実現
182d.市民交流等に貢献 182e.地域ジャーナリズムで市民関心喚起
◎市民に地域の話題や市民の声、市民交流の促進に貢献する
などの地域コミュニケーションの促進に関する満足 |
第2因子 (3.42, 17.1%)
専門番組効用 |
181b.ケーブルの音楽番組 181d.ケーブルのスポーツ番組
181e.ケーブルでの学習教養番組 181a.ケーブルの映画番組
181c.ケーブルのニュース
◎ケーブルテレビの専門番組を視聴することの満足 |
第3因子 (2.34, 11.7%)
非番組効用 |
181l.きれいな画面 181m.アンテナ不用
181k.難視対策
◎美しい映像やアンテナ不用の利点の満足 |
第4因子 (1.68, 8.4%)
BS効用 |
181i.BSの再送信
181j.BSデジタルの再送信
◎BS放送を見ることが出来ることでの満足 |
第5因子 (1.62, 8.1%)
区域外・選択効用 |
181j.サンテレビ、瀬戸内海放送などの区域外再送信
181g.多くのCHのいろいろな番組を選べる
◎区域外再送信や多くの番組を選択できることに対する満足 |
第6因子 (1.53, 7.7%)
安値感 |
183a.初期加入料
183b.毎月の基本料
◎かかる費用を安く感じる程度(コスト感の逆) |
(注)平方和と寄与率はバリマックス回転後の値である。寄与率の合計は75.9%である。
6個の因子で、元々の分散の約76%がカバーされている。それぞれの因子の概念はかなり明確で、地域コミュニケーション効用、専門番組効用、非番組効用、BS効用、区域外・選択効用、安値感である。なお安値感とは、費用を安く感じる傾向(分析対象者の中で相対的に費用を安く感じる傾向)を表している。いわばコスト感とは逆の概念である。すべての評価の項目は、選択肢番号1の方が合意傾向であり、、反対に選択肢番号5の方が否定傾向であるため、新たに形成された因子スコアは、負で絶対値が大きい方が因子の傾向が強く、正で絶対値が大きい方が因子の傾向は弱いことになる。また因子スコア0は、全体の平均の水準にあることを示す。
因子分析の結果で得られた因子スコアの満足度グループ毎の平均値を求め、グループの平均的な姿を求めた結果を、図5.3.2.3に示す。
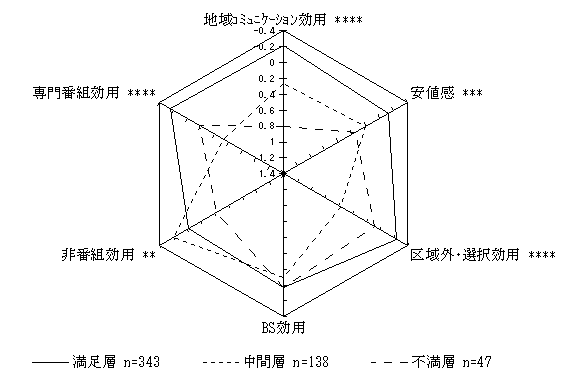
図5.3.2.3 CATVの利用満足に関する因子スコアの平均値
平均値の検定:*:0.01<p≦0.05,**:0.001<p≦0.01,***:0.001<p≦0.0001,・・・・
同図からは次のような点を知ることが出来る。
-
満足層は全般に概してどの因子でも評価が高い。しかし非番組効用については評価は平均値水準より若干下にある。
-
中間層は、地域コミュニケーション効用、安値感は中間の評価であるが、非番組効用は最も評価が高く、専門番組効用、区域外・選択効用では評価は最下位にある。
-
不満層は地域コミュニケーション効用、非番組効用、安値感では最下位の評価であるが、専門番組効用、区域外・選択効用では中間層を越えている。
-
BS効用はどの層も同じような評価で、この点では差は小さい。
-
中間層と不満層の位置づけはかなり複雑である。
全般に満足度の構造が、中間層と不満層の2つのグループで特に複雑であることを示している。これは(2)項目別の評価で垣間見た結果と一致している。しかし総合満足度が21個の評価項目をで総合した6個の因子で表されるとした場合、各因子が総合満足度に対してどの様な寄与をするのか(ウエイトを持つか)も重要な検討事項である。
そこで6個の因子スコアを説明変数とし、総合満足度を従属変数として、回帰分析を行った。その結果を表5.3.2.2に示す。分析は強制投入方式とステップワイズ方式の2通りで行い、ほぼ同じような結果を得ている。その結果を下記にまとめる。
表5.3.2.2 回帰分析の回帰係数
| 因子 |
強制投入方式 |
ステップワイズ方式 |
| fq18n61:地域コミュニケーション効用 |
0.341
|
0.341
|
| fq18n62:専門番組効用 |
0.251
|
0.251
|
| fq18n63:非番組効用 |
0.056
|
−
|
| fq18n64:BS効用 |
0.036
|
−
|
| fq18n65:区域外・選択効用 |
0.194
|
0.194
|
| fq18n66:安値感(コスト感では負) |
0.167
|
0.167
|
| 定数 |
2.302
|
2.302
|
| 重相関係数 |
0.562
|
0.557
|
| 寄与率 |
0.315
|
0.310
|
| 回帰式の有意性P |
0.0000
|
0.0000
|
総合満足度の持っている分散の約30%強が回帰式で再現されている。再現されていない割合が多いために、決定的な結果とはいいにくい点があるが、この制約下で次の点が明らかである。
-
利用満足度は次の式で表される。
利用満足度= 0.341*fq18n61+ 0.251*fq18n62 + 0.194*fq18n65
+ 0.167*fq18n66 + 2.302
-
満足度に効く順序は、係数の大小で直接比較可能である。
地域コミュニケーション効用>専門番組効用>区域外・選択効用>安値感
加入動機としての有効性は強いとは見えなかったが、満足度では最大の源泉となっている。
-
非番組効用、BS効用は、満足度を構成する有効な要因ではない。
因子スコアは直交標準化データであるために、相互に独立である。このために回帰式の係数の絶対値の大小関係は直接に総合満足度への寄与の度合を表す。したがって、加入者が感じている満足度に寄与する要因として、「地域コミュニケーション効用」が最も大きい効果を発揮していることは明確である。次いで「専門番組効用」、「区域外・選択効用」となっている。
なお本節の5.3.6項に、本項の結果と比較するための参照ケースとして、首都圏のあるCATV局における満足の構造を示している。双方を比較すると、サービスへの注力度合と地域差がもたらす満足度の構造の違いが明確に理解できる。