はじめに
現代社会において、漫画が確固たる日本文化の一つであることは否定できないであろう。そしてそれと同様に日本アニメーションも世界に誇る日本の文化の一つである。かつては漫画の神様であり日本アニメーションの生みの親である手塚治虫は、アメリカのウォルト・ディズニーのアニメーションに憧れて、日本でのアニメーション制作に力を注いだ。しかし今や、その手塚のアニメ「ジャングル大帝レオ」が、ディズーアニメに逆輸入されて、「ライオンキング」というアニメーション映画になったことはあまりに有名である。
アニメーションは今や大人も楽しめる立派な文化に日本においても成長したということであろう。いやむしろ世界のアニメーションは今や日本が牽引しているといってよい状況なのではなかろうか。 その日本アニメをテレビアニメに限定して類別すると次のようになる。
①SFロボットアニメ(ガンダムX・ダグオン・黄金勇者ゴルドラン)
②魔法・変身アニメ(セーラームーンシリーズ・ウェディングピーチ)
③冒険アクションアニメ(ストリートファイターⅡ・バーチャファイター・ドラゴンボール)
④スポコンアニメ(H2・スラムダンク)
⑤学園恋愛アニメ(ご近所物語)
⑥ゲーム・ホビーアニメ(ドッジ弾兵・爆走兄弟レッツ & ゴー)
⑦ホームアニメ(サザエさん・ちびまる子ちゃん)
⑧幼児むけアニメ(ドラえもん・キテレツ大百科・ポコにゃん・アンパンマン)
⑨名作もの(ロミオの青い空・名犬ラッシー)
⑩その他(地獄先生ぬーべー、ゲゲゲの鬼太郎) [註:( )内は最近のアニメ]このうち、本論で問題にするのは、②魔法変身アニメである。これは古くは「魔法使いサリー」に始まり、つづく「ひみつのアッ子ちゃん」では魔法のコンパクトが爆発的にヒットした。当時、「テクマクマヤコン」という呪文を知らない女の子はいなかったに違いない。その後、クリーミィ・マミがアイドル性を備え、現実のアイドル歌手とオーバーラップさせて人気を博した。ちょうど、クリーミィ・マミが放映された頃は、アニメの全盛期で、新技術もどんどん開発され、世の中でも「アイドル」が小泉今日子などを中心に幅をきかせた時代であった。さらに世はSFを抵抗なく受け入れる時代でもあった。それには小説や漫画の影響はもとより、スピルバーグを代表とするアメリカSF映画の影響が大であった。そうした状況下において、クリーミィ・マミは女の子はもとよりアニメ好きの青少年をも巻き込んで、アイドル・SF性をもった魔法・変身アニメとして人気を博した。
その後、テレビ局は手をかえ、品を変えて魔法・変身アニメを制作・提供しつづけた。そうして1992年にセーラームーンが登場する。1.セーラームーンの登場
今の幼女ならばセーラームーンの存在を知っているであろうが、大人のなかには名前だけで、その内容を知らない人もいるであろうから、簡単にその内容を記しておこう。
主人公は月野うさぎ、14歳、中学2年生。ある日、ルナという黒猫に出会う。うさぎはルナから胸飾りをもらい、「ムーン・プリズムパワー・メイクアップ」と唱えると、セーラームーンに変身できるようになる。ルナはうさぎを始めとするセーラー戦士をみつけるために地球にやってきた使者。セーラーマーキュリー、セーラーマーズ、セーラージュピター、セーラーヴィーナスと次々とセーラー戦士を見つけだし、地球制服をねらうダーク・キングダムから地球を守ろうとしている。そしてセーラー戦士たちは、ダーク・キングダムが送り出す妖魔と闘うわけだが、主人公のセーラームーンは、他の四人のセーラー戦士やタキシード仮面に助けられてばかりいる。
基本的にはセーラー戦士と妖魔の闘いだが、テレビが進行するにしたがって、話も複雑となり、白猫のアルテミスが加わり、セーラー戦士たちは月のプリンセス・セレニティを見つけることになる。ところがそのクィーン・セレニティは実はうさぎことセーラームーンで、他の四人の戦士は月の王国の四守護神の生まれ変わりで、味方であったタキシード仮面は地球のプリンスエンディミオンの生まれ変わりと、どんどん話は広がる。
ドジな主人公だが、最後のキメはきっちりとつける。そして「月にかわっておしおきヨ!」という合言葉が、子どもたちの間で流行した。いや、子どもだけでなく、この流行語は実態を知らない大人たちの間でも流行した。大人たちはセーラームーンがどのような話かは知らなくても、制服の美少女たちがセーラー戦士であることは知っていて、その合言葉がコケティシュであることを知っているのである。
つまり、大人にとってセーラームーンは、幼児アニメではなく、現実の女子中高校生が「おしおき」してくれる、あるいは彼女たちに「おしおき」するイメージをもつことで、流行語に参加することができたのである。
「セーラームーン」は「セーラームーンR」から「セーラームーンSS」へ、さらに「セーラースターズ」へと、シリーズは広がる。登場人物が増えれば増えるほど、キャラクター商品は増えることになる。
あるデパートでおもちゃ売場の成績をなんとか上げたいと、必死の思いで企画を考え、セーラームーンの等身大(大人の大きさ)の人形(というかロボット)を設置すると、大当たりで、売場に活気が戻ったという。つまり、それほど子供達の間でセーラームーンの人気はすごいのであり、大人の注目度も高かったといえよう。
現代社会において、幼児向けテレビアニメの持つもう一つの意味が、このキャラクター商品である。おもちゃ会社はテレビの人気キャラクターを商品化することで、自社の業績アップを企図する。
そこにはおもちゃ本来の有用性や工夫はなにもなく、ただただ人気キャラクターへの依存性のみが見られる。おもちゃ会社には、子どもたちに、楽しいおもちゃ・教育的なおもちゃ・想像性あるおもちゃを与えようという姿勢はまったく見られず、ただ利益をあげるのにてっとり早い方法として、テレビキャラクターを利用している[註1]。その典型が(株)バンダイであろう。バンダイの主要玩具の一つは、このセーラームーン人形と機関車トーマスエンジン・シリーズである。この両方が、テレビが生み出したキャラクターであり、けっしてバンダイが製作したおもちゃキャラクターではない。 それに対して、タカラ玩具が生み出したリカちゃん人形は、タカラのオリジナルキャラクターである。ここで、女児にとってのキャラクター商品代表「リカちゃん」人形に登場してもらおう。
「リカちゃん」は昭和42年7月に発売され、その後、リカちゃんの母・姉・父等が作りだされている。これは、今も引き続き製造・発売されているわけで、現在の女児からすれば、自分の母親が子どもであった頃からのキャラクター人形ということになり、親子二代にわたる商品となる。
リカちゃんの広報を担当した久保田修介氏はリカちゃんの商品コンセプトについて次のように語る[註2]。「リカちゃん理念」には、「リカちゃん」人形遊びを通して、少女たちに美意識や感性を発露させるとともに、現代社会の学習、教育を提案しています。さらに少女たちの想像力を喚起させ、いつくしみの心、人をいたわり、愛する心を育て、健やかな成長がはかられることを願うとうたわれています。
つまり、「リカちゃん」人形の原点は生きる喜び、夢や憧れ、愛やいつくしみ、心の潤いを得たいという人間としての〝普遍的願望〟を満たすものを創造することです。

久保田氏の言が額面通りではないにしても、「リカちゃん」人形が昭和42年以降の女児・少女たちに、ある種の夢と想像力を与えたことはたしかであろう。
リカちゃん人形で遊ぶのと、セーラームーン人形で遊ぶのとどう違うのかという質問もあろう。実は両者には決定的な差がある。キャラクター人形で遊ぶ場合、子どもたちはどうしても、テレビドラマをなぞることが中心となり、そこには自分自身による創作は減少する。もちろんリカちゃん人形での遊びも、家庭でのできごとの物真似的な要素はあるが、リカちゃんの性格設定は、その子どもに任され、いろんな性格のリカちゃんが生まれることになる。
そこに、単一な性格、すでにテレビによって性格が設定されたキャラクター人形と、おもちゃ会社独自の人形との差が生まれる。
男児に人気の機関車トーマスについても同じことが言える。同じ機関車を素材にしたおもちゃでも、スェーデンのBRIO社の木製の機関車シリーズは、ディテールのみ機関車や客車・貨車であるが、特別なキャラクターを見出せるような特徴はない。キャラクターは子ども自身が作り出す物であるというポリシーが如実に現われている。
より高度な機械性を求める小学生とは違って、幼児には自らがその玩具に工夫をこらし、想像力で接することのできるおもちゃの方が適しているのではないであろうか。
かつて、我々は自然の中に、自ら玩具を見出して、どんぐりで独楽を作ったり、葉で手裏剣を作ったり、もっと単純には松ぼっくりをボールに見立てたりと、いろんな工夫を懲らして来た。この「見立て」ということも重要な創造力のひとつである。ママゴトはすべて見立てである。自分を母親に擬し、人形を赤ちゃんに擬し、ドロを御飯に見立て、葉っぱや草を野菜に見立てる。砂場は家であり、台所であり、庭である。本物そっくりな玩具を大人に与えられるのではなく、自分で探してきて、それらに擬すのである。そこにこそ、子どもの智慧が生まれる。
「ごっこ」は遊びであると同時に練習である。それは材料を集めることから始まるのに、今のように擬似玩具が揃っていると、子どもたちの楽しみは、実は半減してしまうし、ミニチュア玩具以外を認めなくなり、創造性が損なわれることになる。2. セーラームーンのキャラクター
主人公の「うさぎ」を始めとしてセーラー戦士たちは女子中学生である。それゆえ、彼女たちは常には学校のセーラー服を着ている。そして彼女たちは戦士に変身しても基本的なコスチュームはセーラー服である。それゆえ、彼女達は「セーラー服美少女戦士」なのである。
なぜ彼女たちはかくもセーラー服を着用しなければならないのであろうか。
ここで、代表的な最近の魔法的変身少女の主人公の普段のコスチュームを比較してみよう。
aセーラームーン、bミンキーモモ、c赤ずきんチャチャ、d魔法陣ぐるぐる、eレイアース、fウェディングピーチ、
彼女達はA幼児体タイプ、B美少女体タイプに二分することができる。
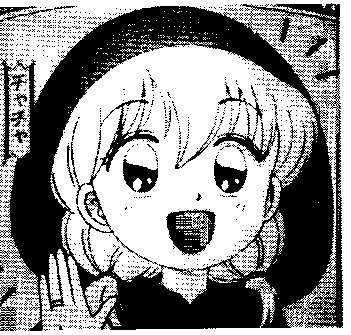
A幼児体タイプ……b,c,d
B美少女体タイプ…a,e,fA幼児体タイプは基本的にコスチュームは幼児服であり、そこに「おしゃれ」感覚は少ない。ミンキーモモには多少あるが、それは大人のおしゃれとはことなる「かわいさ」でしかない。それに対して、B美少女体タイプのコスチュームは美麗であり、装飾的である。
このうち、セーラームーンはB美少女体型に属するわけであるが、この中でもセーラームーンは異色性を放つ。それは先に指摘したように、戦闘態形に変身してももとの服装とさしたる変化はなく、そのため、変身してもあまり強くない。いつもサブキャラのタキシード仮面に助けられるという設定となる。これはeレイアースマジックナイトの3少女とは正反対である。彼女たちは変身後には武器を持ち、戦闘の結果、血を流すことさえある。
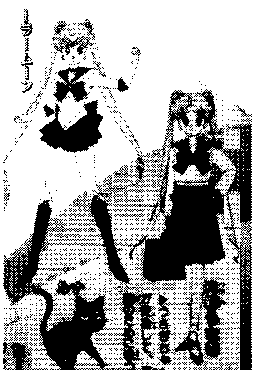
セーラームーンには、主人公の設定として、
a①美少女だが出来は良くない。
a②特別の能力を付与されてもあまり効果をだせない。
a③第三者に助けてもらう。
という三要素が見出せる。しかし普通のパターンでゆくと、
b①普通の少女だが、心は優しい。
b②特別の能力を授けられ、平和のために問題を解決する。
b③サブキャラが陰から援助する。
となり、①→②→③という一連のストーリー展開が視聴者を納得させる構成となる。しかるに、セーラームーンでは、問題の解決は主人公ではなく、陰の存在でなければならない第三者サブキャラが行なっている。つまり、主人公こそが「問題解決」においては、「刺身の妻」なのである。奇しくも第13回放映の「女の子は団結よ!ジェダイトの最後」の巻で、悪役のジェダイトが「泣け!わめけ!男がいなければ、なにもできない、あさはかな女たちよ」と哄笑している[註3]
これはいったいどうゆう設定なのか。
ようするに主人公「うさぎ」はa①のためだけに存在しているのである。そしてa①の要素とは、まさに現代の少女像にほかならない。
それは、学校の成績もたいしてよくなく、かといって何か特別なことに一生懸命というわけでもない(a①)。他人が助力しようとしても、それを真剣に受け止めないため、結局、身に就かない(a②)。そして自分を好きになってくれる人の全面的援助を大胆に受け入れる(a③)。都会の彼女たちには、ブルセラ・モデルや援助交際が、大金の入手方法として呈示されている。
そこには人権問題など吹き飛んでしまうほどの現実が、ごく限られた空間と時間と交流の中において存在してしまっている。
しかし考えてみれば、女性を「美少女」という「ものさし」でしか計らない風潮を我々は認めてしまっている。たとえば、最近のコマーシャルである。
エステティックのCMで「わたし、身体もすごいんです」という台詞がある。これは「身体も」ということの前提として、「顔は当然いいんです」というのがある。会社の先輩女史に対して、若さと美貌を武器に男を味方にすることを全面肯定したCMである。
かつてミスコンが女性を表面的な美でしか判断しない、男中心の勝手な差別行為として非難されたことがあった。では、このCMはなんなのだ。男性が主催するものは否定するが、女性のために少しでもためになるものならば(美容という点で)、許されるというのであろうか。
いやそうではないであろう。ようは女性の人権を真剣に考えている人数よりも、自分の美を高めようとだけ考えている人の数のほうが圧倒的に多いということにすぎまい。
これ以上、人権問題に踏み込むことはよそう。問題はセーラームーンが生み出されたコンセプトである。
主人公「うさぎ」は、バカでも無能力でもよいのである。制服が似合って、プロポーションがよければそれで、現代のヒロインになれるのである。
つまり、正義=美(顔と身体)という公式が成り立ちさえすればよいことになる。
これは女児・少女が自ら求めるキャラクターでは、けっしてない。では誰の求めるキャラクターなのか。それは、女子中学生をブルセラの対象とし、コギャルを性のはけ口にしようとする大人の求めるキャラクターにほかならない。
セーラームーンは子どものためのキャラクターではなく、大人のためのキャラクターなのである。
女児がセーラームーンに夢中になっている時、同じ年齢の男児は何に熱中しているのであろうか。
正確な統計をとったわけではないが、『テレビといっしょ』『テレビランド』『めばえ』『幼稚園』等の幼児雑誌を概観すると、男児に人気のあるのは、実写ものの正義のヒーロー番組や機関車トーマス等の乗物が出てくる番組のようだ。
これらにはまたそれなりの批判もあるが、セーラームーンに比べれば幼稚で純朴である。ことにトーマスシリーズは、イギリスの作家W.オードリーの原作がしっかりしていることもあり、幼児向けのストーリーがきちんとできている[註4]。男児の一部はこのような幼児らしい話に触れているわけである。
それに比べて女児の番組は限定されており、いきおいセーラームーンが主流となる。セーラームーンがコギャルの象徴ならば、セーラームーンを見せることは、コギャル症候群のワクチンを打っているようなものとなる。3.商業主義と保護者の立場
幼い子どもほど社会の影響を受けていないのは自明のことである。つまり現代的な赤ちゃんとか、昔の赤ちゃんという言い方は原則的には存在しないことになる。赤ちゃんは昔も今も「赤ちゃん」でしかないのである。医学の進歩や、社会の進化によって、赤ちゃんがこれから成長していく条件は、昔と今ではずいぶんと違うことであろう。しかし生まれたての赤ちゃんが、それらの諸条件を備え持って生まれてくるわけではない。それらの社会的環境は、あくまで後天的条件にすぎない。
この論理でいうならば、最初から「現代っ子」はいないことになる。幼児を「現代っ子」にするのは、親を始めとするまわりの環境である。
かつては子どもたちは、自分が行動できる範囲の情報しか得られなかったし、周囲の言動のみがその模範であった。しかしメディアが発達した現代社会においては、その情報量は格段に飛躍した。テレビさえ見れば、理解するとしないとにかかわらず、世界の裏側のことまで知ることができる。
もっといえば、本当には理解できない情報を多量に注ぎこまれる状況にある。その結果がどうなるかは帰納的には実証されていないから、なんともいえないが、本当に年齢にみあった情報を見逃す危険性は高まっているということはできるであろう。
バラエティ番組の下品なギャグであろうが、ほのぼのとした動物番組であろうが、同じレベルで情報として子どもの目に飛び込んでくる。また実際の動物や昆虫を見る前に、テレビでそれを知ることも多いであろう。テレビで見た熊は猛獣でもないし、テレビの中の毒蛇はけっして噛みつかない。このような状況が普遍化すると、その生き物本来がもつ特性は無視した状態で、子どもたちはその存在を「知識」として知ることになる。
けっして山で出会った恐い動物や、草むらで遭遇した危険な生き物とは理解できないのである。人間には間接体験と直接体験の二つがあり、両者とも重要なのであるが、深谷和子氏はこの二種類の体験には必要な出会いの順序があるとする。そして、「人生の初期にはまず、具体的で生き生きとした直接体験によって、子どもの体験世界が構成される必要があ」り、間接体験は「直接体験のつみ重ね」を経た後にのみ「確かな形で体験の世界に組み込まれる」と論じる[註5]。まさにそのとおりであろう。
とはいえ、今のテレビの存在する状況を否定してもはじまらない。すでに存在する状況の中で、我々は幼児教育を考えねばならない。まず、現在、幼児たちがどの程度テレビをみているかをNHK放送世論調査所の調査によって眺めてみると、表1のごとくなる[註6]。
これによると、幼児の一日の平均視聴時間は3時間弱である。しかし3歳児は、ながら視聴をいれると約5時間となる。3歳児というと10~12時間の睡眠をとる。そうすると、起きている時間の約4割がテレビ視聴時間となる。
社会学の方面から、井上宏氏は、現代の子どもたちが、程度の差はあるものの、生まれた時からテレビがすぐそばにあり、テレビに慣れ親しんでゆく状況を「テレビ接触のなかで、ある種の感覚的反応の仕方を身につけていく、別のいい方をすれば、彼らなりの情報処理の仕方を発展させていく」ことと判断している[註7]。
また井上は「子どもにとってテレビはまさに‘魔法の箱”であって、見たくて見たくて仕方がない。しかし、親は子どもの長時間視聴をコントロールしたいし、家族がそろう食事時には、子どもをテレビから離したいと思う」[註8]と述べ、さらに「親の方も矛盾していて、食事時に見たいものがあれば、見ながら食事してしまう」と親の態度を批判している。そのうえで、「テレビは家族の団らんを阻害することになったのか、あるいは促進することになったのか」と問題提起している[註9]。
結論的にいってしまえば、テレビ以外の方法で家族の団らんを形成するのがいいに決まっている。しかし親たちは必ずといってよいほど子どもにテレビを見せ、自分も見る。まず子どもにテレビを見せるのは時間かせぎのためである。朝の忙しい時、NHKの「お母さんといっしょ」やフジテレビの「ひらけポンキッキーズ」を見させておけば、子どもは静かにテレビに集中しており、母親は安心して家事ができる。夕方の5時から6時にかけても同様である。夕食の支度をする時間帯にうまく幼児向け番組が設定されており、どうしてもそれに依存せざるをえない。
そして、主婦が一息つけるのは、夕食事の一時であり、その時間に楽しめるのテレビとなる。いきおい子どもも母親と一緒にテレビをみることとなる。この生活サイクルを改善することは非常に困難であろう。いやほとんど不可能といってよかろう。
ここでは、それにふれることはしない。それよりもテレビの内容について論じたい。テレビを避けることはできないにしても、幼児が見るテレビを選択することぐらいはまだできるであろう。
上田融氏はCMを通して企業が子どもをターゲットにあくどい商業を展開していることを指摘する[註10]。上田氏によると、子どもが企業のターゲットになったのは1970年代に入ってからのことで、「テレビという巨大なメディアが介在してのこと」だという。そして上田の心配も児童の創造力の欠如にあった。子どもをターゲットにしている産業の側は、あくなき商魂でこれでもか、これでもかと子どもの”メカ志向”をそそる商品を作り出すだろう。それは商売だからやるのは仕方がないとしても、私が心配なのは、既製品でメカが手に入るという生活、金さえ出せばいいという消費志向のなかで、創造性という人間としてのかけがえのないものを失っていかないかということである[註11]。
資本主義社会において、営利追求は公認されており、むしろどれだけ多く儲けたかが人間の尺度となっている。つまり倫理や道徳よりも利潤追求が肯定される社会である。公害がでようが、子どもが蝕まれようが、高利潤をあげた人間は「エライ人」として崇められる社会である。我々は、この資本主義社会に生きていることを忘れてはならない。これを忘れて理想論を展開してもなんの役にも立ちはしない。
しかし、同時に親となり保護者となれば、本能的に子どもを守ろうとすることも事実であるし、それが生き物の自然な姿であろう。このことはなにもテレビに限ったことではない。子どもの生活空間全体にもかかわることである。室崎生子氏は子どもの生活空間について、「子どもを育てる都市空間の設計は、経済優先の論理でなく生活者の論理からおこなうものである。安全で、子どもが自由に利用でき、人々の連帯・交流を促す空間が配慮され、生産活動を支え、生活の便利さが保障されるまとまりある範囲で、誰もが移動しやすい徒歩圏の生活空間を守ることが基本となる」と論じ、その一例を京都市に求めている[註12]。
また、鈴木みどり氏は「テレビの商業化が急速に進行するなかにあって、子どもはその視聴経験の累積から学ぶ以上に多くを失っているのが現実ではないだろうか」と、子どもが成長すれば批判力も身につくことを認めながらも危惧を訴える[註13]。
さらに鈴木氏は、十代の子どもの生活まるごと商品化し、それを「情報」という名で販売する番組が出現している。テレビの商業主義がここまで進んでいるのだから、テレビを「環境」として生きる子どもたちがその心の商業化に抵抗し、人間らしい成長を遂げるのは容易ではない[註14]。
と、十代の子どもについても危惧を述べる。
個人主義の時代、資本主義の社会で我々が子どもとはいえ干渉できることは少ないであろう。そしてテレビが現代社会において消滅させることのできないものであることも事実である。今さら減反政策以前の日本にもどることは出来ないし、テレビのない時代にも戻れない。
できることといえば、せいぜい我が子を守る事ぐらいである。それも子どもの権利を尊重しながら。テレビチャンネルは幼児よりは大人にまだ独占権が残されている。これも大人の専制性かもしれない。しかし封建主義といわれようと、いやらしい中年の性向まるだしで作製され、キャラクター商品のために続けられているセーラームーンから子どもを守るくらいはしてもよいのではないかと考える。