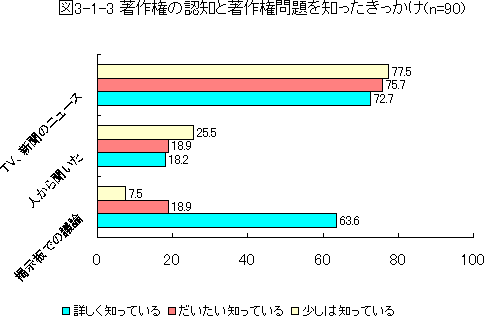←戻る 次へ→
3.研究の成果
3.1 著作権の「認知」と「理解」
(1) 著作権の「認知」
インターネットなどの普及によって、「著作権」に触れる機会が増えたのにも関わらず、著作権そのものや内容については殆ど知られていないのではないだろうかと予想した。そこで、まず、「著作権についてどのくらい知っているのか」を調査した。
図3-1-1はその結果である。TVや新聞などでも取り上げられることが増えたこともあり、約97%が著作権を「知っている」と回答している。さらに、1割は著作権について「詳しく知っている」と答えている。

次に、楽曲の歌詞がサイトに無断で掲載されていたり、MP3等で無断で楽曲を公開していたりするなどのインターネット上での著作権の問題についてみていく。インターネット上で著作権が問題になっていることについては83%の人が何らかのことから問題になっていることを知っているようである。
続いて、インターネット上での著作権問題を知っていると回答した人だけに限定して調査した。まず、インターネット上で著作権が問題になっていることを知ったきっかけは何だったかを図3-1-2に示す。
約半数がTV、新聞などのニュースから知ったと回答している。他の項目と比べるとその割合は特に高くなっている。

図3-1-3は、図3-1-1で示した著作権の認知についての結果と、図3-2-2の著作権問題を知ったきっかけの結果をクロス集計したものである。ここでは、いくつかの項目のみグラフにして表示している。
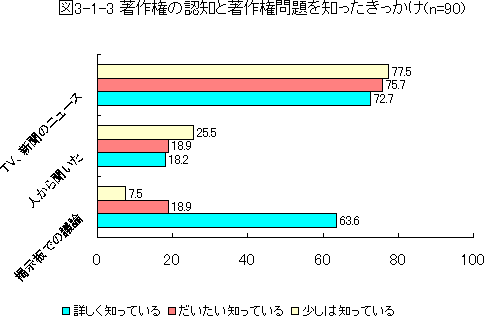
ここでは、「掲示板サイトで知った」という項目に注目したい。
著作権を詳しく知っていると答えたグループでは「掲示板サイトの議論で知った」という割合は6割近くになっているが、著作権に関する知識が乏しくなるほどこの割合は減少している。特に、著作権について詳しく知っていると回答した人と、そうでない人の間の差は顕著に表れている。
このことから、掲示板サイトの著作権に関する議論は深い部分まで踏みこまれているのではないかといえる。逆に、TV、新聞などのニュースの場合、意識して見たり、読んだりしたものではなくたまたま目に入ったものではないかといえるのではないか。
また、詳しく知っていると回答している人は、受け身で著作権の情報を得ているのではなく、進んでそれらの情報を集めているのではないかと推測できる。
(2) 著作権の「理解」
(1)では、著作権についてどの程度知っているのかをみてきた。ここからは、著作権の内容についてどのくらい「理解」されているのかということについてみていく。
まず、調査票に著作権侵害の行為と侵害でない行為の両方をランダムに書き、その中から「著作権侵害にあたると思うのもの」を選んでもらうという方法を取った。以下、この設問を著作権テストと呼ぶ。
著作権テストは満点が7点で、そこから間違いを引いていくという方法で算出している。図3-1-4は著作権テストの各項目の回答の分布である。
なお、グラフ中の項目のあとの「正」は著作権侵害にあたる項目、「誤」は著作権侵害にはあたらない項目である。また、グラフの項目は選択肢の文章を省略して使用している。

図3-1-4をみると、一応は著作権の侵害にあたる項目が選択されていることが多いが、曖昧な項目で正解率が下がっていることが分かる。
特に、「友達にCDから録音したMDを渡す」ことや、「携帯電話の着信メロディとして、許可を得ずに曲をインターネット上に公開する」ことを著作権侵害だと認識していないケースが多くみられた。これらは、日常的に行われてしまっていることであったり、普段良く使用していたりするために著作権の侵害であることに気がついていないのではないかと考えられる。
図3-1-5では著作権テストを点数でみてみる。このグラフでは、著作権テストの全体の点数を示している。全体の得点は約3.4点が平均であった。満点が7点であるので、ちょうど半分くらいの点数になっている。

図3-1-6は学科別にみる、著作権テストの平均点である。これをみると、メディアを扱っている広報学科、パソコンを始めインターネットに関することも扱っている情報システム学科の理解度が高くなっている。
逆に、メディアやパソコンなどに深く触れる機会のない学科の平均点は低くなっていて、また理解の度合いも低いと言える。このことから、著作権が身近な問題であると認識されていないと考えられる。

これらのことから、「著作権」の認知度はTV、新聞のニュースなどで、耳にする機会が増えており、程度の差はあるが知っている割合は高いことが分かる。特に、掲示板サイトでの議論で著作権に関する問題を知ったり、みたりしている場合、著作権の内容などについても詳しく知っているケースが多いといえる。(図3-1-1〜図3-1-3)
内容に関しては、著作権侵害だと分かりやすいものについては、かなりの人数がその項目を選択していた。しかし、分かり難い項目に関しては、回答が分かれる結果となった。(図3-1-4)
また、著作権の「理解」は、普段の学習や興味に影響される部分が大きいといえる。(図3-1-6)
このような状態では、インターネットが普及し情報の送受信が容易になっている現在において、「著作権の侵害」と自覚せずに侵害行為が行われている場合が多いといえる。著作権の詳細な内容についてまで触れることはないと思うが、学校の授業などで著作権についてやどのような行為が侵害にあたるかということや、侵害する(される)ことによってどのような事態が起こるかと言ったことなどについて触れる機械を持つべきではないかと思う。ある程度の知識を持った上で、インターネットなどを使用するようになれば状況は改善される可能性が高いのではないかと考える。
←戻る 次へ→