- 利用者が求める情報の種類、すなわち情報ニーズによって、利用されるメディアは大きく異なる可能性がある。
- インターネット環境にあるか否かによっても、利用されるメディアは大きく異なる可能性がある。すなわちインターネット環境では、従来メディアからインターネットへの移行が起こる可能性は高い。
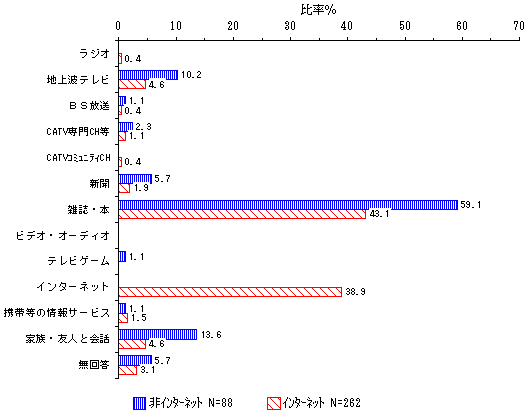
図1.「f.自分の趣味に関する情報を得る」上で最も役立っている手段
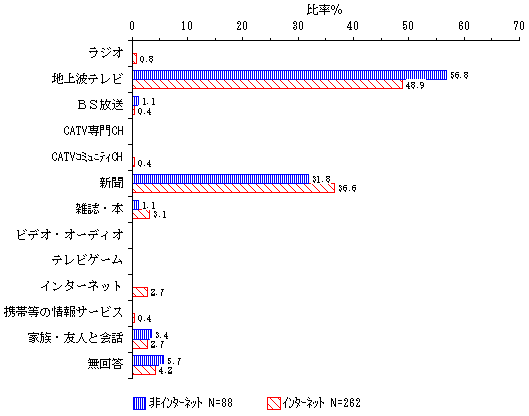
図2.「d.政治や社会の問題について判断を下す」上で最も役立っている手段
はじめに
周知の通りインターネットは1990年代の前半から急速に普及し、2001年12月末での利用率は44.0%であり、とりわけパソコンを利用するインターネットの利用率は38.5%であった(1)。年率では20%弱で伸び続けているので、既に現在は46%程度に至っていると推測される。この様にインターネットが普及して多くの人がインターネットを利用するようになると、従来メディアの利用が様々な影響を受ける。例えば「テレビを見る時間」に着目すると、インターネットを利用するようになって「かなり減った」人が9.3%、「少し減った」人が22.8%、「変わらない」人は67.1%、「少し増えた」と「かなり増えた」人が0.4%という調査結果がある(2)。この結果は、明らかにインターネットの利用がテレビ視聴を減少させていることを示している。同調査では、テレビほどではないが「新聞を読む時間」や「家族と話す時間」、「本を読む時間」もインターネットの利用後に「減少した」と言う人が「増加した」という人よりは多くいる。つまりテレビや新聞、本などに配分していた時間が、インターネットに移行し、新たなメディアの棲み分けが進行していると考えられる。
そうとすれば次には、どの様にメディア利用の変化が進行しているのかという点に関心が持たれる。一つは具体的な利用時間量の変化であるが、この計測は困難で、まだ有効なデータは作られていない。もう一つは、総体としてはインターネット利用に伴う変化が生じているとしても、変化の程度が利用する情報の種類に依存するのかしないのか、インターネットへの移行が起きやすい情報利用があるのか否かという問題がある。そこでこの問題を次のように調査し、明らかにすることを試みた。
現実の過程ではわれわれは情報ニーズを感じると、その都度大概が暗黙のうちに利用制約や利用効果を勘案してコミュニケーション・メディアを選んでいると考えられる。この様な過程で、情報ニーズに対応したメディア選択、つまり利用者が何らかの情報の必要性を感じた際にどの様なメディアを優先的に利用するのかを調査する。そして、インターネット環境下か否かによってどの様にメディア選択が異なるかを明らかにする分析を試みた。
なお本報告の予備的分析については、別地域のデータに基づく分析を別途報告している(3)。今回の報告はその成果を引き継ぐものである。また本報告でのインターネット利用では、携帯電話・PHSのみのインターネット利用を除外している。これは携帯電話・PHSの利用だけでは、メディア利用全般には大きい影響をもたらすことは無いと考えているためである。
調査地域としては、他地域と比べて比較的インターネット利用率が高い茅ヶ崎市を選んだ(4)。茅ヶ崎市109町丁の中から36町丁を無作為で選択し、さらに20歳以上49歳以下を条件に1473人を住民基本台帳から調査標本として抽出し、2002年3月に郵送法で調査を行った。回収数は405票、有効回収数は397票で有効回収率は27.0%であった。
主な調査項目は、本報告で利用する後述の質問項目以外に、新聞の利用、テレビ視聴、地上波放送以外のテレビ利用、雑誌の利用、移動電話・メール・ウェブの利用、インターネットの利用、メディア利用の変化、フェースシートがある。これらは別の意図で利用される予定である。
なお本調査で20歳以上49歳以下に限定したのは、この世代でインターネットの利用率が高く、インターネットの利用者と非利用者を比較する分析のためには有効なデータが得やすくなるためである。限定しない場合には50才以上の層から多くの回答が得られやすいが、この層はインターネットの非利用者の比率が高い。このために世代分布が歪み、歪みを避けるためには多くの回収票が利用できなくなる。これを避けるために年齢制限を設けた。
今回の397票のデータでは、インターネットの利用・非利用ごとに性別、世代別の分布を見たところ、女性30代、40代の非利用層のサンプルが多めであることが分かった。そこで最終的には30代非利用女性サンプル10票、40代非利用女性サンプル33票を無作為に削除した。結果的には、性別および世代で完全に偏りのないデータを作成することが出来た。この報告では1割強のサンプルを活用できなかったが、全般としてみれば当初の意図が生かされた有効なデータが作成できたと考えられる。以下の分析では表1に示すサンプル調整後のデータを利用する。
表1 分析のための調整後のサンプル 男性 女性 20代 30代 40代 合計 インターネット利用
47.7
52.3
29.0
41.2
29.8
100.0
45.5
54.4
31.8
38.6
29.5
100.0合計
47.1
52.9
29.7
40.6
29.7
100.0
本報告に利用している設問を表2に示す。情報ニーズに対応した設問がA.〜K.まで11項目あり、選ばれるべきメディアが「1.ラジオ」〜「12.その他」まで12項目ある。回答者はA.〜K.のそれぞれの情報ニーズに対応して、最も役立つ(優先度の高い)メディアを1つ選ぶことになる。これをインターネットの利用グループと非利用グループに分けて集計した結果を、表3に示す。以下の分析ではこのデータを利用する。
表2 設問:左のA〜Kの各項目を行う手段で最も役立っているものを1つ選択する。 設問項目 選択されるメディア A.海外の出来事や動きを知るうえで
B.日本の出来事や動きを知るうえで
C.地域の出来事や動きを知るうえで
D.政治や社会の問題について判断を下すうえで
E.自分の仕事に関する情報を得るうえで
F.自分の趣味に関する情報を得るうえで
G.人との話題を豊富にするうえで
H.自分の知らない世界や生き方に触れるうえで
I.興奮や感動を味わううえで
J.疲れをいやしたり、気晴らしをするうえで
K.健康や生活の日常役立つ情報を得るうえで1.ラジオ
2.NHK・民放のテレビ放送
3.BS放送
4.ケーブルテレビやCS放送
5.新聞
6.雑誌・本
7.ビデオ・オーディオ
8.テレビゲーム
9.インターネット
10.携帯電話・PHSの情報サービス
11. 家族や友人との会話
12. その他
以下ではインターネット利用と非利用のグループの比較の結果を示す。まず「F.自分の趣味に関する情報を得る」上での選択に関する結果を図1に示す。顕著な傾向をまとめると、次のようになる。次に「D.政治や社会の問題について判断を下す」上で最も役立っている手段の場合についての集計結果を図2に示す。この場合の主な結果は以下である。
- 雑誌・本とインターネットが抜きんでて高い。この2つは趣味情報の代表的メディアである。
- 非インターネット利用者は雑誌・本を選ぶ比率が高い。他方でインターネット利用者は雑誌・本とインターネットを同程度に選んでいる。
- 地上波テレビ、CATV、新聞、家族・友人との会話はすべて相対的に小さく、インターネット利用者は非インターネット者の半分程度である。
- インターネットが他のメディアに優先されており、インターネット利用者と非利用者ではメディア選択はかなり異なる。
- 地上波テレビと新聞が抜きんでて大きく、他のメディアが選ばれる可能性は低い。
- インターネットが選ばれることはない。
- インターネットの利用者も非利用者も大した差はない。
表3 情報ニーズ別のメディア選択の集計結果 1
ラ
ジ
オ2
N
H
K
・
民
放
の
テ
レ
ビ
放
送3
B
S
放
送4
ケ
|
ブ
ル
テ
レ
ビ
の
専
門
チ
ャ
ン
ネ
ル
や
C
S
放
送5
ケ
|
ブ
ル
テ
レ
ビ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
チ
ャ
ン
ネ
ル6
新
聞7
雑
誌
・
本8
ビ
デ
オ
・
オ
|
デ
ィ
オ9
テ
レ
ビ
ゲ
|
ム10
イ
ン
タ
|
ネ
ッ
ト11
携
帯
電
話
・
P
H
S
の
情
報
サ
|
ビ
ス12
家
族
や
友
人
と
の
会
話無
回
答A.海外の出来事 利用 非利用 B.日本の出来事 利用 非利用 C.地域の出来事 利用 非利用 D.政治や社会問題 利用 非利用 E.仕事情報 利用 非利用 F.趣味情報 利用 非利用 G.話題を豊富に 利用 非利用 H.知らない世界 利用 非利用 I.興奮や感動 利用 非利用 J.癒しや気晴し 利用 非利用 K.生活情報 利用 非利用
したがってこの場合には、インターネットがあってもなくても、メディア選択はさして変わりがないことが分かる。さらにこれらの2つの事例を通して、次の傾向を知ることが出来る。
- 利用者が求める情報の種類、すなわち情報ニーズによって、利用されるメディアは大きく異なる可能性がある。
- インターネット環境にあるか否かによっても、利用されるメディアは大きく異なる可能性がある。すなわちインターネット環境では、従来メディアからインターネットへの移行が起こる可能性は高い。
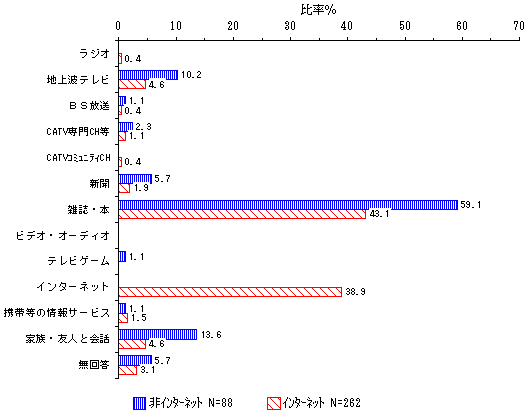
図1.「f.自分の趣味に関する情報を得る」上で最も役立っている手段
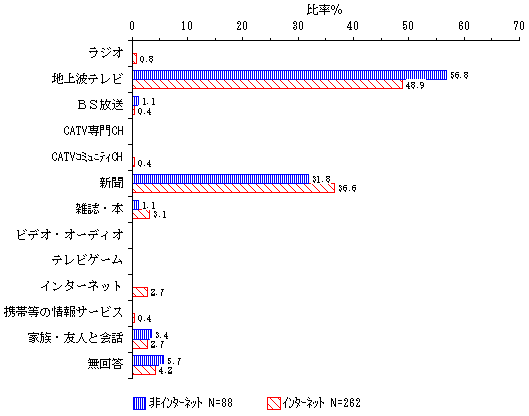
図2.「d.政治や社会の問題について判断を下す」上で最も役立っている手段