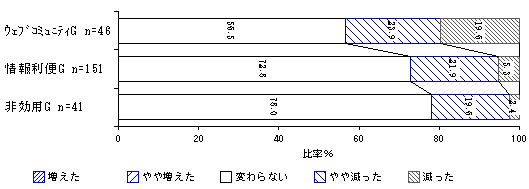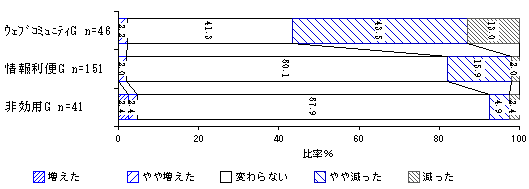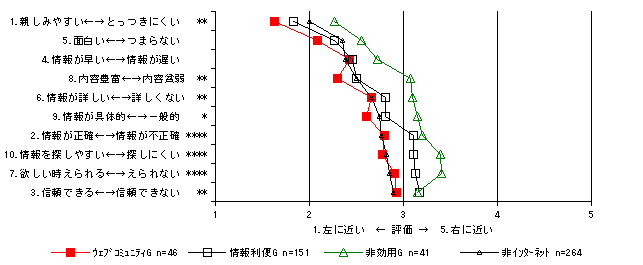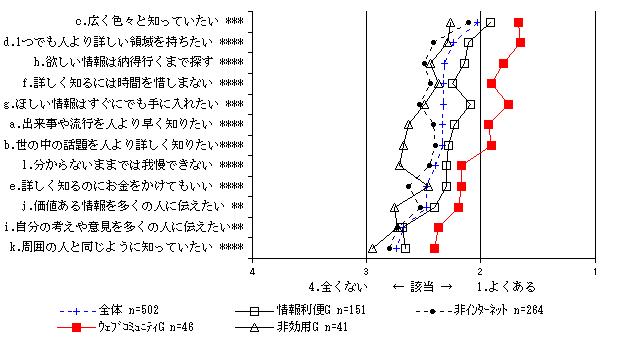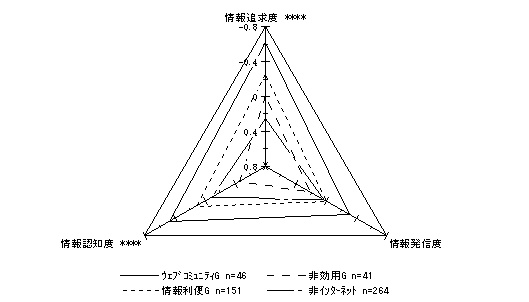前項ではウェブ効用グループ別のインターネット利用の姿を見てきた。それではこれらのグループはメディア利用の変化という点ではどの様な傾向を示すのだろうか。まず図3.3.3.1にテレビと本・雑誌に関する集計例を示す。(1)のテレビの場合にはウェブコミュニティG(減少比率43%)から非効用G(減少比率22%)まで減少比率が単調に減少している。また「減った」比率も急速に減少している。明らかにウェブコミュニティGではメディア移行が強く起こり、非効用Gではその程度は減少している。
同様な傾向は(2)本・雑誌の読書時間でも見ることが出来る。こちらでは僅かに増加したとする人がいる反面で、ウェブコミュニティGでは実に57%の人が、読書時間が減少したと回答している。その傾向とは反対に非効用Gでは、増えたとする回答者2グループの合計が5%いるのに対して減ったとする2グループは7%であり、88%は不変であるから、実質的にはほとんど影響無しとなっている。
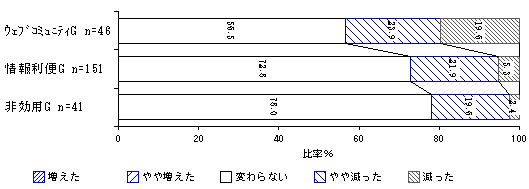
(1)テレビ視聴時間(χ2乗:*)
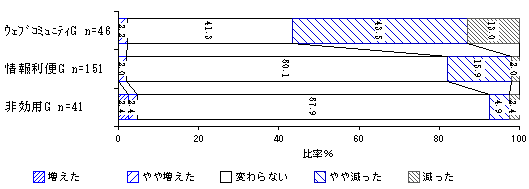
(2)本・雑誌読書時間(χ2乗:****)
図3.3.3.1 ウェブ効用グループ別のメディア利用変化例(日野)
次にグループ別の新聞の閲読時間、家族との会話の時間の変化については、表3.3.3.1に示す。いずれの場合も、ウェブコミュニティGと情報利便G、非効用Gとの差はかなり大きい。ウェブコミュニティGでは明確な時間減少を見て取れるが、他の2者にはそれほど顕著な傾向は見えない。
この様に見てくると、ウェブコミュニティGはインターネットの利用に伴うメディア移行を最も体現しているグループであることが分かる。次いで情報利便G、非効用Gが続くが、後の2者では、移行の傾向はかなり小さいと見ることが出来る。
表3.3.3.1 グループ別の新聞、家族との会話の時間変化
| メディア |
グループ |
増えた |
やや増えた |
不変 |
やや減った |
減った |
新聞
χ2乗:*** |
ウェブコミュニティG n=46 |
|
4.3
|
56.5
|
21.7
|
17.4
|
| 情報利便G n=151 |
|
1.3
|
86.1
|
9.9
|
2.6
|
| 非効用G n=41 |
|
|
90.2
|
4.9
|
4.9
|
家族との会話
χ2乗:*** |
ウェブコミュニティG n=46
|
2.2
|
2.2
|
69.6
|
23.9
|
2.2
|
| 情報利便G n=151 |
|
2.0
|
94.7
|
2.6
|
0.7
|
| 非効用G n=41 |
|
2.4
|
90.2
|
4.9
|
2.4
|
ウェブコミュニティGでは、様々なメディアで利用が減少し、インターネットへの移行が生じていることが明らかになったが、それではこの移行はどのようなメカニズムで起こるのであろうか。この移行については、モデル的には2つの場合が考えられる。
1つは代替要因による移行である。既存のメディアに対する不満がインターネットで解決される、そのためにインターネットの利用が増す場合である。例えばテレビに対して不満があり、その不満がインターネットで解消される場合には、インターネットの利用が増加する、などの場合である。
2つ目は、代替的な欲求よりもより上位の水準の欲求、例えば人々の生活上の時間配分を規定するような水準の欲求が関与する場合である。この場合には何らかの先有傾向、ないしはパーソナリティがメディア移行の支配要因となることが考えられる。これを先有傾向要因による移行としておく。
そこで以下ではこれらの可能性を検証する。
本調査では、3.3.2(2)e.において、インターネットの印象について述べてきた。ここでは民放テレビについて調査した結果を、ウェブ効用グループ別に集計して図3.3.3.2に示す。同図では、全体(n=502)の平均値が1に近い項目を上位に置いている。その結果ウェブ効用3グループは評価結果が明確に分かれ、お互いに交差することはない。そしてウェブコミュニティGは最も民放テレビには好意的であり、次いで情報利便G,最後に非効用Gとなった。非効用Gは3グループの中では反民放テレビ的であると理解される。なお非インターネット層は、ほぼウェブコミュニティGと同様な傾向にある。
同様な集計はNHKテレビに対しても行っている(図省略)。その場合にはウェブコミュニティGの評価が相対的に右寄りになり、情報利便Gと重なる位置にシフトするが、非効用Gが最左端であり、相対的には反NHKテレビ的であることは変わりがなかった。
この様なテレビに対する印象の集計結果と、(1)で述べたメディア移行の傾向を合わせると、テレビに好意的なグループほどにインターネットに伴う移行が起こっていることになり、前述した代替要因による移行では説明がつきにくい。この様に見てくると、テレビとは別の機能を求めてインターネットに移行するという解釈が有効である。そこで先有傾向要因による移行の検討が考えられる。
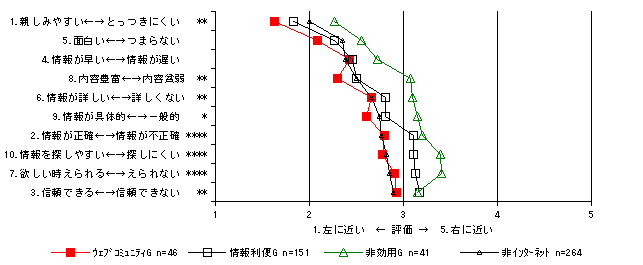
図3.3.3.2 民放テレビの印象の平均値の分布
平均値の検定:*:p≦0.05、***:p≦0.001、****:p≦0.0001
インターネットの利用に伴うメディア移行の要因が何らかの先有傾向にあるとの考えは、あり得ることではあるが、モデル的にはまだ未検討の問題で、なかなか困難である。ここではその可能性を持つ要因を例示的に提示することを目的に、以下にその分析を試みる。
本調査ではテレビの視聴傾向や生活観などをいろいろと聞いているが、その中にいわば情報態度とでもいうべき設問がある。この設問が比較的に有効そうに見えるので、その分析を説明する。 情報態度に関する設問は、例えば「A.世の中の出来事や流行は人よりも早く知りたい方である」に対して回答者が該当する度合を、「1.よくあてはまる」〜「4.まったくあてはまらない」の選択肢で聞いている。この設問に対する回答をウェブ効用グループ別に平均値で集計した結果を図3.3.3.3に示す。
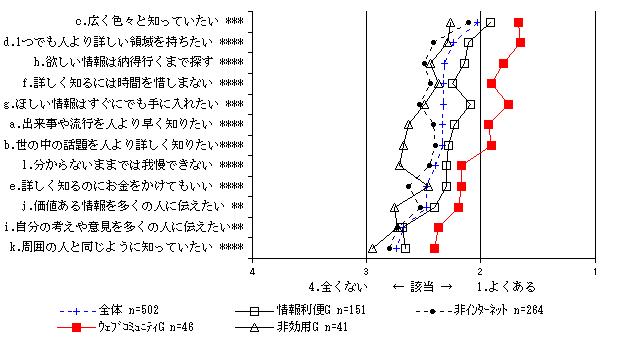
図3.3.3.3 情報態度の平均値の分布
平均値の検定:**:p≦0.01、***:p≦0.001、****:Sig.≦0.0001
同図は全体の平均が1に近い順に上から設問が配列してある。また非インターネット層も図中に記載されている。同図によるとウェブ効用の3グループは、グラフ上では明確に分かれている。さらにウェブコミュニティGはすべての設問で出現が最も多く、非効用Gはすべての質問で出現が最も少なく、情報利便Gは中間にある。また設問によっては分離は拡大したり縮小したり、様々である。
そこで因子分析を使って、議論を簡略化することを試みた。因子分析の結果を表3.3.3.2に示す。なお類似した方法論は川浦(1998)にも見ることが出来る。
表3.3.3.2 情報態度の因子分析結果
| 因子(平方和、寄与率) |
対応する変数(係数の大きい順↓ → ↓) |
第1因子 (2.94, 24.5%)
情報追求度 |
22f.詳しく知るに時間を惜しまない 22d.人に負けない詳しい領域を持ちたい
22e.詳しく知るにお金を惜しまない 22h.欲しい情報は納得行くまで探す
22g.欲しい情報はすぐでも手に入れたい
◎時間やお金を惜しまず、納得行くまで情報を追求しようとする度合を示す。 |
第2因子 (2.63, 21.9%)
情報認知度 |
22b.世の中の話題を人より詳しく知りたい 22l.物事を分からないままにするのは我慢出来ない
22a.出来事や流行を人より早く知りたい 22c.いろいろなことを知っていたい
22k.周囲の知ることを知らないと落ち着かない
◎諸々の事柄を、とりあえずは知っておきたいと言う度合を示す。 |
第3因子 (2.00, 16.7%)
情報発信度 |
22j.価値ある情報は多くの人に伝えたい
22i.自分の考えを多くの人に伝えたい
◎自分の情報を他人に伝えようとする度合を示す。 |
(注)平方和と寄与率はバリマックス回転後の値である。寄与率の合計は63.1%である。
次にウェブ効用グループと非インターネット層の4つのグループ毎に、抽出した3つの因子軸の因子スコアの平均値を求めたところ、各グループは図3.3.3.4のような位置づけになった。この図から各グループの傾向をまとめると、次のようになる(この図では外側の方ほどにその軸の傾向が強くなるように描かれている)。
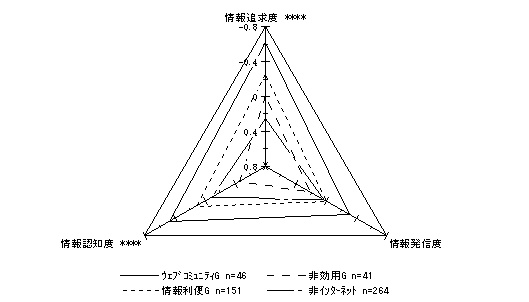
図3.3.3.4 情報態度の因子スコアのグループ別の平均値
平均値の検定:***:p≦0.001、****:p≦0.0001
-
ウェブコミュニティGは3因子ともに傾向が強い。特に情報追求度>情報認知度>情報発信度である。
-
情報利便Gは情報追求度は強いが、情報認知度は平均より若干強い水準、情報発信度は平均の水準にある。
-
非効用Gは情報追求度は平均、情報認知度はかなり弱く、情報発信度は平均である。
-
非インターネット層は情報追求度が弱く、情報認知度は平均より若干弱い水準、情報発信度は平均の水準にある。
この1.〜4.の傾向を、判定量的な意味合いも含めてまとめたのが表3.3.3.3である。
表3.3.3.3 ウェブ効用グループ別の因子得点平均値
|
情報追求度 |
情報認知度 |
情報発信度 |
| ウェブコミュニティG |
◎ -0.6
|
◎ -0.5
|
○ -0.3
|
| 情報利便G |
○ -0.3
|
△ -0.1
|
− 0.0
|
| 非効用G |
− 0.0
|
−◎ 0.5
|
−△ 0.2
|
| 非インターネット層 |
−○ 0.3
|
−△ 0.1
|
− 0.0
|
(注)記号の範囲 △:0.1〜0.2 ○:0.2〜0.4 ◎:0.4〜
さらに情報態度の因子スコアと様々な設問回答との相関係数を見ると、因子軸には表3.3.3.4に示す傾向があることが分かった。この表より次の点を知ることが出来る。
-
情報追求度はインターネットの利用に強く影響する要因である。表3.3.3.3の傾向とも一致している。情報追求度の強弱は、インターネットの利用の有無を規定する可能性がある。
-
情報認知度はテレビの視聴を左右する可能性の高い要因である。図3.3.3.2におけるテレビの印象の傾向は、表3.3.3.3の情報認知度の傾向と一致している。またテレビからの移行を左右する 要因でもある。
-
情報発信度はウェブコミュニティ性を左右する要因である。
表3.3.3.4 情報態度の因子と様々な変数との相関
| a.情報追求度 |
b.情報認知度 |
c.情報発信度 |
情報追求度が強いほど・・・・
・テレビの視聴時間が減る ***
・掲示板閲読時間が増す *
・掲示板記入時間が増す **
・ホームページを見る回数が増す ***
・ホームページを見る時間が増す ***
・定期的に見るサイトが増す ***
・インターネット利用で新聞を見る時間が減る *
・ウェブコミュニティ性(効用)が強い *
・情報利便性(効用)が強い ***
・環境閲読の傾向が強い *
・用件閲読の傾向が強い ***
・年齢は若い **
・高学歴である *** |
情報認知度が強いほど・・・・
・テレビを見る時間が増す **
・インターネットを利用してもテレビを見る時間が減らない * |
情報発信度が強いほど・・・
・ウェブコミュニティ性(効用)が強い *
・環境閲読の傾向が強い ***
・年齢が若い ***
・高学歴である * |
この様に見てくると、ウェブ効用の3グループと非インターネット層は、大筋としては表3.3.3.5に示すように、情報態度に関する3因子で規定できると考えられる。なお表3.3.3.5を作成するに際しては、以下に述べる判別分析を利用している。
表3.3.3.5 情報態度の因子傾向と各グループの位置づけ
|
情報認知度・情報発信度 |
| 強 |
中〜弱 |
| 情報追求度 |
強 |
ウェブコミュニティG |
− |
− |
中
弱 |
−
− |
情報利便G |
非効用G |
| より弱 |
非インターネット |
ウェブコミュニティGと情報利便Gを判別する要因を整理するために、情報態度の3因子を変数とする判別分析を行った。その結果、3つの因子がほぼ同程度に寄与し、判別率が68%で判別できることが分かった。また同じく3因子を変数として情報利便Gと非効用Gを判別する分析を行ったところ、今度は情報追求度は関係なく、情報認知度と情報発信度の2つの寄与で、判別率が60%で判別できることが分かった。判別率の水準には議論のあるところだが、これらの結果は情報態度がウェブ効用グループを規定する有力な要因であることを示している。
これまではインターネットのウェブの効用の観点から3グループを作り、そのグループの特性を分析することで、グループを左右する要因、ひいてはメディア移行を左右する要因の試論を述べてきた。今後の可能性としては、きわめて興味ある問題提起を出来たと考えられる。