 |
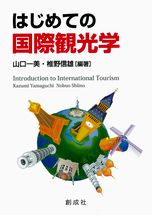 |
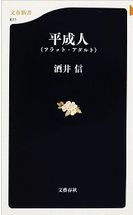 |
||
| �n�������̉�v���v�_ �Γc�@�����@�� �Ŗ��o������@3700�~�{�� |
�͂��߂Ă̍��ۊό��w �R������E�Ŗ�M�Y�@�Ғ� �n���Ё@2300�~�{�� |
�����l�i�t���b�g�E�A�_���g�j ����@�M�@�� ���|�t�H�@746�~ |

 |
||||||||
|
�@ 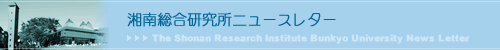
|
|||||||||||||||||
 |
�i�F�Ó쑍�������E�����Y�j |

 |
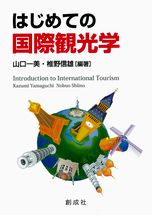 |
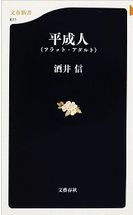 |
||
| �n�������̉�v���v�_ �Γc�@�����@�� �Ŗ��o������@3700�~�{�� |
�͂��߂Ă̍��ۊό��w �R������E�Ŗ�M�Y�@�Ғ� �n���Ё@2300�~�{�� |
�����l�i�t���b�g�E�A�_���g�j ����@�M�@�� ���|�t�H�@746�~ |