分野の異なる講義をバランスよく履修することで、情報システムと情報コンテンツを複合的に活かした研究が期待されます。(→シラバス)
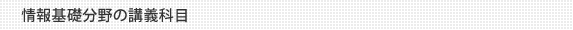
【数理モデル特論】
経営、生産、行政など様々な分野で生じる問題に対し、問題解決策を導く数理的な手法について概説する。まずは、複雑な問題をシステムとして捉え、それを数理モデルとして表現する標準的な方法を解説する。(→詳しく)
次に、数理モデルとして表現された問題に対して最適解を導出するアイディアや解析技術を紹介する。解の導出や解析は素朴なアイディアでは困難なことが多く、理論的な背景や問題の構造の活用が鍵となる。
最後に、導出された解や解析からより効果的な意思決定につなげる技法や、特徴的な問題解決の実例にも触れていく。
【数理モデル演習】
数理モデル特論での内容を受け、経営、生産、行政など様々な分野での標準的な数理モデルの事例を題材とし、そのモデル分析を通じて、なぜそのような現象が起こるのかに答える切り口や問題解決への指針を見つける技法の演習に取り組みたい。(→詳しく)
様々な対象を数理的なモデルとして捉えることは情報学に限らず科学における基本的なアプローチである。自らの研究対象をより明確に捉え分析を行う素養がこの演習を通じ形成されると期待できる。
【プログラミング演習】
研究のためのツールとして、あるいは研究目標として新たなシステムを構築するためにも、プログラミングが必要になる。そのためにはシンプルな文法を持ち、様々なことが記述できるJava言語が適している。(→詳しく)
パソコン上のGUIプログラミングから入り、オブジェクト指向プログラミングの考え方を学ぶ。対戦ゲームなどを題材としてネットワークのプログラミングを学び、最終的には柔軟なデータ構造を用いた人工知能的なプログラムを作成する。
【情報数学演習】
情報科学の土台として欠かせない離散数学の基礎知識と、問題解決のための数理的思考力を養うことを目標とする。(→詳しく)
離散数学は体系的な学問分野というよりも、既成の数学的手法では扱えない個別の難問に対応するための、様々な技法の集大成といった側面が強い。
演習でもそのような特徴を反映して、具体的な問題提起とその解決という形で進めていく。基本的で重要な以下の項目を取り上げる:集合と関係、順序、束、論理、数え上げ技法(漸化式、母関数、反転公式、置換群)、木構造とアルゴリズム、グラフとその応用、輸送回路網とその応用。
【シミュレーション特論】
待ち行列理論の結果を実際の系へ適用する際に、待ち時間や行列長の平均・分散についてだけでも簡単に計算できると都合が良い。(→詳しく)
しかし、到着のしかたまたはサービス時間のどちらかがランダム型でないと簡単な形に表せないとか、数値計算で分布関数についての詳細な情報を必要とするなど問題がある。
したがって実用上は、ある程度あらくても手軽に計算できる近似式とシミュレーションの技法が必要となる。
本講座では上記の件をふまえて待ち行列の近似式とシミュレーションの方法について論じ、待ち行列理論の基礎である[M/M/1]モデルを差分方程式を使って解析する。
【シミュレーション演習】
待ち行列理論の結果を実際の系へ適用を考慮して、以下の内容についてプログラミングを行う。(→詳しく)
1.待ち行列理論の解析には必要不可欠のランダム・ウォーク、マルコフ連鎖などについても論ずる。
2.現実のシステムに忠実なモデルの解析が困難な場合、近似式のあてはめを検討する。この際、近時の精度についても考慮する。
3.同様にモデルの解析が困難な場合、プログラミング言語(C言語)によるシミュレーションを行う。
4.待ち行列における双対性について検討する。
5.論文誌などに掲載されている論文や解説書などのトピックなどについて近似式とシミュレーションなどにより検証する。
【情報システム特論】
今から50年ほど前に、ソフトウェア危機の名の下で、ソフトウェアや情報システムを開発する上での様々な課題が提示された。(→詳しく)
これらの課題の一部は何らかの形で解決されたが、その多くは未解決のままである。特に、基本的な問題として、計画されたQCD(品質、コスト、納期)の未達成の問題、経営戦略と強く結びついた情報システム開発の経営的意思決定の誤りによる崩壊、社会基盤の一部となったソフトウェアの不具合による混乱などはよく知られたところである。
本講義では、最近のソフトウェアや情報システム開発の開発管理上の課題に注目し、その具体例を知るとともに、解決策を検討していく。
【ソフトウェア工学特論】
現在の社会システムやビジネスシステムの状況調査を基にして、情報システム構築、開発、運用管理等システムライフサイクルの側面からソフトウェア工学を概観する。(→詳しく)
以下の項目が研究課題に即して展開される。:
1.導入(もの作りについて、システムについて、社会環境について、ビジネスのシステム要求について)
2.システムとソフトウェア
3.プロジェクトマネジメント
4.システム・デザイン(技術選択と要求定義、ライフサイクル・プロセス、設計指針、試験と確認と実証)
5.ソフトウェア工学の手法と実際:要件定義、機能要素と評価指標、システム要素とプロセス設定、品質管理、信頼性安全性評価、リスクマネジメント、構成管理、ライフサイクル・コストとトレイドオフ
6.保守技術と支援及び管理技術(保守設計、保守活動、保守支援と管理、廃却段階のマネジメント)
7.セキュリティマネジメント
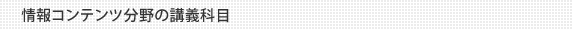
【マルチメディア・コンテンツ特論】
現在、さまざまなメディアにおいて、バーバル・コミュニケーションとノン・バーバル・コミュニケーションが融合して用いられる例が増加してきている。(→詳しく)
本講では、このような複合的なメッセージについて理解を深め、また、効果的な応用を目指して、コンテンツの分析のしかたを学んでゆく。
具体的には、コンテンツは何を訴求しているのかという「訴求内容分析」と、受け手がどのような評価・印象を抱くのかという「受容内容分析」の2つの面から代表的な研究方法を概観する。さらに、さまざまな分析事例について演習形式で検討してゆくので、各学生の持つ課題への応用を考えてほしい。
【映像表現特論】
20世紀は「映像の世紀」と言われるが、これは映像史の出発点が20世紀の歴史の始まりとほぼ重なり、映像(Movie)は20世紀を通して唯一かつ最大の表象メディアとして存在し続け、時代の様々な様相を映し出してきたからに他ならない。(→詳しく)
同時に映像による表現は様々な形態に派生した。この授業では、劇映画はもちろんドキュメンタリー映画や実験映画(アートとしての映画)など様々なジャンルの映像作品を取り上げて、表現の基本的枠組み、特有な文法、さらに技法を考察し、あわせて作家(監督)の表現の独創性がどこにあるかを読み取り、その背景や投げかけられたメッセージを理解する能力を養成する。
19世紀の映像前史から現代の映像作品までを扱う予定だが、現代的な通史ではなく、履修生の希望を聞いた上で、様々なトピックス、作家、主題、技術などでテーマを設けて講義をすすめていく。
【情報デザイン特論】
色彩、イラスト、写真、文字、デザイン知識などの基礎トレーニング後、広報・広告ポスターを研究し表現する。(→詳しく)
イラストレーターとフォトショップのDTP技術と広告発想を身につけることができます。
【CG・アニメーション特論】
CG・アニメーションの企画から制作の理論と実技、さらに、グローバルな展開まで多面的に実践と議論を行う。(→詳しく)
情報化社会の進展と共に映像制作手法は大きく変化し、技術の革新にとどまらず制作システムがインターネットを介して世界規模で展開する状況に至っている。
本講義では、CGアニメーション制作に必要な2D/3Dグラフィックスおよび動画制作手法の特徴の理解と技術を習得した上で、これからの映像制作に必要な知識と企画力および国際分業化時代に必要な技術・体制・マネジメントについて研究を行う。
【ヴァーチャル表現特論】
デジタルを用いた情報表現の演習として、コンテンツ制作をグループワーク形式で行う。(→詳しく)
これは、CGや実写などの素材をもとに、プログラミング言語を用いて、ネットワーク上で動作するゲームなどのインタラクティブコンテンツ制作演習である。
そのコンテンツがいかなる利用者に対してどのような役割を果たすものであるかを考えた企画を行い、情報を整理し、インタフェースやマーケティングを考慮した上で、実際にコンテンツを制作し、これを発表する。
また、グループワークを通じて、各メンバーの得意分野を生かした役割分担と、プロジェクト進捗管理を踏まえた制作を行う。技術的側面にのみ傾注するのではなく、実際にユーザーが楽しんで利用できるようなコンテンツの制作を期待する。
【ウェブ・コンテンツ演習】
本講義では、Webコンテンツの企画・設計・実装・運用・管理に至る各種のフェーズを取り上げ演習形式でコンテンツの制作を行う。(→詳しく)
最初に、企画フェーズでは、ユーザ層の設定や競合コンテンツの調査などをテーマとする。
次に、設計フェーズでは、サイト構造の設計やUI設計、コスト算出と収益予測をテーマとする。
そして、実装フェーズでは、プログラミングだけではなく、スケジュール管理やプロジェクト管理、検証作業や版管理などシステムの実装に必要となる内容をテーマとする。
最後に、運用・管理フェーズでは、システム運用後のWebコンテンツの評価・改善やSEOによりユーザーの誘引についての演習を行う。
【ディジタル・コンテンツ演習】
20世紀にそれぞれ分化してきたメディア専門技術(印刷媒体、放送媒体、通信媒体)はディジタル・メディア技術の進歩に伴い、21世紀において総合的な表現技術として再統合されつつあります。(→詳しく)
すでに分野だけの思考や表現能力では企業ニーズおよび消費者ニーズに対応することができません。総合的なプロデュース能力の視点に立ちながら、かつ最新のHDVによる3D立体映像技術も体験しディジタル・コンテンツ制作を学びます。
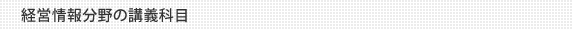
【経営戦略特論】
前半は経営戦略の標準的な図書を読むかたちで進める。そのなかで企業の競争優位を説明する上で競争戦略モデルと資源依存モデルの統合が必要になることを理解してもらう。(→詳しく)
後半は企業経営の実際例を分析し、経営戦略理論を応用するなかで理解を深めていく。具体的な企業の戦略行動の基礎にあるロジックを探るなかで、企業行動の成功や失敗を考える。
各事例における多様な経営上の問題とその解決策をみることで、戦略的思考力の習得を図る。経営学分野を専門としない学生にも、十分に理解できるような講義をめざす。
【金融経済学特論】
サブプライム危機により世界の金融経済は大きな波乱をみせている。この特論においては、こうした状況の中にあって金融経済の先行きはどのようなパラダイムをベースにして展開をみせるかを模索することにしたい。(→詳しく)
まず、伝統的な間接金融、直接金融を軸とするファイナンスをreviewして、それが提起する問題点を浮き彫りにする。そして、それを踏み台として現在、金融界と証券界で急速な進展をみている各種ファンドビジネス等、集団的投資スキーム(collective investment scheme)、およびそれに活用される金融技術(financial engineering)を中心に研究する。
こうした過程で、第1世代の金融技術である派生商品(derivatives)とサブプライム問題で一躍脚光を浴びた第2世代の金融技術の証券化(securitization)についてさまざまな角度から研究を深める。
このうち、デリバティブについては、先物、オプション、スワップの枠組みをベースにして、各種のハイブリッド商品のスペックを検討、実際のビジネスでの有効活用を、ケーススタディをまじえながら模索する。
また、セキュリタイゼーションでは、それが伝統的な金融のコンセプトを大きく変更するコンセプトを具備するインパクトを研究すると共に、サブプライムにおける教訓を踏まえてその効用を最大限発揮できるためのさまざまな課題を検討する。
【ネットワーク産業特論】
インセンティブ・レギュレーションをはじめとする規制緩和の経済理論について考察するとともに、電気通信事業や電気事業など近年その産業組織を激変させているネットワーク産業を例に取り講義する。(→詳しく)
その後、欧米の先進事例を参考に、わが国の既成改革を実現するために、どのような制度を設計すればよいかを競争政策の観点から展望する。
インセンティブ規制としてはプライスキャップ規制とヤードスティック規制を取り上げ、両者のメリット・デメリットを比較検討する。
【管理会計情報特論】
従来の研究テーマとしては十分に議論されてこなかった管理会計情報の戦略的問題とその利用について研究することが本講義の目的である。(→詳しく)
具体的な内容としては、ABC(活動基準原価計算)による製品関連意思決定、ABM(活動基準原価管理)およびABB(活動基準予算管理)の理論的・実践的研究、BSC(バランスト・スコアカード)の戦略的活用、原価企画をめぐる戦略的原価管理、そして管理会計情報の戦略的分析である。最近の論文や著書を用いて研究する。
【情報戦略特論】
情報戦暗において、特に、eビジネスへの対応方法、企業間連携、知的財産問題を学ぶ。(→詳しく)
eビジネスの対応方法については、ネットとリアルのビジネスを情報システムでいかに結ぶかや、カニバリゼーションを避けた効果的なマルチチャネルの販売の方法、ネットショッピングやネットマーケティングでのコミュニティ活用方法を学ぶ。
企業間連携については、ASPを活用した中間業者/代理店の支援、SCMやeマーケットプレイス等での在庫情報の連携、Webサービスを活用した企業間でのプラグアンドプレイプロセスといった手法をもとに、今後の企業間連携での情報戦略を考える。
知的財産問題については、ビジネス方法特許、ソフトウェア資産の権利問題、オープンソース活用方法やオープンソース化のメリットなどについて、具体事例に基づいて学ぶ。
【財務会計情報特論】
現在、会計基準は国際統合化(コンバージェンス)から国際財務報告基準(IFRS)採用(アドオプション)へと大きく流れが変わってきている。(→詳しく)
本講義ではまず、IFRSアドオプションとは何か、さらに、現在の日本のおかれている状況を理解する。次にIFRSとわが国会計基準とで何処が異なるかを検討するとともに、財務報告を読み取る力を醸成する。
【インターネット調査演習】
近年利用が拡大しつつあるインターネット上でのウェブやメールを利用した社会調査の事例を取り上げ、伝統的な社会調査と比較した調査の方法論、特性と適用限界、成功と失敗の要因、実施に際しての課題を学ぶ。(→詳しく)
次に履修生は共通の調査テーマを設定し、ホームページ上で電子メールやCGIを利用したインターネット調査を行う。これによってインターネット調査の方法論を習得する。
また非インターネットの調査も行い、調査結果の相互比較から調査法の特性と適用限界を検証する。
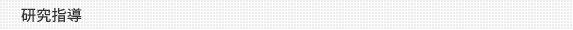
研究指導は、各院生の情報技術に関する専門性を深めながら修士論文を作成するために、1年次より行います。大学院生は、主とする領域(情報システム、情報コンテンツ)の指導教員のもとで個別に指導を受け、修士論文を完成させることになります。
指導教員の選択などは、入学時に行う研究指導に関する研究指導オリエンテーションなどを通して行います。
