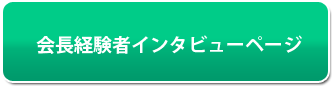田村 徹
元教育学部 学校教育課程 音楽専修教授
元文教大学学園理事長
元父母教 事務局長[1998 ~ 2001年]
(司会)
最初に「父母と教職員の会」の設立等に関係するお話からお伺いできますでしょうか。
(田村先生)
1970年代の学生運動が盛んな時代に文教大学に父母と教職員の会が設立されました。
その当時は家政学部・教育学部合同の教授会で、後藤楢根先生が「父母と教職員の会」を作ろうということを発議されました。私は、「父母と教職員の会」というのは、PTAですかと聞いたら、そうだという話になりましたので、学生運動で、若者たちが高揚している時に、PTA発足は無理として反対したところ、反対するぐらいだから意識が高いと言われて取り込まれてしまいました。
その当時、後藤楢根先生がおっしゃるには、「歴史が浅い大学なので卒業生が少なく、卒業後の学生のアフターケアを保護者の力を借りて徹底して行いたい」ということでした。そういう意味では、先見の明がありましたね。
(秋山先生)
私は家政学部児童学科で幼稚園の教員養成に携わっていました。父母教は主に教員に焦点が当たっていました。その時は、どうして学校の先生になる学生のご父母のために活動しなくてはならないのかと困惑していましたが、結局、お手伝いをすることになりました。
そうしたところ、ご父母の中には学校の先生が多かったですから、そういう方々が本当に力を出してくださって、まだ、卒業生が1人もいない職場にも結び付けるような働きをしていただいた気がしますね。

秋山 胖
元人間科学部 人間科学科教授
前父母教 事務局長[2002 ~ 2009年]
(田村先生)
設立当初は、秋山先生が事務担当で、私は外回りと組織担当でしたが、全国に組織を作るまでには4年かかりました。この4年間は、教職員が「え?大学でPTA?」って首を傾げたと同じように、ご父母の方々も「え?大学でPTA?」と思っていたようで、そこを説得、理解していただきました。支部づくりの中心になっていただいたご父母の方々は、大変なご苦労があったのではないでしょうか。
今でも立派に支部が運営されていることを考えれば、その運営に関わっている方々のご苦労は、今も昔も変わらないということかと思っています。
そうして、1976年(昭和56年)8月22日に創立総会が開かれ、その後1980年に全国組織が出来上がったのは、嬉しい思い出でした。
当時は父母の加入率も80パーセント台で、会費収入も十分あり、学生の部活、就職活動等に支援しました。
(秋山先生)
私は設立総会に出席しました。雨の日の夕暮れでしたが50~60人集まっていました。いよいよスタートするのだ、頑張らなくてはと思ったことを、今思い出しました。
初代会長は、千葉県の学生の保護者、古谷武雄(千葉県教育庁)さんでした。

惠羅 博
情報学部 情報システム学科教授
現父母教 事務局長[2010年 ~]
(秋山先生)
最初は規模が小さかったから、全学教授会で運営していましたが、それぞれ学部が充実してくると全学部教授会などというのは、もう無理ですね。結局、学部教授会が主体になっていきました。
そうした中で、他学部の先生方やご父母との交わりができて「父母と教職員の会」が、新鮮だったし楽しかったですね。
父母教設立当初はよく研修会やなんかで合宿をしていたし、地方に行くと、支部総会や懇親会に出席し交流が出来ました。
(司会)
印象に残っていることなどを教えていただけませんでしょうか。
(田村先生)
湘南校舎で初めて代議員会及び一日大学を行ったことです。その時は、文教大学の教員合格率が全国でも特出していて、その要因の一つに「父母と教職員の会」の存在があるのでは、ということでテレビの取材もありました。
(秋山先生)
テレビで放映されてから、東京圏の大学がどういう組織なのか勉強させてくれと訪ねてみえて、だんだん全国の大学にも同じような組織が増えてきました。当時はまだ目新しかったので、こういった組織の先鞭をつけたという事だと思います。
(司会)
ちょっと先取りしている感じですね。
(秋山先生)
父母教と同様に、人間科学部も私学では最初にできて、他大学が学びにきました。大学がどんどん生き生きしていった時代で、そういう中にいられたことは、自分の研究をしたり、学生に授業をするだけではなく、違った活動をさせていただけたかなという気がします。そういった意味で幸せな体験をさせてもらえたかと思います。
(司会)
惠羅先生は、現在の事務局長としていかがですか?
(惠羅先生)
教員も職員も「父母と教職員の会」を通して発見していくことは、今も変わらないですね。大変有意義だと思っています。ただ、当時は教育学部を中心に、教員になっていく卒業生のためのサービスみたいなのが中心でしたね。
今は、学部が増えたこともあり、各支部の活動に参加してみると教員以外のいろんな就職希望者との関係もあり、なかなか父母教の役割が見えづらい時代になっています。役割というのが徐々に変わってきている気がしますね。
(秋山先生)
役割という意味でうれしかったのは、島原の雲仙普賢岳の噴火の時に、当時の会長を中心に支援活動をしてくれたことですね。
(惠羅先生)
昨年の常総市の水害の時にも学生の実家で数軒浸水被害があり、今までそのような時の規程がなかったので、災害見舞金規程を作りました。
今回の熊本は湘南校舎に9名、越谷校舎に1名在籍者がいらっしゃるのですが、今のところは特に被害に遭われたという報告はありません。
まだ余震も続いており、今後のことは、まだ分かりませんけれども。
(司会)
東日本大震災の時にも特例の措置として大学がお見舞金を出したので、それに合わせて父母教もお見舞いをしました。
(秋山先生)
阪神大震災の時には、在学生の被害状況を父母教が集めて、できるだけ早い対応をしようと動きました。
被害にあった方が経済的に困窮した場合に、こうした援助金を出すことは有効だと思います。学生部長をしていた時にずいぶん助かったのを覚えています。
(惠羅先生)
学生生活援助金として、藍蓼会といっしょに援助しています。
(司会)
今回の熊本地震でもいち早く九州の熊本の支部長に連絡を取りました。
(惠羅先生)
福岡の元支部長を中心に、九州ブロックで西風会という会を立ち上げ、年1回研修会をしています。その繋がりでSNSを通じて支部長に連絡をして、1時間くらいで安否確認が取れました。
地区で集まって、顔見知りになっていると意思疎通がしやすいですね。
今年は地区活動として、夏に東北6県で集まって一日大学を開催し、2月には中国・四国地方でも一日大学を行う計画です。
(秋山先生)
一日大学は、代議員会の翌日に開催していましたが、保護者が大学に来て、授業を担当している先生方に触れる機会として好評でしたね。
(惠羅先生)
今でも代議員会の翌日に越谷と湘南キャンパスの両方でやっていますが、こういう色々な歴史を紐解いて、以前行っていた地方での一日大学も復活させることにしました。昔のような規模ではできないので、小規模にし毎年色々なところでやっていければと思っています。昨年は北陸の福井・石川・富山合同で復活第1号の一日大学を行いました。
(秋山先生)
当初の地方一日大学は吹奏楽部が演奏をして、翌日研修会をしていました。
吹奏楽部だけじゃなく、他の部活も知ってもらうのは大事ですね。
(惠羅先生)
昨年も色々な部活が活躍して、表彰や援助をしました。
(秋山先生)
全国大会といえば、卒業生でオリンピックに出場したマラソン選手もいました。
父母教は全国組織が出来ていますが、支部によっては会員が少なくなっていることが課題です。今後、活動を継続するためには卒業生の同窓会組織の藍蓼会と父母教が一緒になって、大学の知名度を上げ、卒業生と学生のために貢献できる企画を行う必要があると思います。
(惠羅先生)
機会があれば父母教から藍蓼会にお声掛けしています。
(田村先生)
大学や学園のいろんな組織と力を合わせて、一緒にやっていけばいいと思っています。
(秋山先生)
そういう意味では、今後、校友会とどう関わっていくのかですね。
校友会は卒業生も社会で立派に活躍し、指導的な立場の方がいます。そういう方々とも協力して、新しい事業の展開が出来るのではないかと思っています。
(惠羅先生)
父母教としては、大学との立ち位置は、けじめをつけ距離を置こうとしたところがあります。しかし、大学の中にいることも大事にする必要もあるということが分りました。
(司会)
就職関係のことなどですか。
(惠羅先生)
まず学生自身が方針を固めて、そして、それに必要な手立てを父母の方が、あるいはキャリア支援課の方がサポートしていく構造は、しっかりと確立しているように感じています。
(司会)
ありがとうございました。色々貴重なお話を聞かせていただきましたので、今後の活動の参考とさせていただきます。