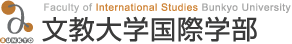


-
NHKラジオ「新聞を読んで」 2003年7月27日
1. 国内では、少年犯罪を含めて、かつては本当にまれにしか起きなかったような事件が頻発しています。こうした事件は、時代や社会を反映しているものであることは間違いありません。それは事件に関して発せられる関係政治家たちの言葉が、ますます軽率になっていることにもよく表れています。人権意識の希薄な政治家たちが、どうして人権にかかわる事件のない社会を造れるのか、と疑問に感じずにはいられません。
2. 発言を取り消せばいい、謝れば済むものではないことが分からない政治家に、世直しなどができるでしょうか。発生した事件に驚き、そしてその後の政治家の発言に唖然とさせられるパターンが続いています。
3. 26日イラク復興支援特別措置法が成立しました。この種の問題が起きる度に考えさせられることですが、日本のあるべき姿として、消極的かつ内向き、つまり何もしない方にマスコミの良心は傾くということです。問題のない時には盛んに国際貢献の必要を説く報道機関ほど、その傾向が強いようです。政党も同じで、いざという時にはひたすら内向き議論で世論に訴えようとする傾向が強いのは、どういうことでしょう。
4. 26日付け朝日新聞や毎日新聞の朝刊は、参議院外交防衛委員会での議員たちのなりふりかまわぬ格闘シーンの写真を載せています。日本の民主主義の成熟度を象徴しているシーンで、驚くほかはありません。
5. 今日は、この採決に至るまでの1週間のイラク問題の報道を振り返ってみたいと思います。
6. 7月23日水曜日の各紙はいずれも、フセイン前大統領の二人の息子が米軍に殺害されたことを大きく報じました。長男ウダイ、次男クサイの二人です。そのいずれかが、やがて大統領を継承すると見られていた人物で、大統領にも勝る強権を振るうことで恐れられていました。アメリカの指名手配リストでも、フセイン前大統領に次いで、2番目と3番目に挙げられていた、まさに大物の最期でした。
7. しかし新聞報道ではほとんど触れられていないのですが、謎は、あの強大な米軍の総力による捜索にもかかわらず、これほどの大物がなぜ3カ月もイラク国内に潜伏できたのか、という点です。見つかったのは、かねてから隠れているのはこのあたりと見られていた、いわゆるフセイン前大統領出身地を中心とするイラク北部三角地帯からそれほど遠くないところでした。
8. 現在イラクに展開されているアメリカ兵は総勢15万人、その中には特殊部隊の精鋭が数多く含まれています。もちろんCIAなどの情報の専門家も投入されています。にもかかわらず、なぜ潜伏が可能だったのか。ましてや一番の大物、フセイン前大統領自身は依然行方不明のままです。
9. 捕り物劇は江戸の昔から、日本人にも大いに関心のあるジャンルです。主要新聞が、フセイン家族の逃亡劇を一日も早く克明に検証してくれることを期待しています。
10. 逃亡者と言えば、1992年から1995年までのボスニア戦争で、非人道的な悪の限りを尽くしたとされるボスニアのセルビア系指導者ラドバン・カラジッチと、セルビア軍を率いてスレブレニッツァという町で、モスレムの男たち7千人以上を虐殺した責任者ラトコ・ムラジッチ将軍も、依然逃亡したままです。アフガニスタンのオサマ・ビンラディンもそうです。現代の情報収集の粋を尽くしても、なぜ逃亡を可能にするのか。大きな疑問です。
11. イラク支援法関連では。自衛隊員の安全が大きな問題にされました。自国の自衛隊員の安全問題を優先させている限り、国際社会の平和に貢献できないことは目に見えています。これまで国連平和維持活動で、北欧諸国をはじめ多くの国の兵士が、外国の平和と安全のために命を落としています。国連では平和の戦士として、彼らに大きな敬意を払います。
12. 紛争後の復興と安定には、イラクであれ、アフガニスタンであり、いまだに問題が残されているボスニアやコソボであれ、国際社会が力をあわせて取り組む必要があるのは明らかです。自衛隊派遣が憲法違反だと見られた時代の議論ならば、意味があるでしょう。しかし今の日本では憲法違反か否かは、もはや議論の対象ではなくなっています。だとすれば、憲法にうたう「平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ」ならば、イラクでも当然日本が持っているあらゆる手段を駆使して、平和を維持し、秩序の回復と復興とに率先して貢献すべきなのではないでしょうか。
13. 22日付日本経済新聞は、自衛隊派遣問題を論じて、「日本政府は治安状況の悪い北部バラドへの自衛隊派遣要請を拒んだ。その後、都合のいい安全な派遣地は容易に見つからず、米国からもめぼしい要請はない」と書いています。このように報道されるのを平気で、日本の自衛隊だけが安全な地へ派遣されることに必死になるのならば、派遣をまったく止めた方がいいのは当然です。こそこそと安全な地を探して派遣してどうして「国際社会において名誉ある地位を」占められるでしょうか。
14. イラク特措法成立をいち早く社説で論じた朝日新聞の26日付社説は、「肝心なのは、どうしたら米政府に喜んでもらえるかではなく、何をすればイラクの人々のために役立つかだ」と主張します。そのとおりです。ところが「自衛隊を派遣するにしても、国連の下でイラク人の政権が誕生し、その要請を受けてからで遅くない」と続けます。
15. 国連の下でイラク人の政権がいつ誕生するか、それこそ雲をつかむような話です。数カ月前に国連の力のなさを憂えたのは朝日新聞も例外ではありません。治安の回復と安定、復興への国際協力、この道筋が出来たときに、イラク人の政府が初めて見えてきます。だとすれば、朝日の主張とは反対に、一時も早く、イラク人の政府ができる状況作りに日本は貢献すべきなのです。イラク人の政府ができれば、日本の自衛隊が出かける意味はなくなります。自前の政府も治安維持機構も経験も持ったことのない新生独立国家、東チモールとはイラクの状況はまったく違います。
16. 21日付け朝日新聞朝刊は、日本の自衛隊が人道復興支援に力点を置く活動であることをイラク国民に大々的にPRする方針であると報じています。イラク国民の理解を得るためのあらゆる努力は必要です。同時に自衛隊を派遣する限りは、国際社会の信頼を得、名誉ある地位を占められるよう堂々と貢献することはもっと大事でしょう。
17. 今国連安保理でも、国連イラク支援団の創設に向かう動きになっていると、23日付毎日新聞のニューヨーク特派員は書いています。戦争前、国連安保理の新たな決議が必要だと盛んに訴えていた日本政府は今、国連での働きかけを停止したかのごとくに見えます。今こそ日本は早急に国連イラク支援団の創設にも懸命の努力をすべきだと政府に訴える新聞記事をと期待していたところ、24日付毎日新聞の社説は「国連支援団の創設を急げ」との見出しを掲げました。
18. そこで注意して読んでみると、「国連支援団創設に向けた協議が実るように、米英政府の決断を求めたい」と書いています。社説の狙いやよし。しかし結論はお門違いと言わざるを得ません。毎日新聞が、国際社会、特に米英政府にどれだけの影響力を自負してこの社説を書いたのか知りませんが、日本の新聞が米英の政府に訴えるよりも、「今こそ日本は国連支援団創設に尽くせ」と日本政府に訴えるべきではなかったでしょうか。日本の新聞は、その力の程を知るならば、遠くの政府に説法するより、自国の政府を動かすことこそが、使命ではないでしょうか。
19. 最近まで国連で人道問題責任者を務めた大島賢三・前国連事務次長が、22日付産経新聞でイラク問題を語っています。戦争前、国連は、つまり大島氏たちは、イラクで百万人の国内避難民と60万人の国外への難民が発生すると見ていたが、実際には難民と避難民合わせて数千人に収まったということです。このようなこともあまり大きく報道されていないのですが、この点について、大島氏は「戦争が約3週間で終結し、しかも米軍のピンポイント攻撃でインフラや人的被害も最小限に抑えられたためだ」と述べています。
20. しかし、日本の新聞で報道されるのはイラク人の不満の声ばかりです。彼らはフセイン政権下では、いかなる不満の声も上げられなかったはずです。また戦争の後の復興が困難なのは十分予想されていたことです。今自由になって不満の声を自由に上げられる社会を、イラクの大多数の人々は本当に歓迎していないのか。フセイン時代に戻せない現実の中で、私には連日イラク人の不満ばかりを載せる新聞の意図が読みきれません。
21. 日本人はとかく、戦争か平和か、あるいは国連決議があるかないか、という2極対立、二者択一思考をしがちですが、戦争のすぐ後ろに平和があることは日本自身が経験したことです。ならば新聞はもっと早期イラク復興というイラクと国際社会の平和と安全のために、日本の貢献の可能性を論じるべきではないでしょうか。
22. もちろんNGO支援やその他の民間人による支援も含めて、国際貢献は総合的なものであるべきです。政府のNGO支援もまだまだ微々たるものです。にもかかわらずNGOだけの貢献で日本の名誉ある地位を占められると報道機関が考えたとしたら、報道機関も名誉ある地位を占めることは難しいといわざるを得ないでしょう。
