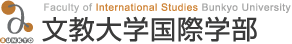


-
新聞を読んで 05年1月9日
1. 今年最初の「新聞を読んで」です。よろしくお願いいたします。
2. 年末から新年にかけて、世界の話題をほぼ独占したのが、スマトラ沖地震と、それによって引き起こされた大津波による災害でした。死者、行方不明者の数は日を追って増え続け、阪神淡路大震災や新潟県中越地震などの体験、さらには、近い将来起こると予想されている巨大地震による被害想定などによって、地震・津波災害にはかなりの精神的備えが出来ているはずの私たち日本人でも、今度の自然災害の規模の大きさには、言葉を失ってしまいます。
3. が、私は今回の災害報道を追っていて、現代人は一種の感覚麻痺にますます陥っているのではないか、という不安に駆られました。
4. そのひとつの理由は、イラクに関連します。米軍の作戦や武装勢力による自爆攻撃などによって、数十人単位の死亡が伝えられるのにも、すっかり慣れてしまっていることです。大量の人の命が奪われているという事の重大さを感じないという麻痺に陥ってはいないでしょうか。今回もひょっとして、死者行方不明者15万人という膨大な数でなかったら、世界はこれほど敏感に反応しなかったのではないか、という不安です
5. もうひとつは、今回、日本をはじめ、北欧諸国を含む多くの先進国の観光客が巻き込まれたことと関連します。2003年はじめのインド西部地震、その年末のイランのバム地方の地震など、甚大な被害を出した地震でも、今回のようには世界は反応しませんでした。もちろん被災者の数が桁違いということもあります。しかし同時に、インドやイランの地震では、先進国の国民の犠牲はほとんどありませんでした。災害規模の大きさもさりながら、自国民が巻き込まれたかどうかは、支援体制でも決定的な違いを生み出します。7日付毎日新聞朝刊の記事によると、2003年12月26日のイランのバム地震の際、国際社会は10億ドル規模の復興支援を表明しましたが、実際に送られたのは、その50分の1にも満たない1700万ドルだそうです。
6. さて、5日付読売新聞朝刊によれば、日本の支援表明は、最初は3千万ドルから始まりました。しかしその直後、米国が3億5千万ドル、中国が6千万ドルの支援を発表したために、日本政府内に動揺が走り、1月1日になってやっと5億ドルという、当時としては最高額の支援が表明されたのだそうです。もっともアメリカも最初から3億5千万ドルの支援を決めたわけではなく、被害が報道され始めた直後、アメリカは、その十分の一の3500万ドルの支援表明にとどまっていました。
7. 新聞では連日、各地での被害者の数が増えていく表と共に、各国が表明する支援額の表も載せたために、まるで国際協力の競い合いが演じられているかのようになりました。そんな中、北朝鮮が厳しい経済情勢の中にありながらも15万ドルの支援を表明したことを、日ごろは北朝鮮に厳しい新聞がきちんと報道したことは、フェアであり、適切な姿勢だったと思います。
8. 各国の緊急支援の取り組みは、6日ジャカルタで行われた、被災国支援緊急首脳会議で、ひとつの頂点に達しました。小泉首相やパウエル国務長官、それにアナン国連事務総長らが出席して行われた会議ですが、この会議では、これまで表明されている支援総額がおよそ40億ドルに達したのに加えて、二つの点が注目されました。
9. そのひとつは、当初アメリカのイニシアチブで作られたアメリカ、日本、オーストラリアなど6カ国による“中核グループ”と呼ばれる支援の枠組みが解体され、国連がリーダーシップを取る緊急支援体制一本に絞られることが、確認されたことです。
10. この問題をいち早く報じたのは、3日付毎日新聞でした。「支援めぐり新たな火種」と題された3面の大きな記事は、イラク復興支援の場合と同様に、アメリカが国連をはずした有志連合、つまり今回の中核グループ構想を進めようとしており、国連や欧州連合、またアメリカの盟友であるイギリスですら、それに強く反発している、ということを伝えました。
11. イラクの二の舞は、世界の良識ある人々は誰もが避けたいと考えていたことです。しかし日本は、アメリカの目指す中核グループに早々と組み込まれていました。この点に関し、日本の新聞は、必ずしも厳しい批判をしていませんが、戦争ではなく、このような人道的活動の場合こそ国連は大きな貢献ができるということを知っている人にとっては、新聞各紙の姿勢は、何とも物足りないものだった、と言えるでしょう。
12. この問題に関連して、7日付読売新聞朝刊は、「国連主導、日本が演出」という大きな見出しの記事を掲げ、外務省幹部の言葉として「米国と国連は関係がよくない。日本は板挟みだったが、米側には、非公式に『国連を活用した支援がベターで、米主導は、批判も米国に集中する』と何度も伝えた」と報じています。これはジャカルタ会議での中核グループ解散の結果を受けて、日本政府の弁明を代弁するかのような記事です。もしそのとおりだとすれば、日本は中核グループに早々と名を連ねる必要もなく、最初から国連主導を堂々と唱えていたら、被災国のみならず、国連を中心とした国際社会、あるいはヨーロッパ諸国にどれだけ好感を与えたことでしょう。残念というほかはありません。
13. この問題で、今は私の推測の域を超えませんが、私は、まもなく国務長官の座を去る、コリン・パウエルさんの功績が大きかったのではないかと見ています。先ほど引用した3日付毎日新聞によれば、パウエル長官は、12月31日にわざわざニューヨークへ出かけてアナン事務総長と会談し、その後被災地を回って、ジャカルタ会議に臨んでいます。3500万ドルの支援額を3億5千万ドルに増額したのは、パウエル長官が大統領に進言した結果だったことも、毎日の記事は伝えています。
14. イラク戦争を巡り、これまで国際協調を重視するパウエル長官が、ホワイトハウスや国防省の強硬派と対立していることが、何度か伝えられてきました。長官引退前の最後の努力として、アメリカはもっと国連を重視した国際協調路線をとるべきだと、穏健派のパウエルさんが政府首脳を説得したというふうに見ると、ジャカルタで、アメリカ自ら中核グループを解散した謎が解けるように読めます。パウエルさんは引退の花道を自らの手で飾ったと、私には映るのです。
15. ジャカルタ会議でのもうひとつの焦点は、国連事務総長が訴えた、支援表明の確実な実行と、支援費目のすり替えの防止問題です。国際協力の世界で、しばしば先進国によって行われるのは、支援費目の移し変えです。どういうことかというと、新たに必要な支援に対して、何億ドルとかの単位で支援を表明します。しかし実態は、その支援活動のために新たに予算を捻出するのではなく、これまで約束しているさまざまな支援の費目を組み直して、新たな費目の名前で出してくる手法です。国連や途上国など、支援を受ける側は、新規の協力だと思って寛大な支援に感謝して喜ぶのですが、いざふたを開けてみると、新たな追加的な予算措置はほとんどないというものです。このような手法は、国際協力活動において、日本も含めてさまざまな国によって使われて、結果的には感謝されることは少ないというのも、めずらしくはありません。
16. こと今回の日本の支援に関しては、7日付朝日新聞によると、「日本の場合、今年度内に支出しなければならない予算として5億ドルを計上した」ということですから、5億ドル全額が新規協力として、国連並びに被災国にまもなく支出されるのは間違いないと思いますが、5日に8億1550万ドルという最高額の支援を表明したオーストラリアの援助は、「借款や最長5年先までの拠出を含めている」のだそうです。支援表明リストは、中身を精査しないと、実際の支援の大きさと効果のほどは分からない、ということを物語っています。ちなみに、今回国連が必要としているのは、今後6カ月間で使える10億ドルです。まさに緊急支援の要請ですが、イランの例にも見られるように、「実態が表明額をはるかに下回る」背景には、国連に拠出を強制する力がないという嘆きです。7日付毎日新聞の記事は、イゲランド国連人道問題担当事務次長の言葉として引用しています。
17. 最後に7日付け産経新聞のロンドン特派員が伝えた重要な記事に触れておきましょう。「UNHCR、初の災害救済活動」と題した記事はUNHCRつまり国連難民高等弁務官事務所が、インドネシアとスリランカで家を無くした被災民の救援活動に当っていると報じています。この国連機関の本来の仕事は、戦争や紛争で国境を越えた人々を救済することでした。それが90年代の初め、湾岸戦争の直後ですが、フセイン政権の弾圧を逃れようとしたクルド族が、国境を越えることが出来ない状態の中、当時国連難民高等弁務官であった緒方貞子さんの英断で、この国連機関としては初めて、「国境を越えていない難民状態の人々」の救援を始めました。以後紛争に巻き込まれた人々は、国境を越えていなくても、UNHCRの救済対象になっていますが、今回はさらに進んで、自然災害の被災民も初めて対象になりました。救援食糧を担当する世界食糧計画WFPとUNHCRとが一体となった活動は、紛争か自然災害かに関係なく、どの組織も真似られない大規模な人道的支援が可能です。今回のUNHCRの決定を心から歓迎して、今年最初の私のコメントを閉じたいと思います。
