大学院情報学研究科、情報学部の竹林紀雄教授が3月24日付東京新聞夕刊に大型コラム「SNS時代のメディアのあり方を問う」を寄稿しました。
本稿は、新聞やテレビといった既存メディアの影響力が低下し、偽情報や誤情報も氾濫するSNSが民意に大きな影響を与えている現状を踏まえて、メディアのあり方について述べたものです。
映像表現や映像メディア研究を専門とする竹林教授は、日本映画監督協会理事、文化庁芸術祭執行委員会委員、山形国際ドキュメンタリー映画祭やFNSドキュメンタリー大賞の選考委員をつとめられるなど映像メディアの発展のための学外活動にも取り組んでいます。
記事についての詳細は以下の通りです。
【掲載紙】
東京新聞夕刊
【掲載日】
3月24日(月)
【記事タイトル】
「SNS時代のメディアのあり方を問う」
※画像をクリックしていただくと新聞の記事の全文をご覧いただけます
※この記事は著作権者である竹林紀雄教授の許可および東京新聞への確認を経て、全文公開しております。

【竹林紀雄教授のコメント】
近年、YouTubeやInstagramといったSNSの台頭により、新聞やテレビといった従来のマスメディアの影響力が低下しつつあります。特に若年層を中心に、SNSが選挙などでの民意の形成に大きな影響を与えていることに注目しています。
例えば、斎藤元彦兵庫県知事の選挙や、トランプ米国大統領の再選をめぐる動きにおいても、SNSが支持拡大に寄与した可能性が指摘されています。また、国会では与野党7党が、選挙をめぐるSNS上の誹謗中傷や偽情報の拡散への対策を含む公職選挙法の改正について議論を進めています。
しかし、問題は単に有権者がSNSの偽情報に踊らされたということではありません。選挙への影響の背景には、もともと存在していたマスメディアへの不信感や既得権益に対する反発があり、それがSNSを通じてうねりとなった可能性が高いと考えられます。
危惧すべきは、マスメディアとSNSそれぞれが抱える問題が、メディア間の相互不信を生み出し、それが社会の分断につながることです。いま情報の受け手である私たち一人ひとりに、メディアのあり方を考え、冷静に情報を判断する姿勢が求められています。
このコラムを本学のメディアや情報を学ぶ大学院情報学研究科や情報学部の院生・学生のみならず、多くの学生の皆さんに読んでいただければ幸いです。
その他の最新の教育・研究



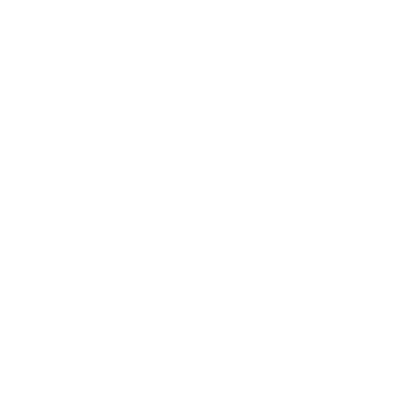


 本学で学びたい方
本学で学びたい方 在学生の方
在学生の方 保護者の方
保護者の方 卒業生の方
卒業生の方 一般・企業の方
一般・企業の方

